FAIクラブの投資法について
連載
第3章 30項目のルール その2 会社内容の分析
(予定している項目) 相場のための会社内容の分析とは 具体的な資料の作り方
ルールの解説 これからの企業情報開示(連結主義・時価会計主義)
上手な電子データの利用を考える
[1]FAIの会社内容分析とは
FAIの銘柄選定は、テクニカル分析が主体である。「株価は上げ下げを繰り返す」という単純な理論を前提としている。だから、下げきった銘柄を探し、長期的なトレンドの転換点を見つけようというわけである。
しかし、下げて安値に来た銘柄にはそれなりの理由があるわけで、安いものを買えばいいということにはならない。買った後下がらなくても、上がらなければ何の意味もない。また、予想外に下げが続いたりすれば、上げたときに率の良い低位株だけに被害も大きいのである。中には倒産してしまう銘柄にぶつかる可能性も、価格の高い銘柄に比べて格段に高い。
だから、チャートの分析と併せて会社の内容も慎重に検討していくわけだ。ところが、内容の良い会社が安値に放置されているはずがない。FAIでは、「今は良くないが、これから良くなっていく」銘柄を探すために、手間をかけてファンダメンタル分析をしていくのである。
ルールの20~26がファンダメンタル分析についての項目である。ルールの解説とともに、FAIの資料整理のノウハウを紹介していく。
[2]データ・スリップ
データ・スリップという言葉は他では聞かない。FAIだけで使われている用語である。和製英語のようである。スリップ(slip)は紙の小片という感じの言葉であろう。正しくはシート(sheet)であろう。英語の教室ではないので、あまり気にせず進めていくことにする。とにかく、FAI投資法で会社内容の分析に使うファンダメンタル資料である。
データ・スリップは、日経の会社情報、または東洋経済の会社四季報を整理していく資料である。会社情報・会社四季報は年4回、3・6・9・12月に発行される。発行されたものを切って、銘柄ごとに1枚の紙に並べていくのである。
非常に面倒くさい作業だが、これがとても重要な意味を持っている。その理由と具体的な方法を説明していくことにする。
[3]変化をとらえるために
会社情報は、上場および店頭登録銘柄の財務データが載っている。株価の推移についても大ざっぱだが一応載っていて便利である。なぜ、わざわざ切り取って紙に貼り付けるのか。その理由を説明する。
株を買う理由は、人それぞれである。それらの分類は別にして、FAIは株価の変化だけを純粋に追求する売買技法である。低位に放置されていて現在の内容は思わしくないがこれから良くなる会社、あるいは内容はそれほど悪くないのに売られ過ぎている会社を見つけて、楽に値上がりを取ろうというものだ。そのかわり、銘柄探しには手間をかけようというのである。
チェックする項目は、比較的少ない。
- 1株あたり純資産
- 日本証券決済の大株主順位
- 人員整理、資産売却
- 経常利益
- 同業種の先導銘柄の動き
- 無配が何期続いているか
- 債務超過ではないか
変化は、実績の変化だけではなく、予想の変化、予想と実績のギャップと企業ごとの傾向などを注意深く見ていく。新聞に発表された業績の修正なども用紙に貼りつけていく地味な作業が要求される。
(注)
機関投資家やプロの相場師は、まったく同じような資料作りをしている。特にFAIだけに限られたものではない。
また最近は企業情報がCD-ROMなどの電子データで安く販売されている。これらを使えば分析やスクリーニングが容易に出来るが落とし穴がある。予想が変化したときに、単純に数値が上書きされてしまい、予想の変化の経緯が記録として残らないのである。やはり儲けるには手間をかけなくてはならないようだ。
[4]データ・スリップの作り方 (1)台紙の準備
紙はB4サイズがおすすめである。A3の方が1枚にたくさん貼れるのだが、枚数が多いので扱いにくい。FAIクラブでは、持ち運びも考えてB4サイズに統一している。(複数で討論するために持ち運ぶ)
紙は普通コピー用紙として使われているもの。紙は重さで厚さを表しているが、一般的には「厚口」「薄口」などの表現で売られている。データ・スリップに使うのは「中厚口」というもので十分だと思う。最近はパソコンの普及で紙の消費量が増えている。そして、街のパソコンショップで、いろいろな紙をかなり安い価格で売っている。
紙を買ってきたら、紙の右下に文房具屋で売っている回転式のゴム印で証券コードをスタンプする。コードは4桁なので、4桁のゴム印を用意する。だいぶ前に証券コードを8桁に増やす計画があった。上場企業・店頭登録企業が増えたことに対応するためである。しかし、バブル崩壊で証券会社の経営が思わしくないために延期となり、そのまま絶ち消え状態となっている。(システムの変更に費用がかかる。)とうぶんは4桁のままであろう。
銘柄は対象とする東証1部から、銀行、ガス・電力を除いたものである。スタンプを押すのに銘柄コード表が必要になるが、市販のチャートブックや業界新聞などに一覧が載っているのでこれを利用すればいい。手元にない場合、取引している証券会社に頼めばくれるだろう。
[4]データ・スリップの作り方 (2)会社情報は3冊必要
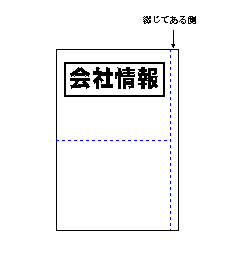 まず、会社情報を3冊買う。銘柄ごとにバラバラにして台紙に貼るので2冊必要。それから予備、というか手元に残すものが1冊で、合計3冊というわけである。
まず、会社情報を3冊買う。銘柄ごとにバラバラにして台紙に貼るので2冊必要。それから予備、というか手元に残すものが1冊で、合計3冊というわけである。貼るための2冊はカッターで切っていくのだが、これが重労働。今は一般の文房具店で特殊なカッターがいろいろ売られているが、手作業は厳しい。おすすめの方法は印刷屋さんの裁断機である。プロの使う裁断機は、会社情報のような厚みのあるものでも、スパッと切ってくれる。小さな印刷屋さんと仲良くなって、安くやってもらうといいだろう。
切る場所だが、多少印刷のずれがあるので、無難なところを決めておく必要がある。
2冊切ったものが用意できたら、仕訳の作業だ。コード番号のリストを見ながら必要な銘柄を順番に取っていく。1000番台、2000番台と区切りをつける。そして、それぞれいらない切れ端で挟み輪ゴムやクリップで止めておく。せっかく仕訳したものがバラバラになると頭にくるからである。
仕訳をしていくと、かなりの枚数でゴミが出るが、すぐに捨ててはいけない。取り忘れがときどきあるものである。
[5]データ・スリップの作り方 (3)上手に糊づけ
仕訳したものを台紙に貼っていく。なかなか根気のいる作業だ。面倒くさいことが嫌いな筆者は、どうやって楽をするかを考えるのが得意である。
図のような方法を考えていろいろな人に紹介したところ好評で、いまだにこの方法で貼っている。
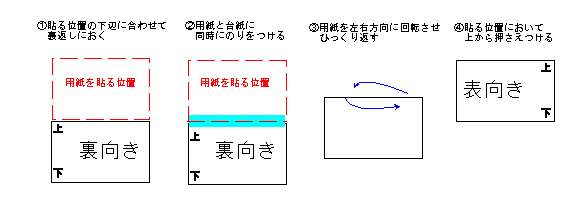
この方法だと、1回の糊づけで用紙の上辺と下辺の両方に糊がつけられる。②のところで、貼る位置の下辺は台紙に、上辺は会社情報を切った用紙の方に糊がつくわけである。
[6]データ・スリップの作り方 (4)会社情報と日経の修正記事
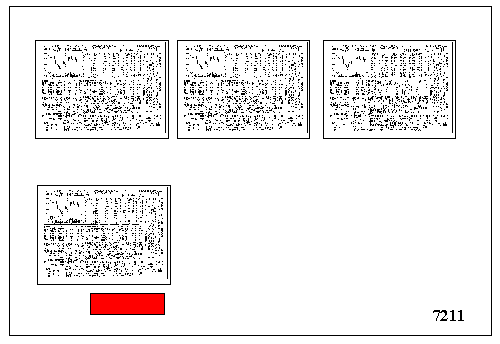
B4の台紙に、切り取った会社情報が6枚、つまり1年半分貼ることができる。その他に毎日日経新聞に掲載される業績データを切り抜いて貼っていく。決算と予想の修正の数字部分だけを切り取って、台紙に並べてある会社情報切り抜きの下に糊で貼っていくのだ。解説の記事をスクラップする必要はない。解説記事は、すでに周知のことを最新のニュースのように書いてあったり、会社によって扱い方が均一ではない。情報としては、歪み、偏り、雑音が多く、マイナス面が多いと言えるからです。我々が必要なのは読み物ではない。安定して供給される一定範囲の数値情報なのである。
(左図の解説)
左上から発行順に右に貼っていく。つまり、左下の切り抜きは4番目となる。
赤い四角のところに、日経の決算・業績予想修正を貼る。
[7]データ・スリップの作り方 (5)台紙の管理
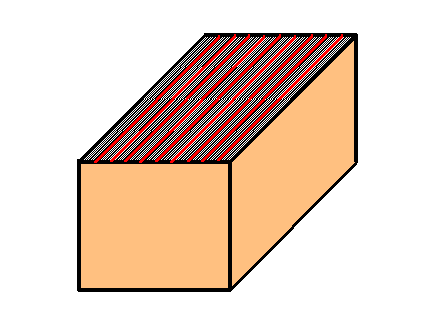 銀行・ガス・電力を除いても、かなりの銘柄数がある。管理方法に一工夫必要である。
銀行・ガス・電力を除いても、かなりの銘柄数がある。管理方法に一工夫必要である。さて、バラバラの紙がたくさんあれば何らかのやり方で綴じてみたくなるが、これはおすすめしない。FAI投資法では、個別に見るだけでなく常に比較をしながら検討していくことが多い。また、機関投資家のように銘柄に制約がつけられているわけではないので、比較の対象は全銘柄になる。つまり、業種に関係なく個々の銘柄のデータや月足を並べてみる作業を行うことになるのである。
だから、1枚1枚バラバラのまま保管しておく。しかし、積み上げておくと具合が悪い。一部にしか切り抜きを貼っていない状態だと、場所によって高さが大きく違うから傾いてしまうし、だいいち、真ん中の1枚を抜くことが出来ない。
おすすめは段ボール箱である。適当な大きさの段ボール箱を用意し、台紙を横長にして1枚1枚を立てた状態にするわけである。
どこに何があるかわかるように、業種ごと(コード番号)に厚手の紙を入れて区切りをつけておく。この仕切紙を余分に作っておき、途中の1枚を抜き出すときに縦方向に差し込んでおく。そうすれば、その1枚を戻すときに楽である。
会社情報は従来1ページに2銘柄掲載されていたが、一部の銘柄について掲載データが増え、1ページ2銘柄ものと1ページ1銘柄ものが混じってしまった。
切り抜き用に2冊用意すればよかったものが4冊必要になり、仕訳に2倍の時間がかかるようになり、1ページ1銘柄だと1枚の台紙に3回分しか貼れなくなってしまった。非常に具合が悪い。
これを解決するため、実験的に進めていた電子データ版のデータ・スリップを、FAIクラブの正式なものとして採用した。
このコーナーでは、あとで詳しく述べる。
[8]1株あたり純資産
ルール20 1株あたり純資産の増加は買い。3期連続増加は絶好
ただし、ここで3連続陽線などで上げていれば売り
「第2章「8」裸値」で、ルール6について解説した。
ルール6 1株当たり純資産に食い込んだら注意
1株あたり純資産と株価が同じ場合、PBR(株価純資産倍率)1.0倍となる。PBRが大きいほど割高、逆に小さいほど割安と言える。
FAIでは、PER(株価収益率)は役に立たないと考えているが、PBRは唯一有効な株価指標として注目している。もちろん、これだけで銘柄を選択することはなく、いつでも月足を中心に総合的な判断をするわけだが、PBRは重要視している。
さて、この1株純資産。やたらと大きく変化を見せるものではないが、低位の銘柄で大きく変化する例は少なくない。低迷後に著しく回復した結果1株純資産の増加率が顕著になる場合は買い、というわけである。
「ただし、ここで3連続陽線などで上げていれば売り」というのは、株価が先見性ですでに上がっていたら、追いかけて買ってはならない、という意味である。
[9]日本証券決済
ルール21 日本証券決済が大株主10位以内に出てきたら買い
現在の完全振替決済制度ができるまでは、名義書換をして株主としての権利を得るために手間がかかった。手数料を払って名義書換に出し、その間売ることが出来ない。あるいは、証券会社から株券を引き出して信託銀行に持ち込む方法もあった。これだと日数はかからないが、かなり面倒くさい。
だから、無配の銘柄を(値上がり期待で)買っても名義を書き換える人はほとんどいなかった。また、バブル期には、株の単価が上がって配当利回りが落ちた上に、値上がりの魅力で配当への関心が極端に薄れた。
低位で無配の銘柄にジワジワと人気がつきはじめ株主の入れ替わりがおきると、名義書換放棄の株券が大量に発生する。こういう株券は、株の流通機構の中にある日本証券決済名義で名義書換が行われる。事故株券をチェックするためだ。こういう株券が「日本証券決済大株主」として登場するわけだ。実際は、特定の大口投資家の登場がほとんどだったかもしれないが。
とにかく、証券決済が大株主に登場した低位銘柄の上昇は、必ずではなかったが、確率の高いものだった。FAI投資法を知らなくても、これに注目して売買を実践している人は多かった。だったというのは、現在は保管振替によって手数料や売れない期間が必要なくコンピュータ上で名義書換ができるために、日本証券決済が大株主に登場することが皆無になってしまったからだ。
[9]人員整理
ルール22 人員整理および資産売却は買い
一見悪材料だが、業績が低迷し株価が安値に来ている企業が人員整理や資産の売却をしたら、これから良くなるための一手である。
基本的に
- 高値での好材料は売り
- 安値での悪材料は買い
例として筆者がよく出すのは、野村証券のバブルの天井である。高値5,990円をつけたのは1987年4月20日である。永遠に株価が上げ続けるかという雰囲気の1989年の月間終値平均は3,500円を下回る水準。ご存じのように1990年は年初から一転下向きになり下げ続けた。1990年9月には1,320円の安値をつけている。
株価には先見性がある。「今どうなのか」ではなく、「これからどうなるのか」が株価として現れる。市場では、他人より少しでも早く動きをつかんで儲けようとするのだから当然だ。
前に典型=例外と述べたが、野村証券の例、これこそ典型と言いたくなる。
安値でも同じこと。バブルの頃の話になるが、1986年に石川島が無配転落した。この直後から大きく株価が上がっている。
1987年に東芝機械がココム(対共産圏輸出規制)違反で騒がれたが、当時400円前後で底練りしていた同社の株価は、ピクリとも下がらなかった。
[10]経常30%以上の増益
ルール23 経常利益予想が30%以上増加だったら注意
FAIでは経常利益に注目する。経常は「けいじょう」だが、「計上」と区別するため「けいつね」と読む。私立=わたくしりつ、市立=いちりつ、と同じ。
前項で書いたように、今ではなくこれからどうなるかが問題なのだから、まだ来ない将来を考える。だから予想の数字を見る。ところが、予想は簡単に鵜呑みにはできない。基本的には、その会社自身が出す数字が公表されるから、どうしても目標的な数字、つまり楽観的になりがちである。もちろん企業によっては非常に丁寧に、とても控え目に数字を出すところも少なくないが、背伸びした数字が多くなる。1冊の会社情報を見ているだけでは絶対に気がつかないが、予想がどう変化していき、結局実績はどうだったのかがデータ・スリップによってとてもよくわかる。
そして、分析するときは、わずかな増加は無視する。30%以上増益の予想が出て、はじめて注意するのである。
[11]先導銘柄
ルール24 同業種の先導銘柄が上昇に転じたら選定銘柄に注意、買いの準備
循環物色という言葉がある。株式市場が活況のとき、次々に出遅れの銘柄が物色されていく動きだ。こういうときに選定されている銘柄の先導役的な銘柄が上伸したら注意をせよ、というルールである。おおよそ3ヶ月遅れて関連の銘柄や子会社が動くのである。
「注意せよ」といっても、あわてて選定銘柄を選んだり、関連のものを何でも買えということではない。あくまで、(ルールによって慎重に選ばれた)選定銘柄の先導銘柄が動いたときは、人気の波及によって動くであろうから、買い場を逃がさないようにしろ、と言っているのだ。
なお、先導銘柄とは、そのときの人気銘柄とか、その業種の代表格のものを言う。明確な定義はない。
[12]安全第一
ルール25 5期連続無配および債務超過はチャートが良くても避ける
チャートの形が良くても、内容に大きな不安がある場合避けなくてはならない。安定配当を重視する日本で5期連続無配は厳しい。また、債務が総資産より大きい債務超過というのも、かなり厳しい状況である。
低位に甘んじている銘柄には倒産の危険もある。安全を重視するのがFAIの投資法である。
ルール26 前期が赤字で、今期が経常または税引きトントンの銘柄に注意
赤字や無配の会社は、一般的に避けられるものである。機関投資家などは、他にどんな要素があっても投資対象として選べない。
もちろんFAIでも倒産のリスクには気を配っているが、赤字、無配というだけで対象外とすることはない。安値にある低位株ではよくあることである。今悪いが倒産までは心配なく、これから良くなるものが大きく上がるのである。まして赤字の場合、実体以上に売られている(評価が低い)ものである。うまく上昇に転じるところをつかまえれば、おいしいのだ。
赤字の会社が、月足チャートで安値から上げの兆しが感じられ、なおかつ、経常または税引きの利益がトントン予想なら要注意となるわけである。しかし、[10]経常30%以上の増益で解説したように、予想を簡単に信じてはいけない。特に赤字の会社なら、あまり見込みがなくても「今度はいちおうトントンの予定です」という感じになるのは当然だからだ。
この章でのルール解説は、これで終わり。ルールの15,17,18,27,28,29,30、以上7つについては、次章以降で予定している具体的な売買の解説で触れたい。
引き続きファンダメンタル分析について本章を続けたい。
[13]国際会計基準と連結主義 (1)会計が変わる
会計などという言葉が出てくると、どうも難しそうで逃げてしまう。筆者自身も詳しい知識はなく、あまり難しいことはわからない。しかし、株の売買を実践するための知識なんて限られたもので十分である。会社情報で特定の数字を拾って限られた範囲で分析をすればいい。企業診断をするわけではない。株の売買で利益を上げることができればいいのだから。具体的なやり方は、この章で解説したとおり。
ところが、
企業が公表しているファンダメンタルのデータが、世界の常識から大きく外れているから変更しましょう
ということになった。ビッグ・バンのひとつなわけだが、とにかくいろいろと変わるらしい。ちょっとだけがんばって勉強してみよう。
[14]国際会計基準と連結主義 (2)開国と会計基準の統一
外為法が改正され、日本でも外貨を持てるようになった。日本は21世紀を目前にして、やっと開国したことになる。しかし、他国との間には海があり、日常生活に大きな変化は見られない。
ところが金融の世界は違う。物が介在せずにお金だけを動かすのだから、もともと国境が無いに等しい。取引のルール、マーケットの構造などの規格が同じなら、非常に効率よくお金が行き来することになる。デファクト・スタンダードである欧米式のルールに合わせ、業者に対する規制を無くすのが、自由化(金融ビッグバン)である。
ビッグバンで身近に思うのは「手数料の自由化」であるが、回数が極端に多いような、かなり特殊な売買をしない限り、大きな影響はない。問題は「儲かっているかどうか」である。損の売買は手数料がタダになってもマイナスである。お金を預け、電話などで注文を出す証券会社の信頼度(安心して売買に専念できるかどうか)を第一に考えればいいと思う。
さて、本題の会計基準について。
FAI投資法で「1株あたり純資産」「経常利益」などを見るが、これは他社との比較やランキングをするためではない。その会社の数字の変化率を見るのが主な目的である。そういう意味では、会計基準などどうでもよさそうだが、根本のルールが変更されるのだから、原則的なことを確認しておくことにする。
(次回から会計基準変更のポイントとFAIクラブ内部での議論について)
[15]変更のポイント (1)時価会計
日本では金融資産が時価(現在の価格)ではなく、取得原価(買ったときの価格)で計算されてきた。これだと、時間の経過・状況の変化によって生じるプラス・マイナスが表に出てこないことになる。
たとえば、企業が他社の株式を買って保有していたとする。
1.買い値より下がっている(含み損がある)
下がろうがなんだろうが、「売らなければ損ではない」というのが原価法による計算である。株式投資に大きく傾倒し、ボロクソにやられていても「問題なし」ということである。株主は、たまったものではない。
2.買い値より上がっている(含み益がある)
1と違って問題とはならなさそうだが、「所有している資産が増えているのだから、表面に出すべきである」というのが時価会計の考え方。本業の利益が同じなら、資産増加によって総資産利益率といった経営の効率性を表す指標が悪くなることになる。
マイナス面を嫌うだけではない。株主(あるいは市場参加者)が、様々な角度から企業を評価する。企業は、株式を公開して市場からの資金調達を容易にするかわり、責任を持って数値を正しく公表する。なあなあではない、緊張感のある関係が求められているのである。
[16]変更のポイント (2)連結主義の導入 その1 お化粧
決算には、その会社だけのデータである「単独決算」と、グループ会社を総合した「連結決算」がある。
日本では単独決算が重視されているが、欧米では連結決算を見る。日本でも連結決算を主とする方式に切り替えようということである。
単独決算だと利益の操作が可能となる。たとえば、不良在庫があり、それを言うことを聞く株式未公開の子会社に売却したとする。子会社とはいえ別法人に売ったのだから売上として計上され、一定の利益も計上される。グループとしては今までと同じ在庫を残したまま、業績を公表する親会社が「見せかけの利益」でお化粧するわけだ。社会問題となった「飛ばし」である。もちろん、この逆をやれば利益の圧縮も可能である。
[17]変更のポイント (3)連結主義の導入 その2 連結の基準
一般に重視されていなかっただけで、従来より連結決算は発表されている。だから前期の利益操作は不可能のようだが、問題となるのは、連結対象の基準である。
従来は持ち株の状況によって区別をしていた。「50%超の株式を保有している」ことが条件だった。だから、実際には支配力を持っている子会社でも、連結対象とならず利益操作に利用される可能性があった。今後は、従来の持ち株基準から、実際の支配力基準をもとに判定することになり、きちんと実態を表す連結決算が発表されることになる。
前述の例で言えば、子会社から再びグループ外の企業に製品を売った時点で、はじめて正規の売上として認められるようになるわけである。
[18]新しい時代の分析 (1)FAIクラブで具体的な議論がはじまった
2000年に入って、久しぶりに買い銘柄を選定した。1988年以来だから、12年ぶりの再開となるわけである。その間にバブルが崩壊し、従来の村社会で構築されたルールが根底から否定されることになった。とにかく不合理な点が多く、なにより「右肩上がりの経済」「横並び」「官主導」「銀行中心の企業社会主義」という独特の価値観が前提となっていた。それを世界標準(アメリカ式?)にするのがビッグバンであり、FAI投資法にとっての変化は、前述の通りである。
さて問題は、具体的にどうするか、ということである。
1988年に、
極端な上げ相場であり
天井の可能性が非常に高く
危険な下げ相場に入ることが予想される
との見通しで、FAIクラブは銘柄選定を凍結した。これは大正解であり、月足を冷静に分析し、多数で質の高い討論をすることの意義が証明された。これからも従来通り真剣な討論を続けていくが、昨年からの大きな議題は「ビッグバンによる変化にどう対応するか」である。この問題について、毎月の例会で討論を行っている。その内容などについて続けていくことにする。
[19]新しい時代の分析 (2)連結決算とデータスリップ その1 データ増加
1988年までは、連結決算を見ることがなかった。まったくゼロではなかったが、ほとんど気にすることはなかった。今後は連結決算を見て判断をすることにある。
しかし、FAIで見る項目は何も変わらないから、連結対象の企業を従来の部門として考えた上で、数字の変化を見ていけばいい。問題はデータ処理である。会社情報には1ページ2銘柄のデータが掲載されていたが、一部のものが1ページ1銘柄となってしまった(「[7]データスリップの作り方(5)」参照)。
手作業で切り貼りしていたのだから、途方に暮れてしまう。
「大きな紙を使えばいい」
「いままでB41枚で1年半だが、1枚で3四半期(3/4年)にして枚数を増やすだけだ」
いろいろな意見が出たのだが、とりあえずの対応をしても先々かならず新しい問題が出てくることは必至である。
- データ量・決算の頻度の増加
- さらなる会社情報の書式の変化
今まででも年4回の会社情報を切り貼りし、さらに毎日の決算発表を切り貼りするのは重労働であった。決算発表が四半期になってデータ量が増えたら対応しきれなくなる可能性がある。また、FAIの対象とする東証1部上場銘柄数も増えている。
会社情報を発行している日経、会社四季報を発行している東洋経済でも、落ち着かない状況ではないだろうか。書式の変更だって「とりあえず」であろう。それに「とりあえず」で対応していたら、混乱が予想される。そこで、電子データの活用に踏み切り、切り貼り作業からの脱却を図ることにしたのである。
[20]新しい時代の分析 (3)連結決算とデータスリップ その2 電子データの活用と注意点
電子データを利用した場合、多くの利点がある。
- データを一元管理し、人数に関係なく作成の労力を限定できる
- 既存のデータベースを利用すれば加工が容易である
- データ量の増加に対応しやすい
月足の作成、日々場帳をつける場合は、すべて手作業でやることになっている。
※場帳(ばちょう)とは、毎日の終値と出来高を記す売買の道具。次章で詳しく述べる。
手作業で行うことで、自然な思考・判断ができるからである。したがって、データスリップ作成にしても、すべて手作業でできればそれにこしたことはない。が、あまりにも手数が必要なことと、前述のように状況の変化に対してよわすぎる点がある。そこでデータスリップのWeb版を、メンバーの協力をもらって完成させた。データベースにインターネットでアクセスし、画面に最新のデータを表示させるものである。 見本はここをクリック
データの推移がひとめでわかり、たいへん便利である。だが、ここであらためて問題が発生する。パソコンに慣れていても、画面で見るのは疲れるし、じっくりと見ることに向いていない。また、インターネット環境がなければ見ることすらできないことになる。
この原稿を書いている2000年4月現在、FAIクラブメンバーにインターネット環境の整備を呼びかけ、同時に低位株に限定したWeb版データスリップの印刷版(とりあえず年4回発行、初回2000年4月号は「3月終値で440円以下、698銘柄を採用、林投資研究所にて販売)を作成した。
今後、公表データの変化に注意しながら議論を進め、改良していくつもりである。
FAIクラブのWeb版データ・スリップ
この連載は「FAI株式投資法」(相場ライブラリーNo.018)より要点をまとめて補足説明を加えたものです