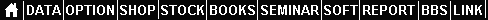
|
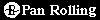
|
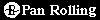 |
2017年7月発売/四六判 上製本
ISBN978-4-7759-7221-2 C2033
定価 本体2,800円+税
著 者 ブラッドレー・C・バーケンフェルド
監修者 長尾慎太郎
訳 者 藤原玄
トレーダーズショップから送料無料でお届け
バーケンフェルドが提供した前代未聞の情報によって、150億ドル以上の資金が取り戻されたが、彼がたった一人で史上最大の脱税スキームを暴き、そのホイッスルブローイング(内部告発)によって、スイス銀行の秘密保持の伝統を打ち倒したにもかかわらず、アメリカの司法省は彼に罪をかぶせ、口を閉ざそうとしたのだ。司法省は彼を共謀罪で検挙し、30カ月も投獄した。
しかし、バーケンフェルドは最終的に勝利する。出所後、彼の正しさは証明された! 米内国歳入庁は、驚くべき暴露を行った彼に対して、史上最大の1億400万ドルに上る報奨を与えたのだ。
たった一人で、スイス銀行業界のあくどさ、大金持ちのあくなき脱税への執念、大銀行に籠絡されている米大統領や国務長官たちの実態を白日の下にさらした彼の真実の物語は、一度読み始めるとページをめくる手が止まることはないだろう!
|
ブラッドレー・C・バーケンフェルド(Bradley C. Birkenfeld) 史上最も重要なホイッスルブロアー(内部告発者)として知られる元金融マンである。現在は不正を暴き、根絶しようと活動するホイッスルブロアーの支援を行っている。バーケンフェルドの歴史的な行動の結果、顧客の脱税や不正、またはテロリストの活動を支える金融機関のリスクとコストは大幅に増大した。バーケンフェルドは、バーモント州ノリッジ大学で経済学の学士を、スイスのアメリカン・グラジュエイト・スクール・オブ・ビジネスで国際MBA(経営学修士)を修得している。NHL(北米アイスホッケーリーグ)のボストン・ブルーインズの根っからのファンでもあるバーケンフェルドはチームや慈善団体と協力して、恵まれない子供たちの支援を行っている。 |
第1部
第1章 成功への道
第2章 ボストン虐殺事件
第3章 暗号を解読する
第4章 スポーツカー、モデル、ヨット、こりゃすごい
第2部
第5章 ベルン炎上
第6章 カウンターパンチ
第7章 タランチュラ
第8章 メキシコで仕組まれたワナ
第9章 タイトロープ
第10章 追われる身
第11章 トワイライトゾーン
第12章 対決のとき
第13章 スケープゴート
第14章 キャンプカップケーキ
第15章 金持ちと貧乏人
謝辞
付録
UBSの一〇大スキャンダル
資料1 スイス銀行の秘密保持
資料2 3ページのメモ
資料3 UBSの研修資料
資料4 マーティン・リヒティによる非追訴合意
資料5 レビンの手紙
資料6 グラスレーの手紙
資料7 バーケンフェルド弁護団の手紙
読み方案内
著者とのQ&A
著者について
ところで、本書の内容はスイスの大手銀行を一個人が追い詰めたノンフィクションとして気楽に読むこともできるが、「アメリカ外交公電ウィキリークス流出事件」「パナマ文書」「エドワード・スノーデンによる暴露事件」といった、ここ一〇年ほどの一連の告発事件の流れのなかでとらえることもできるだろう。こうした現象は前世紀にはあり得なかったことで、なぜならば、以前なら社会階級間に交流がほとんどなかったからである。ピエール・ブルデューが指摘したように、どの文化においてもそれぞれの階級は固有のハビトゥスを有し、それを通じた選別が厳然と行われてきた。学歴や軍歴という例外的なワイルドカードを除けば、階級が異なれば住む世界が異なるという閉鎖性が、社会構造の再生産を維持してきたのである。しかし、近年のグローバル資本主義とネットによる情報の民主化は階層間の大規模な越境をもたらし、階級別の住み分け(ディスタンクシオン)と権益をも徐々に破壊することになった。今世紀に入って世界のあちこちで発生した告発事件の連鎖は、こうした社会的な変化と独立ではない。これは既存のエスタブリッシュメントにとっては大きな脅威である。その意味では、バーケンフェルドの当初の告発に対し米国司法省がそれを抑えにかかり、闇に葬ろうとしたのは、体制側の忠実なエージェントである彼らにとってはごく自然なことだったのだ。
翻訳にあたっては以下の方々に心から感謝の意を表したい。まず藤原玄氏には臨場感があり読みやすい翻訳を、そして阿部達郎氏は丁寧な編集・校正を行っていただいた。また本書が発行される機会を得たのはパンローリング社社長の後藤康徳氏のおかげである。
2017年6月
二〇一〇年一月八日 ペンシルベニア州マイナースビル
連邦刑務所へと続くすべての道のりは長いものであった。
この旅路を短縮し、予想される痛みを和らげるための出口も近道も存在しない。それらの道はすべて決断のうえに築かれ、急カーブやロストハイウエーに満ちている。最後の行程は、裁判所から直行するか、刑務所の排気ガス臭いバスで六時間に及ぶ移送をされるかであるが、それは常に狂った人生の報いであり、常に結末は同じである。
凍えるような金曜日、スクールキルにある連邦矯正施設へ続く道は、終わりなき道かのように感じられた。ペンシルベニア州スクラントンのホテルから、郊外にある刑務所までの道のりは、車で一時間ほどの距離にすぎなかったが、私には一年にも感じられたものだった。レクサスの車中でも息は白く、車外では先が見えないほどに雪が舞い、道路は滑りやすく危険な状態になっていた。私は収監される前に、最後のドライブを楽しみたいと思っていたのだが、手錠につながれ、足首には監視装置を付けられていたので、もはや車を運転することはできなかった。私と同じく一九五センチもの背丈のある兄のダグは、荒天のなか車を走らせていた。私は車中で何人かの友人に別れの電話をかけたが、ほとんどの時間は口をつぐみ、二人とも望んでいない約束の場所へと向かっていた。
これがダグにはつらいものとなることは分かっていた。おそらくは私自身よりもつらかったであろう。彼は私がやったこと、つまり史上最大の金融詐欺と脱税を暴露したことを誇りに思っていたし、アメリカ司法省には激しい怒りを覚えてもいた。ダグは、私には足かせではなく、自由勲章がふさわしいとさえ考えていたのだ。私は、何も問題はないのだと彼に伝えようとした。
「おい、リラックスしようぜ。刑務所での三年は、胸を張って過ごすよ」と、ハンドルを握り、冷や汗をかいた兄の指を見つめながら言った。
しかし、ダグは聞く耳を持たなかった。彼は怒り、苦しみ、そして復讐に燃えていた。私にしてもそうだった。そうでないふりをしても何の意味もないのだ。
私が虚勢を張るのをあきらめたころ、車は雪をかぶった松林を抜ける長いカーブに差し掛かっていた。突如、車はコントロールを失い、スリップを始めたが、ダグはまるでF1ドライバーかのように車をドリフトさせ、けっしてスピードを落とそうとはしなかった。ダグはハンドルに覆いかぶさるようにして、フル回転するワイパーが雪を吹き飛ばすフロントガラスを見つめていた。ワイパーの音は、まるで時限爆弾に取り付けられたメトロノームのようにも思われた。少々ドラマチックにすぎるかもしれないが、実際にそうであったのだ。
「気楽に行こうよ、兄貴。僕は急いではいない」と私は彼の肩に手を伸ばした。 ダグはやっとほほ笑みを見せたが、それはあたかも死者のほほ笑みかのようで、われわれはまたふさぎ込んでしまった。
非業の死を遂げんとするとき、これまでの人生が目の前を走馬燈のように流れると聞いたことがある。幸運にも、それを経験することはなかったが、刑務所に収監されようとしているときにも、似たような現象が起こることをじかに体験した。今振り返ってみると、私の場合は不治の病を患ったようなもので、喜びも悲しみも、さらにはすべての成功体験といくつかのバカげた失態もじっくりと振り返るだけの時間があった。私の人生が目の前を駆け巡ることはなかったが、おんぼろの映写機で古い映画がゆっくりと映し出されているかのようであった。
私は後悔もしていないし、残念会も好きではない。しかし、可能であるならやり直したいこともある。例を挙げるなら、スイス銀行の上司たちには誠実さのひとかけらもないことに気づいたときに、彼らを信用して私を助けてくれるなどとけっして考えるべきでなかった。また、アメリカ司法省に駆け込むにあたっても、史上最大の脱税スキームを丁重に告発する私を守ってくれるなどと期待するべきではなかった。四四歳という十分な年を重ねていたにもかかわらず、私はいまだアメリカの司法制度を信用していたのだ。まぁ、長生きはするものだ。
車中の私の心を占めていたのは、失ったものである。つまり、成功するために猛烈に働いた日々であり、両親であり、兄弟であり、友人であり、そして自由であった。一時間後には、まったく対照的な世界に直面することを私は知っていた。今日までの人生をディズニーランドで過ごしたとするならば、これからはロンドン塔で過ごすことになるのだ。
私は座席に背をもたせ、目を閉じてジェットコースターのような日々を思い出していた。ちょうど二年前、私はだれもが夢見るような生活を享受していた。そこでは目に映るもの、香り、そして感動のすべてが、暖かいカリブの波のように繰り返し押し寄せてきた。
私は、スイスはジュネーブのリブ通りを見下ろす豪華な三階建てのアパートのベランダにもたれていた。エスプレッソを満たした陶器からは湯気が上がり、フィナンシャル・タイムズのオレンジ色の紙面は朝のそよ風に揺れていた。通りの向かいに立つ朝市で仕入れた新鮮なイチゴの山が大理石のテーブルの上に輝き、足元にはスイスのトラムがまるでクリスマスの鉄道模型のように行ったり来たりしている。土曜日の朝、私が住むオーヴィヴは静まり返り、キャバレーのシャッターは下ろされ、観光客を乗せた馬車が石畳の道を進むパカパカという音が遠くから聞こえてくる。雪をかぶったスイスアルプスに陽光が輝き、観音開きの窓からはダイアナ・クラールのジャズの調べが流れていた。
魅力的なブラジル人の彼女、タイはまだ部屋のなかにいて、ペルシャ製の枕の山に埋もれている。二人とも昨夜のお酒が残っていた。ネパールのシルクのような彼女の肌の感覚もまだ残っていたが、ポルトガル語訛りの誘うような声に私は思わずニンマリする。
「ブラッディ、ベッドに戻ってよ、ダーリン。私の大好きなあれが欲しいの」
また晴れやかな週末のひとときであった。われわれは真っ赤なフェラーリ550マラネロに乗り込み、ツェルマットまでドライブに出る。サングラスと白い歯を輝かせながら、美しい山道をブンまわすのだ。私が所有するスイスシャレー(山小屋)は絶景の街の頂きにある。車で乗り入れることは禁じられているので、山の麓の小さな村に車を停め、ケーブルカーで、長く険しい谷を越え、頂上まで進む。やっと到着すると、窓からはまるで絵画のようなマッターホルンの絶景が楽しめるのだ。
それほど特別なことではないのかもしれないが、それもローラン・ペリエのマグナムボトルや、新鮮なブルーガのキャビア、ハバナ産のチャーチル葉巻をありがたいと思わないのであれば、の話である。もしフリゴールのスイスチョコレートやオーデマ・ピゲの時計、ブリオーニのスーツに、あなたを喜ばせ、楽しく過ごすことだけに関心のある魅力的な女性が好きなのであれば、うらやましい話であろう。さらには一番良いことに、すべては現金で支払って手に入れたということを想像してみればよい。
つまるところ、すべては金次第、ということではないだろうか。だからこそ、私は国際的な銀行業界に身を投じ、ラ・トゥール・ド・ペの大学で修士号を修得し、ジュネーブで身を粉にして働いたのである。それゆえ、私はだれもがうらやむスイス・ユニオン銀行、つまり世界最大にして最高の銀行、UBSに職を得たのである。そして、同行ではスイスのプライベートバンカーの精鋭部隊で唯一のアメリカ人として、職務を遂行し、世界中をファーストクラスで旅し、五つ星のリゾートホテルに泊まり、世界の最富裕層が問答無用にスイスの秘密口座に富を隠すよう誘惑してきたのだ。金融の知識と、目いっぱいの笑顔、そして肝っ玉を武器に、UBSと顧客たちのために何百万ドルも稼いできた。そして、私もそこから大きな報酬を得てきたのだ。
しかし、もはやすべては終わり、金がすべてではなくなった。私は、イアン・フレミングが描く人物のような人生を送っていた。スリルがすべての人生であり、またそれを求め続けるものでもあった。私は、この迷惑極まる性質を善意と呼んでいたことに気づき、やがて「会社」にはそんな善意などまるでないことを発見しなければ、今でもまだその生活を続けていたかもしれない。UBSの腹黒い申し子たち、私の極悪な上司たちは、われわれが取り組んでいたことすべてがアメリカの税法に対する目に余る反逆であり、私のあごひげが真っ白になるまで刑務所に入ることになることを最初からお見通しであったのだ。彼らは、私と私の顧客、仲間たちを陥れようとしたのだ。だからこそ、私は、スイスのマフィアたちを追い詰め、先に飛び降りたのだ。
問題は、私が飛び込んだ先が間違いだったことだ。アメリカ司法省は私を歓迎し、保護し、さらにはスイスの秘密と不正とを覆う頑迷な殻を砕き、アメリカの納税者が今後だまされることがないようにした最初にして唯一のスイス・プライベートバンカーである私に感謝するはずであった。しかし、司法省は粘着質の一方の手で私が待つ宝の山に手を伸ばし、もう一方の手で私に手錠をかけたのだ。
卑劣な連中だ。それが洗練されたやり方だというのだろうか。
目を開けると、また怒りがふつふつと込み上げてきたが、車外の風景にふと、われに返る。お前はただ汚名を背負わされたサムライではないのだ、バーケンフェルドよ。私は、アメリカ中部の炭鉱町を眺めていた。馬や家畜が行きかい、ひび割れた煙突からは煙が立ちのぼり、錆びついた古い車はコンクリートブロックに乗り上げている。馬が目に入った。ガソリンが高すぎた時代の唯一の交通手段である。雪に覆われた丘に立ち、青草を探している。かつてこの地は、自国民が求める黒い石を目指してアメリカの英雄たる男たちが地中深くで働いた場所である。鉱山の落盤で多くの者たちが命を失い、またそれ以上に多くの者たちが肺を病んで死んでいったのだ。しかし、今や彼らは、環境保護主義者からは呪われ、選挙のことしか頭にない政治家どもからは遠ざけられた、社会ののけ者となっている。自国に裏切られたのだ。まるで私のように。異なることと言えば、彼らはツェルマットのスキーシャレーなど知りもしなかったことであろう。
われわれは、「マイナースビル」の標識を通過した。もうじきゲームが始まるのだ。私は、秘密を漏らした報いとしてアメリカ政府の慰み者となるのだ。アンクル・サムよ、ありがとう。
私が本当に驚いたのは連邦政府のマフィア連中であり、スイスでの派手な生活などさしたることはなかった。私は質素に育ったし、厳しい環境でも素晴らしい人生を送ることはできた。さらに言えば、全米最古かつ最も厳しい私立の軍学校であるバーモント州のノリッジ大学でもなんとかやってきたのだ。大学では、毎日雪のなかでの腕立て伏せに始まり、ラップサックを背負って一六キロに及ぶ行進を行い、情け容赦ない鬼軍曹に大声で命令され、何時間もおかしくなるくらい講義を受け、そして狂ったように深夜まで勉強するのだ。それに比べれば、スクールキルで起こることなど大したことはなかろう。連邦政府の職員が受刑者を訓練兵のように扱うことは許されないのだ。だが、それゆえに再犯率が下がるのだから皮肉とも言えよう。
いずれにせよ、彼らがどんな無理難題を持ちかけようとも、私は彼ら自身の土俵で彼らを打ち負かすのだとすでに心に決めていたのだ。私は、第二次大戦をテーマにしたコメディで、連合軍の捕虜たちがナチの刑務所長を手玉に取る古いテレビ番組のOK捕虜収容所の熱烈なファンであった。それゆえ、スクールキルは私にとっては「第一三捕虜収容所」であり、私はホーガン大佐となるのだ。さぁ、かかってこい。
私は兄のダグのほうに目をやった。彼はハンサムで、私やわれわれの兄よりも見てくれが良く、とび色の髪も豊富で、歯も白い。ダグはタフな弁護士でもあり、怒ると大きな下あごをつきだし、冷たい青い瞳で標的を射抜くのだ。今、彼のあごは小刻みに震えている。
「怒っているな」と私が語り掛ける。
「いいや、かわいい弟を刑務所に送り届けるのも悪くないね。デーブも何かで訴えられたら、送り届けてやるよ」
彼の返事に私は大笑いした。笑うことができなくなったら、人生は終わりだろう。
「気楽に行こうよ。すぐに終わるさ、分かるだろう」と私。
「だれかを殺してやりたいよ、ケビン・ダウニングのような奴をね」と彼は怒りをあらわにする。
ダグの怒りには心底同意する。ケビン・ダウニングというのは、司法省税務課の上席検事で、私が最初に事案を持ち込んだ相手のひとりである。私は彼に王国の鍵、不法なスイス銀行界の秘密のすべてを手渡し、そして彼は狂犬のように私に襲い掛かったのだ。倫理観にあふれる弁護士であるダグはケビン・ダウニングを職業人として最低の種族とみなしていた。しみったれで、偽善者で、利己的で、本質的に悪人なのだ。
「ほかにだれか候補はいるかい」と私が尋ねる。
「ダウニングの次にかい? そうだな、オレニコフだな」
そう、イゴール・オレニコフ。彼の名前を聞くだけではらわたが煮えくり返る。ロシア生まれのオレニコフは、カリフォルニアの不動産業界の大物で、億万長者。UBS時代の私の最大の顧客である。彼に初めて会ったのはマリーナであった。そこに係留されているヨットは、どれもがマンションを買えるほど高価で、クルーたちはみみん、アバークロンビー・アンド・フィッチのモデルみたいな男の子たち、ヨットのオーナーたちの愛人連中は、本妻の目の前で、シリコン整形の巨乳とダイヤモンドのブレスレットを見せびらかしているのだ。その後、再びオレニコフに会い、彼をリヒテンシュタインに住む私の同僚で、金儲けと姿を隠す天才であるマリオ・スタグルに紹介した。
オレニコフは大金持ちで、万一に備え、その大部分を詮索好きなIRS(米内国歳入庁)の目から逃れさせたいと考えていた。そこで、スタグルは、オランダのペーパー・カンパニー三社を出資者としたリヒテンシュタイン信託を二つ創設した。最終的な受益者はオレニコフである。その後すぐに、私は、彼がアメリカの不動産から上げた二億ドルの利益をUBSのいくつかのナンバーアカウントに移した。本当の口座保有者がオレニコフであることを示す唯一の証拠は、彼の名前が入った索引カードと彼のコードネームである。そのカードは、ジュネーブのUBS本部に厳重に保管され、それを見ることができるのは、私と私の上司であったクリスチャン・ボヴァイだけである。UBSのほかの社員はだれもオレニコフのことは知らないのだ。
技術的には、この取引に違法な点はない。ただ、オレニコフが税務申告のときにスイスに資金を置いていることを「忘れずに」申告するかぎりは、である。私は、数多くのアメリカ人をUBSの顧客としたが、彼らがW−9に記載しようとしまいと、私には関係のないことだった。しかし、誤解しないでいただきたい。私はガキでないし、自分がしていることは理解していた。さらに、UBSは大金を持った金持ちたちを連れてくるべく、われわれ「狩人たち」を追い立て続けた。そこで私は、善意にはしばらくお休みいただいて、ゲームを続けたのである。私は、上司たちが私を辞めさせようとしていることを知って初めて、先制攻撃に出ることを決め、彼らを密告したのだ。
そして、アメリカ司法省はあらがいがたい取引を持ちかける。「バーケンフェルドさん、アメリカ人の口座保有者の名前を教えてください。すべての名前です。さもなければ、あなたのことも起訴しますよ」。私には選択肢などほとんどなかった。密告しようとすれば、だれも守ることはできないのだ。
さて、イゴール・オレニコフは、まったくもってしみったれの、高慢な億万長者の典型であった。彼はお金で最高の弁護士を雇い、罰金を逃れようとしていることを知っていたので、彼のことを密告するに罪悪感はなかった。さらにオレニコフは私にこうも言っていた。来世はニューポートビーチの主婦になりたい、と。彼のとっぴな発言に、私はその真意を尋ねた。彼の答えは、「だって、連中がやっているのは旦那のお金を使うだけだろう」。何と立派な男であろうか。
彼についての私の判断は正しかったが、阿呆省については間違いであった。彼らのDNAには感謝の念など存在しなかったのだ。彼らはオレニコフを脱税で告訴するとともに、私もその共謀者として訴えたのだ。さらには、私を確実に投獄するために、私がオレニコフの名前を上げたのは起訴されたあとである、と彼らは主張したのである。
まったく信じられないことだった。私が司法省に名前を教えなかったとしたら、彼らはどうやって知ったというのだ。しかも、私はすでにアメリカ上院議会に召喚され、宣誓のうえで証言しており、オレニコフとの取引の全容を詳述してもいた。にもかかわらず、ケビン・ダウニングは量刑審理の場でも裁判官の目を見つめ、私がその名前を隠したと宣言したのだ。悪魔のように無表情で、誠実ぶったダウニングは、私は金持ちの顧客たちをかばい、ほとぼりが冷めたら、また一儲けするつもりだと主張したのである。
判事の小づちが振り下ろされた。バーケンフェルドを実刑に処する。
私はあのときの感情と、マホガニーの机をたたく小づちの音を忘れることができない。私にとっては、リー・ハーベイ・オズワルドの一瞬である。だれかが殺されたというだけだ。だからどうした、というのだ。お前はだまされやすい男なのだ。
一方、オレニコフは悪魔との取引に応じ、二年間の執行猶予と追徴課税の支払いで免れた。追徴金の額は五二〇〇万ドル。大金のように思えるが、オレニコフにとってはポケットマネーにすぎない。しかし、その後に毒入りの花が添えられた。オレニコフはUBSと私と三〇人以上の個人や企業を訴え、彼らは自分の税金の支払いを邪魔したと主張したのだ。バカげた話である。あなたは何十年にもわたり政府をだましつづけ、だれかがあなたを密告したら、その男を付け狙ったのだ。その者が刑務所に向かう一方で、あなたは乱痴気騒ぎに舞い戻るのだ。そのころには、私は弁護士費用が払えなくなっていた。弁護団を失った私はやがて収監され、為す術もなく、一方でオレニコフはパーティーを開いて、裁判所で私を中傷したのだ。
なんて国だろうか。自由の地である。ただし、自由を買うお金があれば、の話であるが。
さて、この話の落ちまでお付き合いいただきたい。オレニコフにはアンドレイという最愛の息子がいた。私は、父親よりも彼のほうが好きであった。彼はお洒落な若者で、見てくれも良く、勤勉であった。カリフォルニア州ニューポートビーチで開かれた彼の結婚式には私も出席した。麗しき花嫁の名はキムである。ある日、アンドレイはジープに乗って国道一号線を海岸に沿って走っていたが、何らかの理由でブレーキが利かず、彼は死んでしまったのだ。私はショックを受け、心から悲嘆に暮れたものである。キムは精神的に打ちのめされ、イゴール・オレニコフは終生消えぬ心の傷を負った。
この物語の教訓は、あなたがどれだけのお金を持っていようと、どれほど賢いと思っていようと、死者を取り戻すことはできないということであろう。古い格言ではないが、確実なものは死と税金だけである。皮肉にも、オレニコフはそのどちらをも経験したことになる。
再びダグに目を向けると、口元に笑いを浮かべていた。彼もオレニコフの運命について考えていたのであろう。
それこそがバーケンフェルド兄弟の長所である。われわれはタフで、厳しい競争にも耐え得る、根っからのファイターなのだ。われわれの父親は有名な神経外科医で、三人の兄弟はホッケーやフットボールをしながら育ち、幼いころから雑用を買って出ていた。われわれは穏やかな環境で育ったが、けっして甘やかされることはなかった。われわれの苗字は、ドイツ語で「樺の地」という意味である。それこそわれわれに相応しく、背が高く、屈強で、時に風にたわむことがあっても、けっして折れることはない。もしわれわれを切り倒したいのであれば、少なくともバターナイフよりも大きなものを持ってきたほうがよいであろう。
激しい吹雪のなか、カーブを曲がり、長く細い道を進むと、ついに見えてきた。スクールキル(「スクール[School]」「キル[kill]」と発音するわけだが、そこでは何も学ぶものはないと言っているかのようだ)である。それは辺ぴな所で、森に囲まれ、フットボール場一〇個分もある敷地に建っていた。正面玄関は、コンクリート造りの低い長方形で、黒い曇りガラスの窓がはめられ、天井には有刺鉄線が張り巡らされていた。星条旗が風に揺れ、滑車がカタカタとなっていた。胃が締めつけられるように感じた。報いを受ける時が来たのである。
敷地の外では、報道番組の中継車が並び、歩道にはジャーナリストたちの車が列をなしている。世界中のカメラクルーやリポーターは、ダウンジャケットに身を包み、辺りをうろついたり、寒さに腕をさすったりしている。われわれの車を見つけると、彼らはコーヒーカップを投げ捨て、照明やマイクにスイッチを入れた。彼らがそこで待ち構えていたのは、私がこっそりと教えておいたからである。私は記者会見を開き、アメリカ政府に対して、私を投獄するというでたらめについて話をしようと決めていたのだ。
私というものがまだ分からないなら、言っておこう。私は出る杭を求めるハンマーなのだ。
最後尾に車を停めると、「さぁ、行くぞ」とダグは言った。私は車を降りて、空を見上げた。ぼた雪が落ちてきていた。これから三年間離れることになる自由な世界の見納めである。私はフランネルのランバーシャツに赤いスキージャケット、黒い野球帽と、至って普通の格好をしていた。すぐに見慣れた顔を見つける。
最後まで私の味方でいてくれた唯一の弁護士であるスティーブン・コーンである。彼は無償で働いてくれたのだ。白髪を短く刈り込み、メガネをかけ、明るい笑顔を絶やさない小柄な男である彼はとても賢く、またピットブルのように短気でもあった。彼は、ワシントンDCにあるナショナル・ホイッスルブロアー・センターの主席顧問でもある。コーンは、政府は私に大きな報酬を与えるべきであると固く信じており、それを獲得すべく絶対にやり遂げようとしていた。私は彼を愛していたが、一方で彼は夢想家だとも考えていた。私は彼にうなずきかけ、最後の歩についた。ダグは歩くショットガンとして私に寄り添った。リポーターたちが集まってきたが、黒い防寒着を着て、拳銃と警棒を下げた二人の刑務官が正面玄関から飛び出してくるのが見えた。そのうちの一人が慌てふためいて手袋をした手を振る。
「ここで記者会見をするんじゃない。ここは私有地だ」と彼は叫んだ。
私は道路を指さして、彼にニューイングランド訛りでお見舞いしてやった。「この道路はアメリカ国民のものであって、貴様のものではない。ここは連邦の所有地だ。貴様は、私に与えられた表現の自由を否定しようと言うのか」
刑務官たちは何かぼそぼそと話し合い、罵りながら引き下がっていった。一人の背の低い女性リポーターが私を見上げ、マイクを向けてきた。
彼女はカメラにポーズを取りながら、「バーケンフェルドさん、あなたは脱税を共謀したかどで連邦の権力に屈することになりますが、何かおっしゃりたいことはありますか」と言った。
私は彼女に向かって目いっぱいクリント・イーストウッドを気取る。
「私は、勇気をもって自ら名乗り出て、世界最大の脱税を暴いたことを誇りに思っています」。リポーターたちはレコーダーを操作し、メモを書きつける。「そして、私が得たものはこれです」と刑務所をあごで指した。「司法省によって起訴されました」。そして全員にこれ以上ない冷たい視線を向けて、「ご自身の結論を下してください」。
大勢のリポーターからの質問が殺到したが、私はすでに政府に一矢報いたのだ。スティーブ・コーンは私を押しのけ、感情をむき出しにした。
「アメリカの納税者のために最大の金額を取り戻したホイッスルブロアー(内部告発者)を捕まえて、刑務所に入れるだって。司法の茶番だ。司法の失敗だ。グロテスクだよ」
そして私はコーンの肩に手を置き、兄と握手すると、群衆を押しのけ、コンクリート板を敷いた道を玄関に向かって歩いた。二人の刑務官が私の手を後ろに回し、手錠をかける。ガチャン。
彼らは私を建物のなかに連れていくと、ドアを閉めた。外にいるリポーターたちの喧噪は静まり、靴に当たる雪以外に音をなすものはなかった。二重あごの刑務所長の肖像が飾られた白壁の受付を通過する。リノリウムを塗った床は高校の体育館のようなにおいがする。何となく嫌いではない。その先に、恰幅の良い金髪の女性がハイデスクに座り、オズの魔法使いのように周りに目を配っていた。彼女はすでに私のことを知っていたが、私は一応気をつけの姿勢を取った。
「ブラッドレー・C・バーケンフェルド、です」と名乗る。
彼女は私の嫌味にも反応しない。「えっと、バーケンフェルドさん。何か所持品はありますか」
私はオーデマ・ピゲのロイヤル・オーク・オフショア・T3モデルを外す。ターミネーター3でアーノルド・シュワルツェネッガーが着けていたモデルだ。
「これだけです。失くさないでくださいね。二万五〇〇〇ドルもするのですから」と言って彼女に手渡す。
彼女は私を無視し、威嚇するコブラでもあるかのように時計をつまみ上げると、茶封筒に放り込んだ。
刑務官たちは私を「処理室」に連れていく。汚れた靴下のようなにおいのするスチールのロッカーがある空き室だ。私を壁の前に立たせると、刑務所内での写真を取る。カメラのフラッシュに私はほほ笑んだ。
「なんで笑ってやがるんだ」と一人の刑務官が見下した態度で言う。
「だって、遊びに来たんですから」と私。
二人は憤然として互いを見つめる。もう一人が私の足を指さして、「監視装置はどこだ」。
「昨夜ナイフで切り取って、保護監察官に返しました」
その後、彼らは手錠を外し、ワナにはまった子猫でも見るかのように私を見つめる。私は服を脱ぎ、彼らに渡した。
数分後、私はピタッとした白い肌着とグレーのTシャツ、オレンジ色の囚人服を着て、編み上げの作業靴をはく。予想どおりの服装だ。事前に調べてあったのである。私は軽警備の建物に収監されるであろうとも思っていた。そこは、ホワイトカラーの犯罪者を収監しておく、兵舎のような建物だ。
白衣を来た医者が入ってきて、私の血圧を測ると、イライラしながら数値を口にする。刑務官は私に再び手錠をかけ、私をミス・ハッピー・フェイスのもとへ連れていく。彼女は何かの書類に判を押していた。
「私の宿舎はどこでしょうか、昼食をふいにしたくないのですが」と私は尋ねる。
彼女は眼鏡越しに私をにらみつけた。「今日はそこには行きません、バーケンフェルドさん」
「では、どこに行くのですか」
彼女は天井を指さして、「独房です。上からの指示です」。
なるほど。おそらく所長は、私が正門の前で刑務所を見世物にしたのが気に入らないのだろう。それで私を独房にぶち込むことにしたのだ。しかし、ここでいつまでかと聞けば、恐れをなしたように思われるので、彼女にバーケンフェルドのほほ笑みを返す。
「それは好都合だ、私は一人の時間が好きなのですよ」
刑務官の一人が私の肘をつかんで、オートロックのドアを通らせる。もう一人の刑務官がミス・ハッピー・フェイスにつぶやく声が聞こえた。「あんなこと言う奴は初めてですよ」
長く、静かな廊下を進むと、その先に小さな防弾窓と巨大な鍵の付いた重たいドアがあった。刑務官はそれを引き開けると、手錠を外す。私をなかに押し込むとドアを激しく閉めた。窓を振り返ると彼が鍵をかけていたので、私はウインクして言ってやった。
「良い週末を」
彼は一瞬たじろいだが、すぐに去っていった。
私はずっと昔、社会人となって銀行業に従事するずっと以前に重要なことを学んでいた。私はそれを、マサチューセッツ州の高校でホッケーをしているときに氷上で学んだのだ。相手には自分が如何なる者かすぐに分からせなければならない。優しそうに見えても、かなり気まぐれであることを。彼らを見下ろし、冷たいほほ笑みを与えるのだ。そうすれば、彼らにバカにされるようなことはないだろう。 連中が私を投獄したのは確かだ。自らが法律のように振る舞い、人々を守り、正しいことをしているかのようなふりをする。そして、和解をあきらめ、人生は言うまでもなく、すべてのキャリアをリスクにさらすほどの秘密を明かすよう誘いこんだ。やがて彼らは私を裏切り、私をクズと罵り、金持ちどもとは不正な取引をして、本当の獲物を逃がしてやったのだ。そして、私を独房にぶち込み、鍵を放ったのである。
しかし、忘れてはならないことがひとつある。私はやがて釈放されるのだ。
そして、お前たちは報いを受けることになる。
 武器化する嘘 |
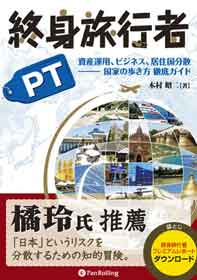 終身旅行者PT |
 金融版 悪魔の辞典 |
 勘違いエリート |
 投資家のヨットはどこにある? |