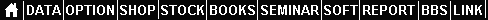
|
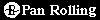
|
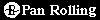 |
ISBN 4-7759-7010-0 C2033
著者 ニコラス・ダーバス
訳者 長尾慎太郎/飯田恒夫
 How I Made $2,000,000 in the Stock Market
著者紹介ニコラス・ダーバス(Nicolas Darvas)ショービジネスの世界で最もギャラの高いペア・ダンサー。幾多の苦労の末、マーケットの上昇や下落に関係なく通用するボックス理論を構築し、株式市場で200万ドル以上の利益を上げ、資産家になる。
訳者紹介長尾慎太郎(ながお・しんたろう)東京大学工学部原子力工学科卒。米系銀行でのオルタナティ ブ投資業務、および金スワップ取引、CTA(商品投資顧問)での資金運用を経て、現在は株式ファンドマネージャーとしてオルタナティブ運用をおこなう。マーケットに関連した時系列データを基にしたシステム・トレードを専門とする。
飯田恒夫(いいだ・つねお) |
 全米トップトレーダー トニ・ターナー女史もオススメ!
全米トップトレーダー トニ・ターナー女史もオススメ!
本書の著者であるニコラス・ダーバスがウォール街について下した結論は、そこは巨大なカジノ以外の何ものでもないということだった。これがディーラーや証券会社、情報屋たちを怒らせた。そして、その事実は、非常に好評を得た彼の2冊目の著書『ウォール街(Wall Street : The Other Las Vegas)』のなかにも書かれている。
本書は、驚くべき書物である。これは株式市場の歴史における最も異例な成功物語のひとつである。
ダーバスは、内部情報をもとに売買を行う株式市場の専門家ではない。彼はショービジネスの世界で最もギャラの高いペア・ダンサーのひとりなのだ。しかし、彼は独自の投資手法を悪戦苦闘の末に開発し、百万長者の数倍の資産家になることができた。彼の手法がシステムと称するほかの方法と異なる点は、マーケットの上昇、下落に関係なく通用することだった。
ダーバスが風変わりな投資法で素晴らしい利益を上げているというニュースがもれて、『タイム』が彼の特集記事を組んだ。その後に説得されて本書を執筆したが、これはたちまちのうちにベストセラーになり、8週間で20万部近くも売れた。
本書に記載された会社のなかには存在しなくなったものも多い。また、取引されなくなった銘柄も少なくない。それでも、本書に書かれた基本原則の信頼性にはいささかの揺るぎはない!
本書は、アメリカにおける株式市場関連の古典的著作である。株式市場の古典と呼ばれる書籍の多くは50〜75年前に書かれたものだが、本書は4半世紀後の今日でもほとんどの記述がそのまま通用する。
ダーバスは独創的な人物だった。彼はクロスワードパズルを作ったり、卓球ではチャンピオン級のプレーヤーであったり、社交ダンス界にあっては世界最高のプロダンサーであったりと、あらゆることに秀でていた。
彼は他人と異なる人間であることを恐れなかった。その鋭敏な頭脳は休むことを知らなかった。ニューヨークのプラザホテルのバーでわたしに質問をしておいて、2週間後にパリのホテル・ジョルジュ・サンクで会って一杯飲んだときにその答えを教えてくれるような人だった。その4週間後にモンテカルロのオテル・ド・パリで会うと、以前の答えをさらに掘り下げて解説し、またその半年後にはリオデジャネイロのレメパレス・ホテル前に広がるコパカバーナの砂浜で日光浴をしながら同じ話題に触れたりした。
チェコスロバキア(当時)のプラハで、いかにもこの街にふさわしい「一流」にしてはみすぼらしいホテルの一室で、作詞家のディック・マニング夫妻と一緒にわたしと妻がくつろいでいたときに、電話が鳴ったことを思い出す。わたしの秘書も含めてだれもわれわれの居場所を知らないはずだった。しかし、ダーバスは探し当てたのだ。
何か緊急の用件か? だが、実際はダーバスが近々出版する予定の彼の著書『ウォールストリート――ジ・アザー・ラスベガス(Wall Street : The Other Las Vegas)』の表紙の色について、自分の考えをわたしに聞いてもらいたかっただけだった。
根強い要望に応えて本書を復刊することができたことをわたしはうれしく思っている。本書は率直にまた衝撃的に株式市場を紹介しているので、ウォール街という巨大なカジノで「勝負」しようとする人にとっては間違いなく必読の書である。
ここで、読者の皆さんにちょっとした面白い情報をお教えしよう。本書が成功裏に出版されたあと、バロンズ誌の発行部数は倍増した。バロンズは大いにダーバスから恩恵を被ったのだ。しかし、バロンズは謝意を表すのに実に奇怪な方法をとった! その他多くの金融関連誌や新聞とともに、バロンズも『ウォールストリート――ジ・アザー・ラスベガス』の広告掲載を即座に断ったのである。その理由は、彼らにとって長年の忠実な広告主であるブローカーや相場の予想屋の正体を暴露したから、というものだった。この書籍の有料広告を受け付けないばかりか、ニュース欄や書評欄ですら、この本に触れることを一切拒否したのだ!
「わたしはパンをくれる人の歌を歌う」ということわざを知ったのは、わたしがまだ駆け出しの新聞記者だったころだ。
記事の差し止めはほとんどのメディアに及んだ。ニューズウィーク誌は予定していた書評を取り消した。タイム誌は記事に添える写真まで要求してきたのに、その記事はあいまいな表現でこの本のテーマに話が及ぶのを巧みに避けていた。
『ウォールストリート――ジ・アザー・ラスベガス』は、ウォール街のうわべだけのいかがわしい幻影の多くを打ち砕いた。この著作を読んだ人はだれしも、株券やブローカー、または金融関連ニュースレターについて以前と異なる見方をするようになっただろう。もし本書の復刻が成功すれば、この書籍も刊行するつもりである。
読者が手にされた本書は、個人ブローカーや証券会社に対する投資家の認識を劇的に変化させた最初の書物であった。
お読みになればその理由が分かるだろう。内容をしっかりと身につければ、あなたの将来の株式投資活動は実り多いものになるだろう。
1986年3月 ニュージャージー州フォートリー
ライル・スチュアート
わたしはケネディ国際空港の電話ボックスの中にいた。その1メートルほど離れたところには、チャーリー・スタインが美しい女性を連れていた。チャーリーはロードハードウィック・コーポレーションの社長で、彼のそばにはいつもきれいな女性がいた。彼は女性にわたしを紹介するのが、そしてわたしを知っていることで、「自分」がどれほど偉い人物かをその女性に悟らせる口ぶりでわたしのことを褒めそやすのが、特にうれしいようだった。
この機先を制する彼のやり方に応じてやっても、いつもは何の見返りもなかったが、この日だけは特別だった。だれにも見えなかったのだが、もうひとり別の美しい女性がいたからだ。彼女は人の目には映ることがなかったが、わたしのすぐそばにいた。彼女の名前は幸福の天使、または幸運の女神という。
このときは、わたしを利用したつもりのチャーリーが、初めてわたしの役に立ったのである。というのは、これが本書の復刻版出版を早めるきっかけになったからだ。
わたしは電話でパリのガールフレンドをつかまえようとしていたのだが、どうやら浮気の相手と外出中のようだったのであきらめようとしたとき、チャーリーがいつもの調子でニコラス・ダーバスを自己アピールに利用しようと歩み寄ってきた。彼は持ち前の大声でわたしの名を連呼した。すると隣の電話ボックスにいた見知らぬ男性が飛び出してきて、彼に尋ねた。「この人は本物のダーバスですか? わたしは彼の本を化学の教科書かなんかのように研究したんですよ。それで、信じてもらえるかどうか分かりませんが、ダーバス氏が書いたとおりにやって10万ドル以上儲けたんです!」
わたしがボックスから足を踏み出すと、その男性はわたしのほうに振り向いた。
「いったいどうしてあの本は絶版になってしまったのですか?」
彼はわたしの答えを待たずに言った。「わたしは10冊以上買ったんですよ。しかし、今ではどんな大金を積んでも1冊だって買えやしない。手元に残った1冊だって次から次へと借りていくやつがいるんです。それでそいつから拝み倒して返してもらわなければならないんです。しぶしぶ返してくれましたがね。でも、もうその本はぼろぼろですよ」
その見知らぬ男性は手を差し出した。「あなたにお礼が言いたかったんです。間もなく出発便の時間がきてしまいます。そうでなければ、夕食にお招きするか、一杯お誘いしたいところです。ひとこと言わせてください。あなたは株では200万ドル儲けたかもしれないけれど、出版業をやっていたら2セントすら儲けられなかったでしょう!」
そう言うと、わたしの手を握り、あわてて向きを変えて搭乗口のほうへ走り去っていった。
わたしは衝撃を受けた。しばらく言葉も出なかった。10年たった今でも、わたしへ送られてくるこの著書についての手紙が途絶えることはない。読者から再三にわたって説明を求められる個所がいくつもある。質問の大半は同じような趣旨のものだ。それなのに本は絶版になっている!
時間がたてば物事はうまく収まるものだ。そして、わたしの株式市場への投資方法も、時とともにその正しさが証明された。わたしの著書も今や古典の部類に入って、「絶版書」マーケットでは1冊20ドルで売買されることもある。
わたしは並外れた幸運に恵まれたのだろうか? 愚か者でも間違えようのない、急上昇を続ける強気相場のモメンタム(勢い)に乗っかっただけなのだろうか? あるいは、わたしの手法はマーケットがどんな状態にあっても通用するほど、その信頼性が高いものなのだろうか?
事実が示しているのは、本書が時間という厳しい審査にも耐え抜いたということである。わたしは空港からパークアベニュー・サウスにあるライル・スチュアートの事務所へと急いだ。わたしの2冊目の著書である『ウォールストリート――ジ・アザー・ラスベガス』の出版元だ。彼はガッツのある男で、ギャンブルにも尻込みはしなかった。しかし、わたしが本書復刻の可能性に触れると、復刻はギャンブルでもなんでもないと彼は断言した。少し意見を交わして、わたしたちは内容を一言も変えることなく、元のままで復刻することを決めた。なんといってもこれは古典なのだ。書き換える必要はない。すでに100万人がこの本を読んだと推測される。そのために影響力は相当大きく、ひとつの取引所、すなわちアメリカン証券取引所がストップロス・オーダー(逆指値注文)の規則を変えざるを得なくなったほどだった。また、この本に非常に立腹した「当局のお偉方」に説き伏せられたニューヨーク州の検事総長が、本書に関する何やらバカげた告発を行った。のちに検事総長はこっそりと告発を撤回する羽目に陥ったが(大々的に行われた告発も、取り下げるときにはその声がほとんど聞き取れなかった!)。
よろしい、最初に出版したときとそっくりそのままにしておこう。しかし、読者から出された無数の質問のなかでいくつかを取り上げて、わたしが答えることにしよう。この質疑応答は本書の末尾に追加してある。
もちろん、わたしが答えたのは最も頻繁に寄せられた質問に限定している。しかし、まったく質問らしいものがない手紙をここで1通だけ紹介しておきたい。それはむしろ詰問状ような内容だった。
その読者は、データが掲載されたページを挙げて、わたしが「宝の山を逃した」と指摘していた。その人は、わたしが専従の助手を2人雇って、2年間わたしのシステムどおりに運用を続けていたら、18カ月で225万ドルどころか、最初の元手(3万6000ドル)の3000倍、つまり1億ドルの収益を上げていたはずだ、と力説していた。
この読者によれば、わたしの落ち度は素早い株価の動きと信用取引をうまく利用していないことだそうだ。また、利益の再投資をしていないことも間違いだという。
もちろん、これはすべて後知恵である。手紙には過ちを立証する詳細なチャートが同封されていた。18カ月で140倍にすることができただろうか? 200倍は? あるいは1000倍は可能だったろうか?
おそらく可能だっただろう。しかし、わたしは自分がやり遂げたことを不満だと思ったことはない。早まって売ってしまうことがないように冷静に判断したこと、またその一方で唯一の武器、すなわちトレイリング・ストップ(価格の上下に合わせて断続的に手仕舞い価格を変更する逆指値注文)を使って、多くの株を売り抜け、難を免れたことで財産を築いたのだ。
わたしには、損失を免れることができるパラダイスは見つけられなかった。しかし、わたしは大した危険にも遭わずに損失を限定することができたし、それもできるかぎり10%以下で済ませることができた。利益と時間は相関関係にあるが、取得後3週間以上利益が乗らないような株式を持ち続けるにはよほどの根拠が必要だろう。ストップロスは2つの効果をもたらした。間違った株からわたしを引き離し、正しい株に導いてくれたのだ。しかもそのスピードは速い。わたしの方法がだれにでも通用するとは限らない。しかし、わたしには効果を十二分に発揮した。本書でわたしの活動を研究し、その結果が読者にとって有益かつ利益をもたらす投資になることを祈っている。
1971年2月 パリにて
ニコラス・ダーバス
第1部 ギャンブラー THE GAMBLER
それは1959年5月のことだった。スミス兄弟からブリランドというカナダ株で出演料を支払うという申し出があってから6年半たっていた。あたかも車輪がちょうど1回転したようだった。というのも、あのときと同じようにわたしはニューヨークの「ラテンクオーター」に再び出演していたからだ。わたしの株式市場での取引ぶりが、どういうわけかウォール街で人のうわさに上るようになった。わたしが成功したという話がもれて、次第に広がった。
ある日、驚いたことにタイムの経済部から電話がかかってきた。株式市場でわたしが成功したことを小耳にはさんだが、インタビューのために記者を送ってよいかという話だった。
翌日、記者がやってきたので、わたしは財産づくりの一部始終を語った。記者に帳簿や取引明細書、電報を見せてやった。彼はその資料を入念に調べたうえで、わたしの話に非常に感心したと言って帰っていった。
その翌日、記者がまた戻ってきて、スタッフの経済専門家が非常に懐疑的で、わたしの話が本当であるわけはないと主張していると言う。
そう聞いても特に驚かなかったので、記者にもう一度事実を示す書類や数字を見せた。彼は5、6時間かけて調べ、帰っていくときにはすべての資料が正確だと納得したようだった。
やがて分かったのだが、これはタイム社内での論戦のほんの幕開けだった。翌朝、その記者が昼食を一緒にしないかと誘いの電話をかけてきた。約束の30分前に再び彼から電話があって、編集主任が同席するという。主任が自分の耳でわたしの話の真偽をチェックしたいそうだ。
2人は1時に昼食の席に現れた。もう一度、わたしは投資の経緯を逐一説明した。主任は熱心に耳を傾けるあまり、テーブルの上の食事に手をつけないままだった。
午後4時を回り、話をすべて聞き終わったあと、やっと彼はサンドイッチをほおばった。5時になると、彼は記者と一緒に帰っていった。何も言わなかったが、明らかに彼も感心したようだった。あれだけ人の話に興味を示す人物に会ったのは初めてだった。
その日の夕方6時に、また電話があった。今度はタイムのウォール街専門記者だった。彼の話では、3人の編集スタッフがわたしにインタビューしたうえで、すべての事実をチェックして、全員がそろって検証したあとでなければ、編集局長がわたしの記事の掲載を認めないと言っているそうだ。非常に驚いたことに、局長はわたしのダンス公演をぜひ見ろと言ったという。
どうやら、局長はわたしの株式市場での成功を疑問視しただけでなく、何とダンスだってろくに踊れないだろうと思っているようだった!
午後7時、3人目の専門記者が尋ねてきた。最初、彼はわたしが話したことすべてが、そして投資活動に関してわたしがそろえたすべての証拠書類が信じられないというように首を振っていた。彼はあらゆることを疑ってかかろうと決めていたようだ。
ジュリアとわたしが舞台で演じると、彼はわたしたちのダンスに感心したようだった。少なくとも、これで関門はひとつ越えた! もうこれで3日間にわたって反対尋問を受けてきたので、いささか神経が参っていた。そのために自分の踊りが絶好調ではないことに気づいており、舞台の最後のほうでパートナーを持ち上げる力仕事の最中に右腕の筋肉をひどく痛めてしまった。だが、何とか舞台を終えることができた。
ウォール街の専門記者と向かい合って投資に関するこまごまとした厳しい質問を受けている間も、腕はひどく痛んだ。質問は延々と――数時間も続いた。彼の質問はいつも同じところに戻ってきた。それは、なぜわたしが株式投資についてこれほど包み隠しせずにしゃべるのかということだった。
自分のやり遂げたことを誇りに思うからだ、とわたしは答えた。何も隠すことはないと思った。
もう真夜中を過ぎていたが、それまで長時間を費やしたにもかかわらず、尋問官は一切の飲み物を断った。彼は、わたしのシステムや記録に何か欠点がないか探し出すために頭を冴えた状態にしておきたいのだ、と正直に認めた。
午前2時、彼はボールペンを投げ出した。
「一杯やりましょう」彼は言った。最後の疑問も氷解し、彼は納得した。記者はグラスを高く上げて、わたしの株式市場での成功に乾杯してくれた。
彼は午前4時に帰っていったが、その前にわたしにアドバイスを求めた。わたしは、株価が39 3/4ドルになったらという条件つきで、ある銘柄の買いを勧めた。そして、ストップロスを38 1/2ドルに置くように忠告した。この銘柄は結局39 3/4ドルまで値上がりしなかった。彼はわたしの付けた条件を無視して、もっと安い価格で買うようなことをしなかっただろうか? そうでないことをわたしは願った。この株は22ドルまで値下がりしたのだ!
翌週、わたしの記事がタイムに掲載された。言うまでもなく、同誌は非常に影響力の大きい読者層を持っており、特に金融界ではそうだった。その結果、わたしは正統派ではないにしても、株式市場で非常に成功した投資家として、大方の――無論すべてではない――金融界の専門家たちに認められた。それでこの本を書くことになったのだ。
もうひとつの結末は、筋肉をひどく痛めたことだった。ある医者は、ダンス公演を完全に断念しなければならないだろうと診断した。その医者は、わたしが二度とパートナーを持ち上げることができるかどうか疑問だと考えたのだ。
2週間後、わたしは舞台に立っていつものとおり公演をした。その後もずっと同じ公演を続けている。ウォール街の専門家と同じく、専門医でも時には間違いを犯すのだということを実証するかのように。