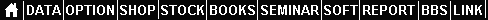
|
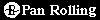
|
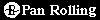 |
2016年9月発売/四六判 494頁
ISBN978-4-7759-7210-6 C2033
定価 本体2,800円+税
著 者 マーク・スピッツナーゲル
監修者 長尾慎太郎
訳 者 藤原玄
トレーダーズショップから送料無料でお届け
本書では、ヘッジファンドのマネジャーであり、テールヘッジの先駆者でもあるスピッツナーゲルが魅力的な旅に読者を誘う。それは、CBOT(シカゴ商品取引所)のピットに始まり、寒帯針葉樹林を経て、古代中国の戦国時代からナポレオン時代の欧州、さらには産業的に急成長するアメリカまで底通する規範的な戦略へ、そして19世紀オーストリアの偉大なる経済思想家たちを通じて、彼の投資戦略となるオーストリア流投資法へと至るものである。目の前の決戦に勝つことで勝利が得られるのではない。むしろ、直接的な結果よりも、間接的な手段を獲得することを目的とした優位性(彼はこれを「勢」と呼ぶ)を狙う「迂回」アプローチこそが勝利をもたらすのだ。重要なのは、時間のとらえ方を変えることだ。一般的な感覚とはまったく異なる異時点的な次元で時間をとらえることになる。
金融危機下でもトップクラスのリターンをたたき出したスピッツナーゲルは、ルートヴィヒ・フォン・ミーゼスやオーストリア学派経済学の理論を、効果的な投資手法へとまとめ上げた最初の人物だと言える。金融のゆがみ、「ブラックスワン」と言われるような株式市場の大混乱はけっしてでたらめに起こることではないということ、そしてまったく市場が無視している極めて生産的な資本を見定めること(スピッツナーゲルにとっては日常茶飯事だが)を本書は説いている。本書はロン・ポールが序文で述べているとおり、「オーストリア学派経済学を象牙の塔から投資の現場に引き出した」のだ。
本書は、市場プロセスとの共生を見いだす当代一流の投資家のレンズを通した世界が広がっている。今こそ、共生が求められるときもないだろう。
第1章 道教の賢人――クリップパラドックス
巨匠
柔よく剛を制す
ピットのなかへ
トレーダーの名誉
債券ピットのロビンソン・クルーソー
マクエリゴットのプールで釣り
オーストリアへ――フォン・カラヤンの一瞬
静止状態
空虚への道筋
前進
賢人の知恵
第2章 松ぼっくりのなかにある森
森と木
スローシードリング
山火事と資源再配分
針葉樹の効果
成長ロジック
第3章 勢――異時的戦略
孫子の道
勢とクロスボウ
力――直接路
囲碁での勢と力
共通テーマ――東から西へ
誤解の衝撃
戦争論――間接戦略
勢、目標、手段、目的
第4章 見えるものと見えざるもの――オーストリア学派の源
予見されるべきもの
東西交差点――ウィーン
ベーアが指摘する蝶の目的論
メンガーが築いたオーストリア学派
皇太子の家庭教師
方法論争
オーストリア学派
第5章 迂回路――起業家の回り道
「ポジティブ」な主義
迂回生産
ベーム・バヴェルク――ブルジョアのマルクス
ファウストマンの森林経済
資本の輪
ヘンリー・フォード――迂回的起業家
人生の迂回路
第7章 市場はプロセスである
大恐慌を予言した人物
ナチスからの逃亡
ヒューマン・アクション
ニーベルンゲンの起業家
ニーベルンゲンで起きた真の変化――市場が引き起こした金利低下
ニーベルンゲンを襲ったゆがみ――中央銀行による金利引き下げ
時間不整合と期間構造
ニーベルンゲンに訪れた最後の審判
オーストリア学派の見方
市場プロセスの勝利
第8章 恒常性――ゆがみのなかで均衡を求める
市場の目的論
イエローストーン効果
ゆがんだ森林からの教訓
市場サイバネティック
どのように物事が「うまくいくか」
自主的秩序
ゆがみ
砂の堆積効果
ゆがみのメッセージ「何もするな」
資本の「勢」
第9章 オーストリア流投資法Ⅰ ワシと白鳥――ミーゼス流でゆがみを探る
機能する恒常性
ゆがみの目撃者
初期のミーゼス流の投資戦略
ワシと白鳥
ケーススタディ――テールヘッジングのプロトタイプ
目標(Ziel)と目的(Zweck)――中央銀行ヘッジング
迂回的投資家
第章 オーストリア流投資法Ⅱ ジークフリート――ベーム・バヴェルクの迂回を利用する
竜退治の英雄――ジークフリート
ケーススタディ――ジークフリートを買う
バリュー投資――オーストリア流投資法の生き別れた相続人
ついに目的に到達する
エピローグ――北方林のシス
世界はフィンランドの勝利に「シス」を学ぶ
「シス」人格と人格形成
謝辞
注釈
「マークの徹底的な調査と説得力をもって迂回戦略に挑んだ本書には、あらゆる投資家が計り知れない価値を見いだすことだろう。目の前の損失は、あとで大きな利益をもたらすまでの途中経過にすぎないということを、自然や歴史が教えてくれている。われわれはそのことを理解し、そして『今を耐え、その後戦略的に性急に』なるべきなのだ」――ポール・チューダー・ジョーンズ(チューダー投資会社創業者)
「高尚かつ機知あふれる1冊だ。何度も読み直すことになるだろう。市場に学ぶ者たちならだれもが知っている、ソロス、ボールドウィン、クリップ、バフェット、クーパーマンといった偉大な人々が持つ、本質を見抜く力(本人たちは認識も理解もしていないかもしれない)を理解するための、理論的・実践的な枠組みを提供している。本書が教えるところは、戦争、森林、武術、オペラ、野球にボードゲームと幅広い。この広範な検証とその成果が各章に見られ、まさに1ページごとに目からウロコが落ちる思いだ。本書を同僚のトレーダー、友人そして仲間たちにも伝えるつもりだ。わたしは、比類なき本書を無条件にお薦めする」ビクター・ニーダーホッファー(『ザ・エデュケーション・オブ・ア・スペキュレーター』の著者)
「スピッツナーゲルが著したこの素晴らしい1冊は、通貨政策がいかに起業家や投資家たちを誤った投資判断へと導いているかを示している。このような策略を回避し、より良い投資結果を得るための手引書として本書を推奨する。マークがいうように、『われわれのだれもがいまやオーストリア学派』である」――マーク・ファーバー(『グルーム・ブーム・アンド・ドゥーム・リポート』の筆者)
「スピッツナーゲルが強調しているのは、戦略的な思考と結びついた健全な分析の基盤である。それを通じて、読者は幅広い投資哲学を得ることができるし、単に勝つことだけを求めるのではなく、勝てる状況に自らを置くことが重要であることを理解するであろう。彼の理論的支柱となっているオーストリア学派の経済学は、市場調整のなぞを解き明かすだけでなく、通貨や信用の操作がどれほどゆがんだ結果をもたらすかを説明するものでもある。スピッツナーゲルが読者に示しているのは、長期的な資産形成を成し遂げるための点の予測ではなく、プロセスの予測であり、戦略的な身の処し方である。わたしは本書を強く推薦する」――ピーター・ベーテキ(ジョージ・メーソン大学経済学・哲学教授)
「まっとうな経済原理と歴史とに軸足を置いた本書は、時期を得た、独自のものと言えよう。優れた哲学を基に、資本形成、イノベーション、そして経済的進歩を見事に照らし出したと言える。また、経済を救済するための政府による介入は、山火事を押さえ込もうとするようなもので、ほかの疑わしい政策と同様に、有害でしかないことを指摘してもいる。素晴らしい、の一言だ」――スティーブ・フォーブス(フォーブス会長兼編集長)
「素晴らしい1冊だ。スピッツナーゲルの取り組みは、新鮮かつ学術的である。それでいて退屈な研究に陥ることはない。経済史の視野を広げたと言えるだろう」――バイロン・ウィーン(ブラックストーン投資顧問会社副会長)
「FRBがいつでも助けてくれると信じきっているウォール街のばくち打ちどもこそ、本書を読むべきだ。マーク・スピッツナーゲルが見事に描き出したのは、エックルスビルに巣食う連中が、通貨は健全であるべしという原則を無効にすることも、歴史的教訓を無視することもできないということだ」――デビッド・ストックマン(元アメリカ連邦議会議員、ロナルド・レーガン政府での行政管理予算局長)
「マーク・スピッツナーゲルは、人類と経済の本質を整理し、混沌としたこの世界に秩序を導き出している。本書は、経済学者、投資家、そして一般人にとっても示唆に富んだものである。とても役に立つ1冊と言えるだろう」――ローレンス・リード(ファンデーション・フォー・エコノミック・エデュケーション理事長)
「偉大なるオーストリア学派の伝統をまとめ、実践的な教訓をつむぎだしたことは、マーク・スピッツナーゲルの優れた業績だと言える。彼は、バスティア、ハズリット、ロスバードの優れた語り部でもあり、分かりやすい例や美しい文章を通して、時に分かりにくく複雑な彼らの思考を伝えてくれる。お薦めの1冊だ」――ピーター・クライン(ミズーリ大学応用経済学享受、ルートヴィヒ・フォン・ミーゼス研究所カール・メンガー・フェロー)
「本書において、マーク・スピッツナーゲルはオーストリア学派の研究と、歴史を通じた彼らの考察をまとめ上げた。投資家としても大きな成功を収めているマークは、オーストリア学派経済学を象牙の塔から、現実の資産運用の場へと引き出し、彼らが唱える資本、迂回生産、自由市場の原理は起業家的投資においても妥当性があることを示したのである」ロン・ポール(元アメリカ連邦議員)
さて、スピッツナーゲルはヘッジファンド、ユニバーサ・インベストメンツ(Universa Investments)の社長兼CIO(最高投資責任者)でもある。私もマイアミで直接話を聞いたことがあるが、その特異な運用プログラムは株式のダウンサイド・プロテクション機能を顧客に提供している。債券と株式だけから成る伝統的なポートフォリオに対し、これらダウンサイド・プロテクションのプログラムを追加することで、投資家はテールリスク(ブラックスワン)をヘッジし、株式のウエート増加を合理化することができる。このため、結果としてリスクを下げ、期待リターンを上げる効果が期待できる。これは日欧でネガティブ金利が導入され、債券市場における収益獲得機会が激減した現在にあって、まことに優れたソリューションのひとつと考えられる。
翻訳にあたっては以下の方々に心から感謝の意を表したい。まず藤原玄氏による翻訳は素晴らしい。孫子から戦争論までさまざまな分野にわたる記述について、正確で分かりやすい訳出を実現できたのは藤原氏の博識と努力のおかげである。そして阿部達郎氏は丁寧な編集・校正を行っていただいた。また投資書籍としてユニークな存在である本書が発行される機会を得たのはパンローリング社社長の後藤康徳氏のおかげである。
2016年8月
長尾慎太郎
オーストリア学派との出合いは、デューク大学で医学を学んでいたころ、F・A・ハイエクの『隷属への道』(春秋社)を手に取ったときである。それをきっかけに、わたしは自由時間のほとんどをオーストリア学派の書物を読み漁ることに費やした。ハイエクやミーゼスのみならず、マレー・ロスバードやハンス・センホルツの書物からも「新しい」経済観を得たものである。
オーストリア学派に出合ったことで、自由市場がどのように機能するのかを完全に理解することができた。自由市場経済が国が介入する経済や計画経済よりも有益であることが、オーストリア学派を通じて、明らかとなったのだ。オーストリア学派について学ぶにつれ、そこで語られていることこそが真に自由な社会に住む、真に自由な個人が、互いに作用し合いながら生きていく世界そのものであることがはっきりとしてきた。オーストリア学派の経済学者たちが自由市場の論陣を張っていたころ、知識層の大半は集産主義や社会主義を擁護していたのである。今、改めてオーストリア学派の方々に感謝の意を表したいと思う。
経済と個人的自由の関係について斬新だと、一人悦に入っていた考えは、その実、わたしが思いつく何年も前から語られてきたことなのである。ロスバードは著書『アン・オーストリアン・パースペクティブ・オン・ザ・ヒストリー・オブ・エコノミック・ソート(An Austrian Perspective on the History of Economic Thought)』で、古代の道教の師たちこそが「世界で最初のリバタリアン」であったと語っている。道教とオーストリア学派とが、二〇〇〇年あまりにわたる自由経済、政治思想の歴史を統括するものであろう。わたしの友人であり、オーストリア学派仲間であるマーク・スピッツナーゲルは、ロスバードの洞察力溢れる考察を本書の重要なテーマに据えている。
私的所有権、自由市場、健全な通貨、そして自由社会という古典的自由主義を源流とするオーストリア学派の中心原理は、今、あらゆる自由社会の基本理念となっている。ラルフ・ライコの言葉を借りるなら、
文明社会における古典的な自由主義(ここでは単に自由主義と呼ぶが)の基礎にある考えは、概して自律的な社会の構成員たちが広範に認められた個人的権利のなかで自由に活動するべきである、というものだ。そのなかでも、契約の自由や労働の自由を含めた私的所有権は特に大切にされるべきである。……オーストリア学派経済学とは、……自由主義へと連なる学派に対して、その信奉者からも反対派からもともに与えられた名称である。
時がたつにつれ、ミーゼスの仲間や弟子たちと数多く知り合い、関係を深めていったが、やはりわれわれからしてもミーゼスは頭一つ飛び出た存在であり続けた。彼は、自分の哲学が経済界全体に受け入れられやすくなるよう、主張を弱めたりするようなことはけっしてなかった。もしそうしていれば、生前にもっと高い評価を得ていたであろうことは疑う余地のないことだ。しかし、彼は名声よりも、経済学の真理を追い求めることを選んだのである。
ミーゼスは、常に紳士的で、親切かつ思慮深い人物であり、あらゆる面で彼のようにありたいと努めたものである。世の中、特に経済が正気とも思えない事態になると、常にミーゼスの示唆に富む言葉に頼ってきた。「財政出動や信用膨張を通じた経済救済策を是とする者たちの宗教的とも言える熱気に対しては、どんな論理的主張も歴史の教訓も役には立たないのだ」
人間の行動がいかに予測不可能か、そして個々人の選択が経済全体の動きにどれほど大きな影響を与えるか、これこそがオーストリア学派の主要な考察対象である。価値の主観性、起業家の役割、世の中を前進させるために必要な資本蓄積の追及を理解しようとするものでもある。これらの事実を把握することは今日においても不可欠なことではあるが、一九世紀半ば、学派が初めて論壇に登場した時代においては、その重要性は今よりも大きかったのではなかろうか。
本書において、マーク・スピッツナーゲルはオーストリア学派の研究と、歴史を通じた彼らの考察をまとめ上げた。投資家としても大きな成功を収めているスピッツナーゲルは、オーストリア学派経済学を象牙の塔から、現実の資産運用の場へと引き出し、彼らが唱える資本、迂回生産、自由市場の原理は起業家的投資においても妥当性があることを示したのである。スピッツナーゲルの「オーストリア流投資法」はその分かりやすさ、使い勝手の良さからしても魅力的だ。また、彼の投資法を見れば、介入主義や、主流派経済学、さらにはウォール街の文化にあらがうことは容易ではないことも分かるであろう。
中央政府を牛耳る者たちが、経済を崩壊へと導く政策を次々と打ち出す姿を見ざるを得ないことにオーストリア学派を信奉する者として大きな不満を抱いている。市場とは自然の生き物だ。本書が示しているように、昨今の救済文化とは相容れない考え方かもしれないが、中央政府の計画や介入による負の影響がなければ、市場は自然と自立的安定を取り戻すのだ。
中央銀行は、その意に反して、自らの行動を通じて今だかつてない規模のゆがみをもたらしているのだ。彼らは、世の中にお金をばら撒けば、過去の介入主義政策がもたらしたあらゆる問題をどうにか解決できるのではないかと、わらをもすがる思いで考えているのだろう。
世の中の人々は、それほどバカではない。官僚による操作を排除し、資本主義本来の働きに期待しようではないか。三五年あまりの間、医師として務めてきたわたしは、人間の体が持つ自己治癒力を阻害するようなことはしてはならない、という「ヒポクラテスの誓い」を奉じる者でもある。政府もそうあるべきで、市場の自己治癒力を尊重すべきである。これこそが本書のメッセージの根幹を成すものであろうし、市場とともにある、ということであろう。
自由市場の重要性に対する理解が深まるにつれ、それを守るためには政治活動を通じて戦わなければならないと感じるようになった。その活動は、教育から革命までさまざまな形をとり得るだろう。アメリカでは、教育や説法、または民主的なプロセスを通じて必要な変化をもたらすことが可能である。言論の自由、集会の自由、信仰の自由、請願の自由、私的所有権といったわれわれの権利は今もって守られている。それらの権利が阻害される前に、何十年にもわたる政府介入により産み落とされた政策を変えなければならない。
建国の父たちは正しく認識していたとわたしは信じている。少なくとも、憲法制定以来、個人の権利を阻害することに血道を上げてきた彼らの後継者たちよりは。わが国は、自由という価値に基づき建国されたのだ。いまさら個人の自由が持つ価値を説明するまでもなかろう。教育制度、メディア、そして政府というおかしな力が、自由に対するわたしの本能に戦いを挑み続けている。彼らは常々、あらゆる物事から人々を守るために政府が必要なのだと説き続けてきた。しかし、何ものにも制約されない市場こそが、個人の自由と調和するものだというわたしの信念が揺らぐことはない。
この自由は、オーストリア学派経済学の基本コンセプトでもある健全な通貨を介して伝えられていくものである。主流派の経済学者たちは、この重要性を無視し、さげすみ続けてきた。このような経済の「専門家たち」がもたらす終わりなき害悪は、彼ら自身が証明するところであろう。
ミーゼスの言葉を借りれば、通貨とは市場が適切に機能するために役立つ商品として、市場のなかで生み出されるべきものなのだ。通貨が持つ役割のうち、最も重要なのは交換手段としてのそれである。そして、価値評価手段、富の貯蔵手段として機能する。
残念ながら、政治家たちは通貨の膨張が経済成長につながると信じているようなのだ。彼らは、政府は何も生み出せないという事実に目を閉ざしている。「政府が人々を豊かにすることはできないが、貧しくすることはできる」。その逆を真とするのは、あまりにおめでたいと言わざるを得ない。一九世紀半ばの経済学者フレデリック・バスティアの珠玉の一篇『ザット・フィッチ・イズ・シーン、アンド・ザット・フィッチ・イズ・ノット・シーン(That which Is Seen, and That Which Is Not Seen)』で語られた目先の結果のさらに先を考えるべき、との教訓に耳を傾けるべきである。またこれは、本書でスピッツナーゲルが語る主題の一つでもある。
FRB(連邦準備制度理事会)は市場に直接介入することも、金利を通じて市場に口をはさむこともできるが、究極的には自由市場経済の変わることない性質から逃れることはできない。政治家たちは通貨制度を自分たちの好きなようにいじくり回すことはできても、通貨の本質を規定している経済法則を書き換えるようなことはできない。これまでにも述べてきたように、権力を独占する少数の者たちによる腐敗は、多くの者たちの長年にわたる負担のうえに、一部の者たちだけを富ませるものではあるが、最終的には自然の法則が勝つのである。市場における自由な選択によってしか、経済合理性は生じ得ないのだ。
通貨は常に中立的な存在と考えられてきた。通貨供給量が価格決定に重要な役割を果たすとは考えられてこなかった。むしろ、商品の価格は、単純にそのものの需給関係によって規定されるものと考えられていたのである。このことは、初期のオーストリア学派の経済学者たちもそれとなく受け入れていた節がある。しかし、それゆえにミーゼスは通貨の非中立性というものに取り組むことになったのだ。秀作『ヒューマン・アクション』(春秋社)で述べている。
通貨価値が中立かつ安定的ではあり得ない以上、通貨発行量に関する政府の計画も、社会を構成するすべての人々に対して公平ではあり得ない。通貨価値に影響を与えようとする政府の施策は、しょせん指導者の個人的な価値判断に依拠せざるを得ないのだ。あちらを立てればこちらが立たず、というのが世の常で、公益または公共などと呼ぶには程遠いものとなる。
一国の通貨を改竄するということは、収入、貯蓄、日々の買い物など人々の生活のすべての経済的側面に干渉する、ということである。政治家の意に基づいて通貨が操作されると、必ずといってよいほど、混乱、失業、そして政変が引き起こされる。それゆえに、通貨は軽々しく扱われるべきものではなく、インフレを抑え、またまじめな市民が繁栄することを可能にするためのものでもあるということを認識する必要があろう。
本書がはっきりと示したように、常に価値が目減りしていく不換紙幣が用いられている市場経済での投資は極めて難しいものとなる。通貨が堕落すれば、政府は秩序を保つために自分たちの権力を増大させ、さらに市場へ介入してくることだろう。歴史を振り返ると、政府の役人どもは、もはや取り返しのつかない状態になっても、経済計画が機能しないということを認めようとはしない。そして、政府が「大量の通貨を発行すること」でそれを取り繕おうとすれば、事態は悪化するばかりなのだ。FRBの役割に関していえば、アメリカ人にとってこれほど分かりやすい話もあるまい。
皮肉な話であるが、あらゆるものの価格のうち最も重要なもの、つまり時間の価格、言い換えれば、金利については、政府は介入をやめ自由市場に委ねるべきだというコンセンサスができあがっている。金利こそが、政府が通貨価値をコントロールする手段である。この価格統制を通じて、政府は消費者と生産者との間を取り持つ市場の機能をゆがめているのである。この市場の調整機能が失われると、単に通貨供給量や中央銀行による信用創造の操作だけに起因して好不況を繰り返すことになる。このことを明らかにしたことは、オーストリア学派経済学者の功績であろう。オーストリア学派にすれば、失業率や一般的な生活水準などの問題は、国家が推し進めている通貨政策の反映だとすることもできよう。
ミーゼスは、通貨が経済それ自体よりも大きな政治問題となり得るということを理解していた。タカ派かハト派かにかかわらず、財政赤字を擁護する向きにわたしが強硬に反対するのは、ミーゼスの指摘に負うところが大きい。彼らがどう論じようと、つまりは不換紙幣を頼りに、インフレによって政府の資金繰りをやりくりし、それぞれの既得権益を守っているにすぎないのだ。
政府による介入は人民の敵とするところで、個人的な自由こそが真の自由を獲得するために必須のものであることをオーストリア学派は徹頭徹尾主張している。この信念と、ミーゼスという先達がいたからこそ、わたしはワシントンや議会でもやっていくことができたのだ。
「オーストリア学派経済学」という言葉が広く受け入れられるようになるとは思ってもみなかった。しかし、二〇〇八年以降、この言葉が広く浸透し、オーストリア学派を長く信奉してきた者としては興奮を抑えられずにいる。オーストリア学派が教えるところによれば、現在の世界には暗い将来しかないように見える。しかし、前向きでいられる理由もたくさんあるのだ。つまり、若い世代の存在である。数多くの若者がわたしの仲間となってくれたことを大いに誇りに思う。またこれは、アメリカの若者たちが自由と経済というものをどのように受け止めているかの現れでもあろう。
これらの原理原則がさらに一般の知るところとなり、ミーゼスや彼を師と仰ぐ者たちが信奉してきた経済的真実が明らかになれば、われわれはいずれ母国を健全な経済基盤のうえに置くことができるであろう。
自由とはまさに大衆のものである。そのことをしっかりと認識することこそが、オーストリア学派というものを受け入れることにもなろう。
ロン・ポール
まず、資本の概念を改める必要がある。これは名詞的ではなく、動詞的にとらえるべきものである。無生物的な資産またはその一部というよりも、経済を進歩させるための道具を作り、改良し、実際に適用するための行動または手段を成すものである。言ってみれば、資本とは「プロセス」、方法、道筋、つまり古代中国人が「道」と呼ぶものである。
資本には二つの時点をつなぐ、という特徴がある。将来の異なる時点における位置取りまたは優位性がその中核を成す。時間とはそれを「取り巻く」もの、つまり規定し、形付け、助け、時に妨害するものである。資本同様に、このプロセス、つまり「資本道」に取り組むにあたっては、時間というものもとらえ直さなければならない。
このプロセスの特徴は、極端かつ意図的に回り道をするというものだ。つまり、本書のキーワードである「迂回」である。「左に歩を進めるために、まずは右に進む」ことで、「手段」を押さえる。この戦略的な中継地点を得ることで、より効果的に究極の「目的」を達成することができるようになるのである。このプロセスは、北方林のような自然界から、起業家たちの棲む実業界まで、至るところで目にするものだが、あまりに当たり前すぎて気づかないだけのことなのである。われわれは時に目的地にばかり目を奪われて、その途中の道筋を見落としがちである。だからこそ、勝負に負けるのだ。
これは、日々の生活における戦略的思考や意思決定といったあらゆる場面で通用する教訓である。しかし、本書は投資について語るものであり、それこそが筆者の主眼である。投資とは人類独自の行動であるが、この教訓が最も活きるのも投資であることを本書を通じて明らかにしていくつもりだ。ブルームバーグ端末やブローカーのウェブ画面などのきらめきは、そこに映る短期的な利益という魅力も手伝って、あたかもわれわれが追い求めるのはそれだけかのように思えてしまう。見えざるものこそが、見えるもののうしろに隠れる目的論的メカニズムであり、いわば時とともに動き回る「世界のエンジン」なのだ。時間的束縛ゆえに目先のことにしかとらわれないウォール街は、このような経済のメカニズムに目を向けるはずもなく、ただ実際に起こっていることの影を追いかけているだけである。
救いがあるとすれば、これらのメカニズムは本質的に極めて単純だということだ。さらには、オーストリア(ウィーン)学派経済学が分かりやすく説明してくれてもいる。このオーストリア学派というのは、一九世紀の文化的・知的集団に、その誕生の地にちなんで半ば侮蔑的につけられた名である。カール・メンガーとオイゲン・フォン・ベーム・バヴェルクを祖とするこの集団は、資本をより生産的な目的を達成するための迂回手段としてとらえる新しい考え方を打ち出した。彼らの知的後継者であるルートヴィヒ・フォン・ミーゼスがオーストリア学派をさらに進歩させ、今日においてなお、彼の名が学派の旗印となっている。
オーストリア学派以外にも、われわれの範となるものがある。実に二五〇〇年も昔、古代中国にも戦略的思考の核をなした人々を見いだすことができる。道教の師たちがそれだ。彼らは、始まりは終わりであり、終わりはまた始まりであり、柔はまた剛であり、剛はまだ柔であり、進歩とは退却であり、退却とはまた進歩であるとする二元論的思考を持っていた。洋の東西に見られるこれらを原点として、われわれは、欲望の求めるところだけに集中するのではなく、幾つもの時点をつないでいく術を学んでいく。遠回りする術を追い求めながら、全体像をつかんでいくのだ。
過去の偉大なる戦略家たちは、後の優位性にための手段に気を払う、ということを学ばずして身に付けていた。迂回戦略をとった起業家の典型としてヘンリー・フォードが挙げられるが、彼も直感的にそれを理解していたのであろう。しかし、投資家としてのわれわれには終わりなき複雑な世界は見えても、生産、経済的進歩、そして死滅という手段と目的のプロセスは分かりにくいものだ。ここでフィンランド人指揮者であるジャン・シベリウスの言葉を引用しよう。「あらゆる音色や解釈のカクテルをつくるよりも」、ありのままの、原始的な方法で「冷えたお水」を提供したいと願っている。
本書をつうじて、資本ならびに資本主義的投資のメカニズム、つまり市場プロセスそのものの手段、方法論に対する認識を新たにしていく。このメカニズムと歩をあわせることで、筆者が「オーストリア流投資法」と呼ぶところの知的な、さらにいえば実践的な原理原則を見いだすことになる。オーストリア流投資法とはつまり、利益そのものを直接的に追い求めるのではなく、利益を獲得するための迂回手段を取りにいく、というものだ。
出版社から執筆の話をもらい、筆をとることを決心したとき、まずは徹底的に己を振り返ることから始め、その後文字に落とし込んでいった(投資家としてはプロであると自認しているが、書き手としては素人なので、前者は純粋に楽しめたのであるが、後者は苦痛でしかなかった)。自身の投資方法を説明するために、北方の針葉樹林から、中国の戦国時代、ナポレオン期の欧州、アメリカ産業の黎明期、そして当然のことながら、一九世紀から二〇世紀のオーストリアに現れた偉大なる経済学者たちと、回りくどいまでの旅路を歩んでみた。そこに共通するのは、常に目的よりも手段を志向する、つまり利益よりも、市場のプロセスとの調和を求めるということだ。ヘッジファンドの運営を第一としながら、二年余りに及ぶ筆者の努力の成果が本書である。余談ながら、本を書くときに最も恥ずべきことは、率直にいえば「我田引水」をしていると非難されることであろう。筆者が記したのは、投資家として、またヘッジファンドマネジャーとして実践していることにすぎないが、ファンドの追加出資はもう受け付けていないこと、そして本書の印税はすべてチャリティに充てることを記し、いくばくかの弁明とさせていただきたい。投資に関する本を著しながら、我田引水をはかるような輩は大いに軽蔑されるべきだと筆者は考えている。
本書は、オーストリア流投資法を紹介するものだ。筆者が提唱する方法の効果を示すために、数字を駆使することにもなるが、それは最後の二章で記すにすぎない。筆者の議論の大半は、オーストリア流投資法の基礎となる、すべての重要な考え方に充てられている。お読みいただければ分かることだが、このような回りくどい本の構成になったのも、考えてみれば目的を達成するためには間接的な道を進むべきだという筆者の投資手法に合致しているとも言えるだろう。
では、本書の全体像を記したい。
第1章では、CBOT(シカゴ商品取引所)の古老エベレット・クリップから受けた教えを通じて、筆者なりに市場のプロセスを紹介する。彼の教えは図らずも古代道教の教えや『老子』または『道徳経』として知られる偉大なる書物と相通ずるものがあった。今日に至るも「クリップイズム」には学ぶことが多い。その後、自然界に論を進め、自然界が持つ生産的、時に日和見主義的な成長戦略が教えるところを学んでいく。
第2章で述べるとおり、針葉樹の基本思想は世代間での迂回戦略である。つまり、まずは岩だらけで、ほかの植物が生息できないような荒れ果てた地に退却し、そこから野火がつくりだした肥沃な土地へと進出していく。
針葉樹のこの戦略は、第3章で見るとおり、孫子をはじめとする独創的な戦略家または意思決定者が用いる標準的な軍事戦略にも認められる。孫子の教えは、『孫子の兵法』の言葉だけが引用されることが多いが、それは戦略的な優位性とも言い換えられるであろう「勢」を中核とするものである。同様の考えは、カール・フォン・クラウゼヴィッツの『戦争論』でも語られている。誤解も多い彼の著書であるが、クラウゼヴィッツが主張しているのは、戦略上の要衝を押さえ、敵を弱体化させ、より目的合理的に勝利、さらには平和を獲得せよ、というものである。
第4章では、イデオロギー抗争を戦った人々に見られる迂回戦略を見ていく。オーストリア学派経済学者の原型とも言えるフレデリック・バスティアは、マルクス主義者と戦い、見える者と見えざる者という考えを残してくれている。また、オーストリア学派の祖メンガーは、プライオリストという立場を取り、ドイツ歴史学派は経験主義へのやみくもな傾倒にすぎないとして戦いを挑んでいた。
メンガーに続き、第5章では、オーストリア学派を世に知らしめたベーム・バヴェルクについて述べる。彼は、貯蓄と投資、資本蓄積の関係についての見識を世に示した。そのおかげで、今日の投資家は市場プロセスを理論的に理解することができるのだ。資本に関する彼の理論は、より深遠かつ効率的、生産的な資本構成を積み上げるための「迂回生産」を描き出すものだ(石炭と鉄を大衆向けの自動車へと仕立て上げたフォードが好例であろう)。
第6章で見るように、迂回することの難しさを過小評価すべきではない。われわれ人類は時間選好という生来の特質と、遠い将来なら待てるが、近い将来ならば待てないという時間に対する近視眼的な矛盾を抱えているからである。実社会においては、行動経済学で「双曲割引」と呼ばれるように、人々は遠い将来に比べて、近い将来では単位時間当たりの割引幅が大きくなるように思われる。この特質は、筆者が資産価格とは何かを理解するために重要な役割を果たしているのであるが、ベーム・バヴェルクは時代を先がけること一〇〇年以上も前に、同様の事柄を書き記しているのである。目先の利益を強く求める人類の奇癖ゆえに、一見安易に手にできそうな利益には警戒すべきであるし、一方で、後の優位性を確保するために、当初は不利な立場に甘んじるという迂回戦略を実践することは、本能に反した取り組みであるがゆえに、ほとんど不可能にも思われるのだ。老子いわく、「明道は昧きが若く、進道は退くが若く、夷道は煩しきが若し。上徳は谷の若く……大器は晩成す」。
第7章では、一九世紀初頭から半ばにかけての、実社会における起業家精神と経済循環を語ったミーゼスの考察を引用し、「市場はプロセスにすぎない」という彼の偉大なる教えを学んでいく。彼の研究は「動的な人間」の活動が主眼となる。それは、オーストリア学派経済学者のマレー・ロスバードが「人類は目的合理的に行動するという根源的事実がある。これは絶対的なものである」と指摘するところのものである。人類は主観的目的を達成するために手段を選択するという点に焦点を当てたことで、ミーゼスは市場プロセスだけでなく、幅広い歴史の趨勢を理解することができたのである。経済に対する認識を確たるものにしなければ、経済史家たちが経験的証拠を分析したり、一見もっともらしい「関係」を述べたりしても誤るだけであるとミーゼスは説いている。
第8章では、干渉主義政策によるゆがみが自然界に内在する統制力を働かなくしてしまう様子を見ていく。それが森林であれ、市場であれ、システムの恒常性を維持するための力は常に働いており、元の状態に戻る道筋は極めて複雑であるけれども、いずれは収束するのである。それゆえ、市場プロセスは、大きな「目的論的」メカニズムであると見ることができる。中央銀行が自然な動きをゆがめると、このメカニズムが拒絶反応を起こすがために、負のフィードバック・ループを示すことがある。
ここまでの八つの章を通じて、「資本道」、つまり期待する結果を手にするための迂回手段の基礎を構築していくことになる。遠回りをいとわない者、一見関係性が希薄なように思えることも受け入れられる者だけが、最後の二章、オーストリア流投資法と呼ぶところの資本投資戦略の議論から得るものがあるのだ。これは、オーストリア学派の視点からしても新しく、また重要な分野であろう。オーストリア学派は伝統的に自らを学術的な経済分析や政策提言に閉じ込めてきた。つまり、起業家精神ないし市場プロセスを存分に発揮させるには何をなし、さらには何をなさざるべきかを問うてきた。しかし、本書の最後の二章においては、政策提言から実践的な投資へと歩を進め、極めてゆがんだ現実社会を航行していく。筆者の投資法は、オーストリア学派の偉大なる経済学者たちから長い年月をかけて学んだ考え方に大きく依拠しているものなので、これをオーストリア流投資法と名づけている。本書の主たる目的は、オーストリア学派の重要性をほかの投資家にも伝えることであり、オーストリア学派の考え方から何かを得てくれれば良いと考えている。
投資家は、現在のシステムがいまだかつてないほどゆがんでしまっていることを認識しなければならない。政府の介入という命取りにもなる飼料がなければあり得ない資産膨張は、遠からぬ将来、大爆発を引き起こすほど一触即発の状態にあるのだ。第9章で見るとおり、株式市場の大きなゆがみを見れば、向こう数年の間に相当な暴落を予測しておくべきであろう。自嘲していうなら、本書の大部分を費やして、なぜそのようなことが起こるのかを述べたつもりである。急を要することであるがゆえに、暗く、批判めいた警告を文面に盛り込んでいる。
第9章、オーストリア流投資法Ⅰでは、筆者がミーゼス流定常性指標と呼んでいる測定方法を使って、システムのゆがみを正確に測定する方法を学んでいく。これは、ミーゼスが唱える原理に基づき、いつ市場から退却し、いつ市場に入るかを知ることでわれわれを市場のゆがみから守るものであり、さらには「テールヘッジ」と呼ばれる高度な戦略を用いて、市場のゆがみから利益を獲得するためのものでもある(残念ながら、この戦略は一般の投資家はもとより、プロの投資家ですら用いるのは難しい)。筆者は、この投資手法で名を知られているが、手の内を明かすと、マーケットイベントに関して言えば、インパクトのあるブラックスワン、いわば予期せぬ「テールイベント」など存在しないのだ。多くの人々が見落としていることほど、その実、予見可能なものなのである。
第10章、オーストリア流投資法Ⅱでは、ベーム・バヴェルクの原理を用いて、実践すべき迂回的な資本構成を探求する。そこでは、ウォール街とは異なり、すぐに利益をもたらすことはないけれども確実に利益を上げていく企業に目を向ける。オーストリア流投資法は、バリュー投資として知られる手法より古い、より原始的な方法といえよう。オーストリア流投資法はバリュー投資よりも歴史があるだけでなく、さらに磨きをかけたものと言える。
エピローグでは、北方林からの教えでもあるシス(sisu)に焦点を当てて、迂回戦略をまとめる。
オーストリア学派の理論的洞察を市場プロセスの本質と組み合わせることに加え、筆者の投資法はオーストリア学派の取り組みを経済そのものに反映させている。物理学者のように自らの考えをモデル化したがる主流派経済学者たちとは異なり、ミーゼスの伝統をくむオーストリア学派は、曲線の当てはめや、計量経済学のバックテストなどは用いない。
ミーゼスの言葉に真摯に耳を傾けるならば、景気循環のような経済現象を理解することについては、「これらの事実が意味するところは自明である」などとは言えないことが分かるであろう。特に株価の動向を予見しようとするなら、なおさらのことである。自分たちの進むべき道を定め、どの事象が関係し、どの事象が無視しえるかを選択し、そして重要なことに集中するためには、推論が必要である。論理的推論が投資哲学を導き出して初めて、経験的調査を用いて「自分たちの仕事をチェック」できるのであるし、まさにそうするつもりである。
本書においては、即席の戦略ではなく、投資、さらには人生の重要な活動に適用できる考え方を通じて筆者の方法論を紹介していく。つまり、あとに訪れる機会を台無しにすることのないよう、目の前を流れる多くの機会を賢明に選択していかなければならないということだ。思考がなければ、行動は根拠のないものとなってしまう。論理的思考は何にもまして重要なものである。
若きトレーダーとして取引所に降り立った(実際に最年少であった)とき、クリップは筆者に、自分はなCBOTにいるのかを確実に理解させようとした。第1章でも触れたが、けっしてお金を稼ぐ方法を伝授されたわけではない。もしお金を稼ぐことだけを考えていたとしたら、彼はこう言っただろう。「もうここにいることはないだろう。むしろ、ラサール駅の行列に混じって、電車に乗り込むのを待っているだけだ」と。筆者も読者に同じことを伝えよう。お金を稼ぐ方法を教える書物があるのなら(そんなものはめったにないのだが)、書店の長い列の最後尾に並べばよいだけだ。
本書で意図するところは、読者に考え方を教え、迂回戦略の原則を伝えることだ。大人になってからゴルフのスイングやスキーを学ぶときと同じように、基本となるメカニズムを理解し、実践できるようにすることが狙いである。それができれば、この戦略に不可欠な遠回りもできるし、資本を迂回させることもできるであろう。もし道に迷っても、オーストリア流のコンパスを用れば、その戦略的思考と同じように古くからある迂回路を通じて、左に行くために右へと進むことができるであろう。
『老子』の言葉を引こう。「千里の道も一歩から」では、本書とともに第一歩を踏み出そうではないか。
2013年7月 ミシガン州ノースポート
マーク・スピッツナーゲル