著 者 マーク・ダグラス
訳 者 世良敬明
◆立ち読みコーナー
訳者まえがき・序文・はじめに・第一章 成功への扉
マーケットについてよく知っている投資家はいるだろう。買い時、売り時、有望株を識別する優れた分析手法についてもよく知っている投資家はいるだろう。
しかし自分自身についてよく知っている投資家はどれだけいるだろうか?
たとえ非常に鋭敏な分析力があり、かなり意欲的で、幅広く奥深い知識があったとしても、決断力に乏しく失敗を恐れていては、再起不能のミスを犯してしまう可能性が常にあるのだ。実際、多くの投資家がトレードやマーケットの本質について誤解と矛盾した信念を抱いている。そのため客観的な集中力を維持できず、的確な執行に不可欠な自信がなくなってしまい、トレードに悪戦苦闘してしまう。
そして、その結果はどうか。大半の投資家がトレードを始めてから1年以内に、資金の全額か、あるいは大部分を失ってしまうのだ。
マーク・ダグラスはトレーディング・ビヘイバー・ダイナミクス社の代表を務め、金融業界の有力者や大手企業から広く尊敬を集めているトレードのコーチである。約20年間にわたって、多くのトレーダーたちが自信、規律、そして一貫性を習得するために、必要で、勝つ姿勢を教授し、育成支援してきた実績がある。
ダグラスにとって、トレードで成功を収めるカギは、網羅されたマーケット分析や最新型の「システム」ではない。投資家自身の心理の強化にある。そしてそのためにはトレードを確率的視点から考察し、適切な中核的信念を取り入れて「勝者の心構え」を持つ必要があると主張する。「ゾーン」状態に達したトレーダーは、マーケットが次にどうなるか知る必要はないし、気にしない。「自分」が次にどうしたよいか知っているのだ。そこには決定的な違いがある。
本書では、投資家がトレードで一貫した結果を出せない隠された理由を明らかにし、奥底に潜む心の習性がもたらす障壁を乗り越えるため、実践的なプロセスが提示
されている。ダグラスはマーケットの神秘に挑戦し、見事にひとつつひとつそれを明確にした。すべての株式トレードを支配する「不確実性の原理」を本書から理解すれば、ランダムな結果を大局的に見て、リスクの本当の現実を受け入れられるようになるだろう。
本書から、マーケットで優位性を得るために欠かせない、まったく新しい次元の心理状態を習得できる。「ゾーン」の力を最大限に活用し、大きく飛躍してほしい。

「たとえば友人からこんなプレゼントを受け取った経験はないだろうか。一見、何の変哲もないものなのに、使えば使うほどその有難さが身に染みてくるような贈り物だ。最近、私にもそうした経験があった。トレードがまったく客観的にできるようになれば(つまり恐れず、ストレスがなく、欲張らず、通常のビジネスをしているときとまったく同じようにトレードを判断できるようになれば)、この優位性から収益力が向上するのではないだろうか。トレードがより本心から楽しめるようになるのではないだろうか。間違いない。その通りだ。では、この心構えはだれにでも習得できるものであろうか。これまた間違いない。その答えは「イエス」だ! 私が受け取った贈り物は『ゾーン』という名の本である。著者のマーク・ダグラスとは個人的な面識はない。しかしだれもがマーク・ダグラスの“賜物”を手にしてほしいと強く感じた 次第だ」
――ウエルズ・ワイルダー(トレンド・リサーチ社代表、『ワイルダーのテクニカル分析入門』『ワイルダーのアダムセオリー』の著者)
「まず概念からして魅力的だ。そして初めの数章を読めば、現時点で本書がトレード心理学の最高傑作であると実感するであろう。マーク・ダグラスはトレード心理学の教科書的価値のある作品を発表した。『規律とトレーダー』は非常に役に立つ、洞察力のある、そして助けとなる本である」
――アレキサンダー・エルダー博士(フィナンシャル・トレーディング・セミナーズ社代表、『投資苑』の著者)
「マーク・ダクラスは、トレード業界にいまだかつてないものをもたらした。それは利益を積み重ねるために必須の心理テクニックを段階的に習得する機会だ」
――ジョン・マーフィー(JJMテクニカルアドバイザーズ代表、『マーフィーのテクニカル分析』『市場間分析入門』の著者)
続きを読む
「私が自信をもって本を推薦することは滅多にない。しかしマーク・ダグラスの 『ゾーン』は例外だ。『新マーケットの魔術師』でご存知の方もいるように、私は22年間マーケットとかかわっているが、今では株式や先物のトレードには技術面だけでなく、心理面での鍛錬が重要なのだと固く信じている。そして本書が提示しているのは、まさに有能かつ一貫したトレーダーになるために絶対に欠かせない心の姿勢だ。マーク・ダグラスはベストセラーとなった前作『規律とトレーダー(The Disciplined Trader)』で、トレード心理学の指導者としての地位を確固たるものとした。そしてその専門的土台を踏まえ、『ゾーン』では「なぜそうしてしまうのか」「どうしてそうしてしまうのか」という根本的な説明から始まり、問題点を明確に分析し、そして心から自信を持ってトレードできるようになる筋道を提示し、最終的にはそのためにどのような行動を取るべきかが具体的に解説されている。この本は買いだ! 文句なしに推薦できる」
――ロバート・クラウス(フィボナッチ・トレーダー・コープ代表、『ギャン 神秘のスイングトレード』の著者)

「トレードの心理面は、成功者となるために大変重要な分野である。そしてマーク・ダクラスは、この分野での最高の指導者であり、第一人者である。氏は『ゾーン』という、これまた優れた本を出版した。それは一度読み出したら、文字どおり“やめられないとまらない”作品だ。トレードへの心理的アプローチで役立つだけではない。人生のあらゆる面で役に立つだろう。自信をもってお勧めできる」
――ジョン・ヒル(フューチャーズ・トゥルース社代表、『勝利の売買システム』『究極のトレーディングガイド』の著者)
「マーク・ダグラスから授かった教えは、私がハーバード大学で受けた教育よりも価値があると言って過言ではない。トレードを始めて9年になるが、多くの優れたアナリスト、システム開発者、心理学者、催眠術師について研究してきた。しかしトレード計画の立て方まで教えてくれる人は、マーク・ダグラスただ一人である。そしてさらに素晴らしいのは、氏の教えがマーケット以外にも適用できるところだ」
――ピーター・イーストウッド(トレーダー)
「『規律とトレーダー』が読めるとは何という幸運だろうか。普通はトレードの独学は非常に“つらい道のり”である。しかし本書は無我夢中で読んだ。
『これは自分のことではないか』『これは自分のためではないか!』。まるでマークが自分の横で友人として指導してくれているかのような気持ちになって読んだ。読者の皆さんにもこの経験を楽しんでいただきたい」――ティモシー・スレーター(ブリッジ・フィナンシャルズ社代表)
「『規律とトレーダー』と『ゾーン』は、今までに読んだトレード心理学に関する本の中でも最高の部類に入る。どのページも貴重な洞察に満ち溢れている」
――ラリー・ペザベント(アストロ・サイクル社代表、『フィボナッチ逆張り売買法』の著者)
「私のトレード歴は長く、その間に数多くのトレード書を読んできたが、今までどのような本も推薦した経験がなかった。しかし本書は、トレードをしようと思うなら必ず読まなければならないと思う。トレードから恐怖、ストレス、不安を排除する心理状態を築く方法が紹介されているが、これが実践できれば、ほとんどのミスを取り除き、一貫した成績を維持できるようになるであろう。バン・タープやルス・ルーズベルトのセミナーを受講した経験があり、確かにそれはそれで素晴らしいのだが、本書はまさに核心を突いていて、適切な心理状態となるに必要なものを習得するのに最適である。一貫して収益を上げられるトレーダーを目指しているのであれば、マーケットと各トレードの認識の仕方が、どれだけ注意すべきことであるか知っておかなければならない。語弊を恐れずにあえて言わせてもらえば、トレーダーの95%がこのことを学ばなかったばかりに失敗しているのだ。当初の限定版は150ドルであったが、そこにある情報には千金の値打ちがあった!」
――エレリー・コールマン(チョイス・デイ・トレーズ社)
「96年前半、米市場ではハイテク株が悪化し、私は投資顧問(株式ブローカー)として、悪夢の日々を送っていた。かなり積極的なトレード判断によって数銘柄に過剰集中した結果が裏目に出て、ドローダウンが証拠金を超えるなど損益曲線が大きく変動するのを目の当たりにした。ストレスが増大し、損失も増大し、まさに生きるか死ぬかの心理状態にあった。文字どおり混乱し、私の言動が多くの人々の生活に悪影響をもたらしていた。
絶望の淵に沈んでいるとき、偶然ニューヨーク・インスティチュートの図書館でマーク・ダグラス著の『規律とトレーダー』の話を聞いて、早速注文した。そして到着するやいなや夢中になって読みふけり、週末までに6回は繰り返し読んだ。わらにもすがる思いだったのだ。そして本書に指摘されていたことが、どれだけ自分の現状に当てはまるかを知って驚いた。自分の経験がまったく一般的なパターンであると初めて知ったのである。
それだけではとても我慢できなくなり、マークの連絡先を探し出して電話をかけ、自分の状況を説明し、正直なところ「治療」してほしいのだと訴えた。まず始めたのは本書をさらに何度も読み返すことであった。そして、氏の講演テープを聞き、個人相談をしてもらった。2年後、私の生活は一変した。実際、この文章を書いている今は短期休暇中である。トレードや仕事に何の懸念もストレスも感じていない。
マーク・ダグラス、そして氏の著書の『規律とトレーダー』と『ゾーン』は、現在の自分のモノの考え方に重大な影響をもたらしており、そのことに心から感謝している。私にとって非常にかけがいのない支えである」――グレッグ・ビーバー(ビーバー証券代表)
「真の意味で成功者となるために乗り越えなければならない重大な心理的葛藤やストレスを理解している初心者はほとんどいない。往々にして未熟なトレーダーほど、心理学の重要性を無視するか、過小評価する傾向にある。マーク・ダグラスの新作『ゾーン』で提供されている洞察と戦略は、単に読んで面白いだけではない。初心者にもベテランにも如実に運用成績の向上をもたらす可能性が高いのだ」
――トム・ビーロビック(オメガリサーチ社、投資家教育担当の責任者)
「マークの新作『ゾーン』を読んでいて、思わず声を出さずにはいられなかった。『うわあ、まさにその通りじゃないか』。本書には、ほかでは見られないであろう非常に貴重な洞察がある。まさにマークは独創的な思想家だ。いや、独創的な究極の思索家なのだ。
今はやりの通俗的な心理学から派生したようなトレード心理学の本を数多く読んできたが、そうした内容とはまったく異なり、極めて正確にトレードの本質をつかんでいる。それは人間のあらゆるほかの努力とはまったく異なる心理的戦略を必要とする点である。だからこそ、マークが言うように、医学、エンジニア、ビジネスといったほかの職業での成功者の多くがトレードをすると、悲惨な結果に終わるのだ。
これには私自身も思い当たる節がある。トレードで前向きな考え方を持つと、トレードでは厳禁である希望的観測をつい導いてしまう。そして希望的観測から、自分は負けとは無関係だと思い込んでしまうのだ。マークの心理戦略は、氏自身の経験、そして氏がともにした世界最高級のトレーダーたちの経験から体系化されている。勝利者のような思考法を望むのであれば、この本を読んでほしい」――エディー・クォン(カサンジャン研究所)
「マーケットに関する本は数え切れないほど読んできたが、おそらく私にとっての最高傑作は『規律とトレーダー』であろう。
マークは以下の点を主張している。①トレードが洗練されればされるほど、一貫したトレード結果はなおさら心理面にかかってくる。そして、②どんなに網羅したマーケット知識も、自己規律と感情をコントロールする術を学ばないかぎり、何の益ももたらさないだろう。
この主張をまったくでたらめだと思うのであれば、あるいは自分がこの本を読む必要もないほど傑出した人物であり、何でも知っているのだと思うのであれば、どうかマークの本を読まないでほしい。私たちはマーケットを通してそうした人たちから資金を得ているのだと思う。勝者がいれば敗者もいるのだろう」――カーク・ウッドリー(メリル・リンチ社バイス・プレジデント)
「『ゾーン』は現時点でマークの最高傑作である。これであらゆるトレーダーが手元に置いておくべき本は2冊となった。図書館で借りるような本ではない! 本書は150ドルでもお買い得だ」
――ジム・トゥエンティマン(アストロ・チャーツ・タイミング・ニューズレター社代表)
「私は前作を何度も読み返していて、そこから得た知識のすべてが非常に役立っているのだが、この『ゾーン』を読んだとき、本当の意味でピンとひらめくものがあった。実際に本書を読んで以来、自分のトレードに重大かつ有益な変化が生じている。 「何事も起こり得る」という文言は非常に単純だ。ところが、現実に起こったことを本心から認められるようになったとき、トレードから驚くべき自由を経験したのである。そしてもちろん、その自由が本書で明確に説明された心理状態をもたらしているのである。驚くべきことだ! 一貫性を維持するために何度も本書を読み返すつもりだ。本当にありがとう」
――ジョージ・ポールマンⅢ世(トレーダー)
「『ゾーン』は情報満載で、トレードで成功するために重要な“カギ”が盛り込まれている。初心者から熟練者まであらゆるトレーダーの必携の書であると本心から思う」
――レイ・バロス(コモディティー・トレーダーズ・クラブ・ニューズ社)
「『規律とトレーダー』に記載されていた概念が、精神分析医としての私の仕事に共通するものがあるのは非常に興味深かった。これほどの明晰な思想家である著者に、心から感謝したい。新作の『ゾーン』の出版を心待ちにしている」
――アリックス・ワイス・シャープ博士(精神分析医)

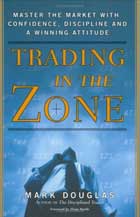 シカゴのトレーダー育成機関であるトレーディング・ビヘイビアー・ダイナミクス社の社長を務める。商品取引のブローカーでもあったダグラスは、自らの苦いトレード経験と多数のトレーダーの間接的な経験を踏まえて、トレードで成功できない原因とその克服策を提示している。最近では大手商品取引会社やブローカー向けに、本書で分析されたテーマやトレード手法に関するセミナーや勉強会を数多く主催している。著書に『規律とトレーダー』『ゾーン 最終章』、講演DVDに『「ゾーン」 プロトレーダー思考養成講座』がある。
シカゴのトレーダー育成機関であるトレーディング・ビヘイビアー・ダイナミクス社の社長を務める。商品取引のブローカーでもあったダグラスは、自らの苦いトレード経験と多数のトレーダーの間接的な経験を踏まえて、トレードで成功できない原因とその克服策を提示している。最近では大手商品取引会社やブローカー向けに、本書で分析されたテーマやトレード手法に関するセミナーや勉強会を数多く主催している。著書に『規律とトレーダー』『ゾーン 最終章』、講演DVDに『「ゾーン」 プロトレーダー思考養成講座』がある。
原題: Trading in the Zone
訳者/世良敬明氏(せら・たかあき)
1995年、明治大学政治経済学部政治学科卒。日経商品取引員の営業を経たのち、シカゴで翻訳・記者業務に従事。米国CTA(商品投資顧問業)の免許を持つ。
意識調査
本書の洞察は鋭く核心を突いている。第一〜三章で指摘されている敗者の条件は、まさに私自身がトレードで身をもって経験しており、「自分のことを言っているのではないか」と苦笑しつつ翻訳を進めたのを覚えている。もしこの感覚に同意していただけるのであれば、第四〜七章にある独創的な分析とトレードの真実に「なるほど」 と納得してもらえるのではないかと思う。
また第八〜一〇章には、その真実を完全に受け入れ、しかも機能させるためのノウ ハウが、詳細な解説とともに提示されている。その創造的かつ合理的な説明から、本当の意味での自己規律の有効性を認識していただきたい。そして第一一章には、それまでの理解を踏まえて、実際にどのように取り入れるかの筋道が提供されている。その内容は非常に実践的で、訳者本人も練習生の一人である。率直なところ現時点での 感想は「なかなか難しい」であるが、少なくとも自身の心理的弱点をはっきりと認識し、またトレードに対する考え方が非常に気楽になったのは確かである。
ダグラス氏の論理は、まず結論とキーワードを記してから、かなり遠くのほうへ話 題を飛ばし、少しずつ元に戻ってくるような展開をする。その距離が壮大なため、戸惑いを感じる方もいるかもしれない。正直な話、訳者本人が何度かそのような経験をした。しかし気にせずに読み進んでいただきたい。そうすればある時点で「なるほどそういう意味だったのか」と優れた推理小説を読んでいるかのように、急に目の前が明るく感じ、より深く氏の説にうなずいてもらえるだろう。
本書に流れる思想は、私たちの東洋思想とかなり相性が良いように思う。たとえば 八正道(正見、正思、正語、正業、正命、正精進、正念、正定)の観点から読むと、より容易に理解できるのではないだろうか。何度読んでも新しい発見がある。そしてその多くは生活全般にも役立つ情報である。本書が読者の方の一助になれば、訳者としてこれ以上の喜びはない。
訳出に当たっては、友人のナオミ・バーコブ氏にネイティブの視点から助言していただいた。辞書にない英語のニュアンスを解説していただくだけでなく、彼女と文意 について論じ合うなかで最適な日本語にひらめくケースが幾度となくあった。また株式会社ゼネックスの佐藤昌彦氏には、一読者の立場から原稿の不明瞭な点を指摘していただいた。本書が読みやすいものになっているとすれば、それは間違いなく両氏の優れた知性と協力のおかげである。この場を借りて厚くお礼を申し述べたい。ただし翻訳に関する全責任は、もちろん訳者の私にある。
翻訳の機会を与えていただいた益永研社長、成毛浩之専務をはじめMKニュース社 の先輩方にも感謝の気持ちを記しておきたい。研鑽を積む機会を提供してくれる仲間に、できるだけ良い仕事で報いたいと常に願っている。
最後に、本書の発行者である後藤康徳氏(パンローリング株式会社社長)、編集者の阿部達郎氏(FGI代表)に深く感謝したい。両氏の傑出した決断力と迅速な行動力が、日本の投資家たちにどれだけ貢献しているかは、今日のウィザードブックシリーズの充実を見れば明らかである。続きを読む
二〇〇二年一月
世良敬明
本書は氏がライフワークとして積み重ねてきた歳月、思考、研究の集大成であり、トレードをなりわいとする私たちにとってはまさに究極の書である。
本書では、トレードに挑む際に立ちはだかる数々の難問が徹底的に分析されている。「難問」というと、大半のトレーダーには利殖方法の研究しか思いつかないかもしれない。例えば典型的な初心者にありがちなのは、売買判断に裏情報や営業マンのアドバイスなど利用しても一貫した成績は残らないと悟り、「自分が信頼できる売買戦略を開発するか購入するかしかない」と理解するパターンだ。たしかにそうすれば金儲けができる。そしてトレードが楽になる「はず」だ。なぜなら売買戦略の規則に完全に従い「さえ」すればよいからだ。
ところがこのレベルになると、おそらくかつては意識していなかったようなことを実感し始める。トレードが、今まで直面した不快な体験のなかでも最もつらい体験の一つとなるのだ。そしてこの体験こそが、「先物トレーダーの九五%が一年で全資金を失う」という、よく引用される統計値の原因となっている。株式トレーダーにしても結果は基本的に同じだ。この体験が、「株式トレーダーの大半は、単純な買い保持 シナリオ以上の成績を残せない」と専門家に常に指摘される原因となっているのだ。
ではなぜ多くの人が、その大半はほかの職業では大きな成功を収めているというのに、トレードでは悲惨な結果に終わってしまうのだろうか。成功は天性のものでしかないというのか。その考えをマーク・ダグラスは否定する。そして「一個人がトレーダー的心構えを習得すべきなのだ」と主張している。ただしこれは言うは易いが行うは難しい。なぜならこうした心構えは、日常体験で刷り込まれた世界観とまったく相いれないからである。
氏の指摘によると、私たちが成長期に学んだ「生きる術」を日常生活でどのように用いているか考えてみれば、この「敗率九五%」を理解できるという。学校で好成績を取るため、キャリアを積むため、他人との関係を築くために学んだ術、そして日常生活を維持するためにすべきだと教え込まれた術が、トレードでは不適当だというのだ。トレーダーは確率の観点から思考する方法を身に着けなければならない。そして生活のほとんどあらゆる面で実行するように教えられた術を、すべて放棄する技量を身に着けねばならない。本書で、マーク・ダグラスがまさにその方法を教えてくれる。実に価値のある本に仕上げてくれた。氏の知識の源泉は、トレーダーとしての個人的経験、シカゴでのトレーダー教育の経験、トレード書の著者としての経験、トレード心理学分野での講演経験である。
さあ、ぜひ本書『Trading in the Zone』の素晴らしさを味わってほしい。そして実践し、トレーダー的心構えを養っていただきたい。
トム・ハートル
トレーダーならばだれしもが恒常的収益を目標としている。ところが、実際に一貫して利益を上げているトレーダーはほとんどいない。この現状を理解するにあたって、そのカギとなる根本的問題は何か。私に言わせれば、それは心理的要因にある。一貫して勝つ人間には、他人とは違った思考力があるのだ。
私がトレードを始めたのは一九七八年である。当時、ミシガン州デトロイト近郊で損害保険会社を経営していた。本業はいたって順調で、トレードでも簡単に同じくらいの成功を収められるだろうと思っていた。しかし残念ながら、そうはいかなかった。私は自分の結果にうんざりし、「ほかの仕事をしながらでは効率的にトレードはできない」と考え、八一年にシカゴに引っ越して、CBOT(シカゴ・ボード・オブ・トレード)のブローカーとしてメリルリンチ社に就職した。その結果どうなったか。そう、シカゴに引っ越してから九カ月もたたないうちに、ほとんどの財産を失ってしまったのである。無茶苦茶なトレードと生活スタイルで損失を出し、そのことがまたトレーダーとして多額の儲けを必要とし、さらにそこで損失を重ねる、という悪循環に陥ったのだ。
しかし、こうした初心者トレーダー時代に得た体験から、私は自分自身について非常に多くのことを学んだ。そしてついに悟ったのが、トレードにおける心理学の役割である。これが八二年に処女作『規律とトレーダー(The Disciplined Trader: Developing Winning Attitudes)』の執筆に取りかかった動機だ。
当初は文章にまとめること、つまりある程度自分で理解していることを説明し、他人に有益な形にまとめる作業がこれほど難しいものだとは夢にも思わなかった。六〜九カ月間で済むだろうと考えていた執筆作業に結局七年半を要し、九〇年にようやくプレンティス・ホール社から出版されたのである。
その間、八三年にメリルリンチ社を辞め、トレーディング・ビヘイバー・ダイナミクス社というコンサルティング会社を立ち上げた。現在では、そこでトレード心理学に関するセミナーの企画運営をしており、いわゆるトレードコーチの役割を担っている。世界中の投資会社、清算会社、ブローカー会社、銀行、投資カンファレンスでの講演活動を無数にこなし、個人レベルでもフロアトレーダー、ヘッジャー、オプションスペシャリスト、CTA(商品投資顧問)、そしてもちろん初心者といった多種多様なトレーダーたちの相談に乗ってきた。
本書はその一七年間の集大成であり、トレードの根底にある心理的力学の変化を徹底解剖している。それは成功者となる原理原則を効率的に教授しようとしてきたなかで痛感してきたことなのだが、最も根本的なレベルで私たちの考え方には問題があるのだ。私たちの心の作用のプロセスがマーケットの性格とうまく合致していないのである。
売買に自信のあるトレーダーは、自分を信頼し、自分のすべきことを躊躇なく実行する。これこそ成功するトレーダーだ。マーケットの気まぐれな値動きを恐れず、不安を助長するような情報に気を取られるよりも、収益機会を伝える情報に神経を集中させる能力を身に着けている。
今はまだ困惑するかもしれないが、本書から以下にまとめたことを信念として身に着けてほしい。①利益を出すために次に何が起こりそうか知る必要はない、②何事も起こり得る、③どの瞬間も唯一のものである――すなわちどの優位性の結果も唯一無二の経験である――。トレードにはうまくいくときもあれば、そうでないときもある。結果がどうであれ、次に現れる機会を待ち、手順どおりに何度も何度も繰り返す。このやり方を通さなければ、自分の方法論(非ランダム的な売買プロセス)が機能するか否か分からないのだ。そしてまたそのやり方を一貫させるためには、無限の可能性を持つ市場環境から精神的ダメージを負わないだけの自己信頼の確立が同じくらい重要になるのだ。
大半のトレーダーは、自分のトレードの問題点がその考え方、つまりトレード中の思考内容の結果であると信じようとはしない。前著では、トレーダーに立ちはだかる問題点を精神面から明確にし、その問題の本質と存在理由を理解するための哲学的枠組みの構築法を解説した。一方、本書で私が念頭に置いている主な目的は以下の五点だ。 ●マーケット分析を質量ともに向上させたとしても、トレードの難しさは解決できず、一貫した結果は残せないことを証明する。 (注 最近までトレーダーの大多数は男性であったが、女性トレーダーの数が増えているのも私は承知している。トレーダーを代名詞で指すときに便宜上「彼」を使っているが、これはけっして私の偏見を意味しているわけではない) 本書は、一貫した勝者となるために重大な意義を持つ心理的アプローチの提供を目的とするものであり、具体的な分析システムには一切触れられていない。私の関心は
収益性のあるトレーダーになるための必要な思考法の提示にある。読者の方には、すでに自分のシステム、優位性があると思う。ちなみに優位性とは、「もう一方よりも結果の出る可能性が高いもの」という意味である。自信がつけばつくほど、実際のトレードが楽になるだろう。本書の意図は、トレーダーが自分自身ですべき自己洞察と自己理解、そしてトレードの本質の解説にある。これらを理解して身に着ければ、単にマーケットを観察しているだけのときや、単にシミュレーションしているだけのときと同じぐらい、実践が単純明快で気楽なものになるはずだ。
まずは現状でどれだけ自分に「トレーダー的思考法」があるかを明確にするために、以下の意識調査に回答してもらいたい。答え合わせはしない。しかしその回答
は、現時点の自分の心の枠組みがトレードで最大限の利益を得るために必要な思考法とどれだけ一致しているか、はっきりさせてくれるはずだ。
マーク・ダグラス続きを読む
●自分の姿勢と「精神状態」がはっきり結果となって表れることを納得させる。
●勝利者の心構えを確立するために必要な具体的信念と姿勢について説明し、確率的思考法を教授する。
●実際はそうではないのに、一般のトレーダーが確率的に考えていると確信する原因となっているさまざまな葛藤、矛盾、逆説を扱う。
●この思考戦略を心のシステムに取り入れ、本当に機能させるまでの手順を解説する。
ファンダメンタル分析が売買判断の唯一無二の適切な手段であると考えられていた時代がいつごろであったか、ご存じだろうか。実際、私がトレードを始めた一九七八年当時、テクニカル分析は少数派であった。少なくとも大半の業界人にはバカにされていた。現在ではなかなか理解し難いことだが、ウォール街の主要なファンドマネジャーや機関投資家の大半がテクニカル分析を占いのようなものだとみなしていたのは、遠い昔の話ではないのだ。
もちろん今では、まったく逆だ。圧倒的大多数のベテラントレーダーが何かしらのテクニカル分析を用いて自分の売買戦略をまとめている。一方、「純然たる」ファンダメンタル分析者は、ちっぽけな象牙の塔にひきこもった学者連中以外、ほとんど消滅してしまった。では、両者の立場が劇的に逆転した原因は何であろうか。
答えは非常に簡単だ。お金である! 驚くまでもない。厳格なファンダメンタルの視点で売買判断を下すトレードでは、基本的に収益を出し続けることが難しいのだ。
ここでファンダメンタル分析についてよく分からないという読者のために少し解説しよう。ファンダメンタル分析とは、ある特定の株式、商品、金融商品について、その潜在需要と供給との均衡(不均衡)に変化を及ぼしそうな材料をすべて考慮しよう、というものである。さまざまな材料(金利、バランスシート、天候パターン、その他いろいろ)の意義に重点を置いた数理的モデルを利用して、分析者は価格が将来のある時期にどうなるかを予測するのである。
しかしこうしたモデルには問題点がある。材料としてほかのトレーダーを考慮していないのだ。価格を動かすのはモデルではない。将来に信念と期待を抱く人間だ。たとえ材料をすべて比較したうえでモデルが論理的に正当な予想をしたとしても、売買出来高に主体的な影響を持つトレーダーがそのモデルに気づかず、あるいはそれを信じようとしなければ、大した価値を持たないのである。
事実、価格に影響をもたらすと考えられるファンダメンタル的需給要因の概念を、実際に売買判断の中心に据えるトレーダーはほとんどいない。特に先物取引所にいるフロアトレーダーは、価格をかなり劇的に一方向から逆方向へと動かす力があるが、その売買活動の多くは、まったくファンダメンタルモデルの範疇にない感情的要素に対する反応によって拍車がかかる。つまりトレードをする人たち(そして結果的にその値動き)は、必ずしも論理的に動くわけではないのだ。
たとえ結果的にファンダメンタル分析者の「将来のある時点で価格がどこにあるか」という予想が正しかったとしても、その間に価格は大きく変動する。その目的を実現させるために建玉を維持するのは、不可能とは言わないまでもかなり難しいのだ。続きを読む
テクニカル分析は、マーケットが取引所に組み込まれたころから存在している。しかしトレーダーの世界では一九七〇年代末または八〇年代初期ごろまで、利殖の道具として価値があるとは考えられてはいなかった。しかし以下の理由から、現在では業界関係者の必修事項として主流を占めるようになっている。
どの日、どの週、どの月にかかわらず、マーケット参加者の数は有限である。そして彼らの多くが利殖を期待して、同じような行動を何度も繰り返す。つまり各個人に行動パターンがある。そしてその個人の集まりが、首尾一貫してお互いに影響し合うため、それが集団的行動パターンを形成する。こうした行動パターンは、視覚的にも数値的にも識別可能であり、その繰り返しには統計学的信頼性がある。
つまりテクニカル分析は、集団的行動をパターンとして識別し、「あることが起これば次にこうなる」という可能性がより高くなるタイミングを明確にする方法なのだ。ある意味、過去にマーケットで生じた何かしらのパターンを根拠にマーケットの気持ちを読み取り、次の展開を予想する方法であると言える。
将来の値動きを予測する手段として、テクニカル分析は純然たるファンダメンタル分析よりはるかに優れている。単に数理的モデルによる論理的正当性を根拠に、「マーケットがどうなるべきか」に注目するのではなく、テクニカルトレーダーは過去に起きたことと比較して「今現在」マーケットで起きていることに注目している。一方、ファンダメンタル分析では、「そうあるべき」と「今起こっていること」との間に「現実とのギャップ」と私が呼ぶ格差が生じてしまう。この「現実とのギャップ」が、たとえその分析が正解であっても、超長期的な予想以外での利用を難しくさせてしまうのである。
対照的に、テクニカル分析にはこうした「現実とのギャップ」がないだけではなく、トレーダーが優位性を手にする可能性を、ほぼ際限なく提供してくれる。分、日、週、年とどのような時間間隔でも、可能性のある行動パターンがどのようにして生じるか、はっきりと設定できるのだ。したがってテクニカル分析では、売買機会を絶え間なくふんだんに発見できるのである。続きを読む
テクニカル分析がそれほどうまく機能するならば、なぜマーケットのテクニカル分析から自分自身の心理分析、独自の売買哲学へと焦点を移すトレーダーが増えているのだろうか。その答えは、本書を買った理由を自分に問いかけてみれば分かるだろう。おそらく、テクニカル分析に無限の収益性があると分かっていながら、結局はそれほど儲かっていないという格差に不満があるからではないだろうか。
まさにそれこそがテクニカル分析の問題点である。パターン認識でマーケットを読む方法には無限の収益機会があると分かる。しかし知ってのとおり、マーケットについて理解した内容と、その知識を一貫した利益や堅調に上昇する損益曲線に反映させる能力との間には、大きな格差があるのだ。
例えばチャートを見て、「うーん。マーケットが上昇しそうだ(下落しそうだ)」と考え、そして実際にそのとおりになったものの、値動きを見る以外には何も行動できず、自分が手にできたであろう額に苦悩した経験が何度となくあったのではないだろうか。
何かがマーケットで起こるかもしれないという予測(そして稼げるかもしれない金額についての思惑)と、実際のトレードの建玉と仕切りという現実との間には、このように大きな格差がある。私はこの格差を「心理的ギャップ」と呼んでいる。そしてこれこそがトレードを最も困難な挑戦の一つにし、最も習得が難しい謎の一つとしているのである。
では、トレードは習得できるものであろうか。仮想トレードのような気軽さと単純さで、実際の建玉と仕切りは実行できるのであろうか。この根本的疑問に対する答えは、はっきりしている。「イエス」だ。そして本書の意図はまさにそこにある。自分について、そしてトレードの本質について、重大な洞察と理解を提供しようと思う。そうすれば、仮想トレードのような気軽さと単純さで、ストレスのないトレードを実行できるはずだ。
これを無理難題のように思う人もいるかもしれないし、不可能にさえ感じる人もいるかもしれない。しかしそうではない。実際、芸術的なトレードを習得した人は、可能性と現実との間にあるギャップをかなり埋めている。ただし、たしかにこうした勝者の数がごくわずかであるのも事実だ。大多数のトレーダーは、波のように激しい動揺や怒りを体験し、「なぜこれほどまでに一貫した成功を熱望しているのに確立できないのか」といった疑問を感じたまま終わっている。
実際のところ、この二つの集団(一貫した勝者たちとそうでない者たち)の差は、月と地球の差にたとえられるだろう。月と地球はどちらも同じ太陽系に属する天体である。その意味で共通点はある。しかし本質的・性質的に昼と夜のような違いがある。トレーダーでも同様だ。トレードを仕掛ければ、その人はトレーダーを名乗れる。しかし少数の一貫した勝者の性格と大多数の敗者の性格を比較したとき、そこにもまた昼と夜のような違いがあるのだ。
一貫して成功するトレーダーは月にたとえられる。月に達するのは可能だが、その旅はかなり困難で、達成できるのはごく限られた人たちだ。地球から見ると、月は基本的に毎晩観察できる。非常に近くにあるので、そこに手を伸ばせば届くかのように思えるほどだ。トレードも似た感覚だ。どの日、どの週、どの月でも、トレードを仕掛ける能力のある人であればだれでもマーケットに参加できる。そしてマーケットは絶えず動くため、損益もまた常に動く。したがって成功の可能性が限りなく広がっているように「見える」し、成功が掌中にあるかのように「見える」。
「見える」という言葉を使ったのは、この点が二つの集団を区別するのに重要だからである。実際に資金を掌中に入れ、ほとんど思いのままにしているのは、「一貫性への扉」と私が呼んでいるものを突破する方法を習得した、ほんのわずかな人たちだけなのだ。こう書くと、驚いて信じられない人もいるはずだが、これが真実である。限界はあるものの、資金の大半は難なくあっさりと、こうしたトレーダーの口座へと流れ込む。これが多くの人の感情を、文字どおり混乱させてしまうわけだ。
しかし、このような選ばれた集団に仲間入りしていないトレーダーには、「見える」という言葉が、まさにそのとおりの意味を持つ。あたかも自分が望む一貫した収益や究極の成功が「眼前に」、または「掌中に」あるかのように見える。しかし何度繰り返しても、それはちょうど目の前にある蜃気楼のように消えてしまうのだ。この集団で一貫しているのは唯一、精神的苦痛だけである。たしかに意気揚々とする瞬間があるが、ほとんどの時間は恐怖、怒り、欲求不満、不安、失望、裏切り、後悔の状態にある。これは誇張して述べているのではない。
それでは、何がトレーダーを二つの集団に区別してしまうのだろうか。知性だろうか。単に一貫した勝利者は他人よりも賢いだけなのだろうか。それとも一生懸命頑張るからだろうか。分析が優れているからだろうか。売買システムが優れているからだろうか。トレードの激しいプレッシャーを簡単に処理できる生まれつきの才能に恵まれているからだろうか。
こうした考え方は非常にもっともらしく聞こえるが、実際は違う。トレードで失敗している人の大多数が社会的に名の通った聡明な人たちである事実を考えてもらいたい。一貫して負け続ける人々の大半を占めているのは医者、弁護士、エンジニア、科学者、経営者、裕福な退職者、創業者なのだ。また業界最高レベルのマーケット分析者の大半が、思いつくかぎり最悪のトレードをしている。知性と優れた市場分析はたしかに成功に寄与する。しかし勝者とその他を明確に区別する要素ではないのだ。
では、知性や優れた分析ではないとしたら、何だというのか。
最高のトレーダーと最悪のトレーダーに分類される人たちとそれぞれ仕事をしてきた経験、また最悪のトレーダーが最高のトレーダーへと変身するのを教育してきた経験から、私は最高のトレーダーがその他を凌駕し続けている理由を特定できたと断言できる。その理由を簡単に言えば、「最高のトレーダーは他人とは違った考え方をする」からだ。
だから何だと思うかもしれない。しかしこの「違った考え方をする」には深い意味が込められている。たしかに、多かれ少なかれ、私たちは他人と違った考え方をする。しかし一方で、出来事の理解や解釈を他人と共有しているという前提を、当たり前だと思い込んでいる。この事実を私たちは必ずしも心に留めていない。実際、お互いに経験したものについて基本的・根本的に食い違っていると分かるまで、この前提を当然だと思い込んだままでいる。しかし身体的特徴だけでなく、考え方も人を個性的にする。むしろ身体的特徴よりもさらに個性的なのだ。
トレーダーに話を戻し、最高のトレーダーの思考法は、その他の苦戦している人たちの思考法と比べて何が違うのか考えてみよう。マーケットという闘技場は、各参加者に際限なく機会を提供する一方で、常につらく苦しい心理状態に直面させる。だれもがある段階で自分の分析方法を開発し、マーケットに売買機会が生じたタイミングを示す方法を習得するようになるが、だからといってトレーダーのように考える方法を習得できたわけではない。
一貫した成功者とその他を区別するはっきりとした特徴がそこにある。勝者はある種の心構え(独自の姿勢)を確立し、逆境にもかかわらず規律と集中力、そして何よりも自信を維持できるのだ。結果として、その他のトレーダー集団が悩むような一般的な恐怖や売買ミスに影響を受けずに済む。だれもが最終的にマーケットについて何かを学ぶが、一貫した勝者となるために絶対不可欠な姿勢を習得しているのは非常に限られた人たちなのだ。それはちょうどゴルフクラブやテニスラケットを振り、適当な技術をマスターしようと学ぶのはだれでもできるが、それを一貫できるか否かは、間違いなくその姿勢によるのと同じである。
「一貫性の扉」を突破した人は通常、マーケット環境に効果的に対応するそうした姿勢を身に着ける前に、大きな痛みを(感情的にも資金的にも)経験している。例外的にトレードの上手な家系に生まれた人や、トレードの本質を知り、また同様に重要なことだがその教授法を知っている人から教わってトレードを始める人もいるだろうが、その数はほんのわずかである。
なぜ精神的苦痛や経済的損害がトレーダーに共通しているのか。答えは簡単だ。ほとんどの人が、不幸にもトレードを始めるときに十分な指導を受けていないからである。しかしその理由を説明するのは非常に難しい。私はトレードの裏にある心理的力学を解剖し、成功の原理を教授する効果的な方法の開発に一七年を費やしている。そこで私が発見したのは、トレードが逆説と矛盾でぎっしり詰まっていることだ。それが成功法の習得を非常に難しくしてしまうのである。事実、トレードの本質をまとめた言葉を一つ選ばなければならないとすれば、「逆説」になるだろう(辞書によると、逆説とは矛盾した資質をもつもの、あるいは一般的信念や一般の人が理解しているものとは正反対のもの、という意味である)。
金銭的・精神的苦痛がトレーダーに共通するのは、日常生活ではまったく当然で、また非常によく機能する物の見方、姿勢、原理の多くがトレード環境ではまったく逆に作用するからである。つまりまったく機能しないのだ。これを理解せずに、大半の人々はトレードを始めてしまう。しかし彼らにはトレーダーになるという意味、必要な技量、そしてこうした技量を磨くのに必要なレベルについての理解が、根本的に欠けているのである。
分かりやすい例で説明しよう。本質的にトレードはリスキーだ。私の知るかぎり、結果が保証されたトレードはない。間違いや損失の可能性は常にある。ではトレードを仕掛けたとき、自分がリスクを負っていると考えられるだろうか。ひっかけ問題のように感じるかもしれないが、そうではない。
この問題に対する論理的回答は、絶対的に「イエス」だ。自分が本質的にリスクのある活動に従事しているのだから、「リスクテイカー」にならなければならない。これは完全に合理的な前提だ。事実、ほとんどすべてのトレーダーがそのように前提を置いているだけでなく、大半のトレーダーが「自分はリスクテイカーである」という考え方にプライドを持っている。
問題はこの前提が真実よりも深いレベルで受け止められていない点だ。もちろん、だれもがトレードを仕掛けるときにリスクを取っている。しかしだからといって、リスクを受け入れたわけではないのだ。すべてのトレードにリスクがある。なぜなら可能性に賭けているのであり、結果は保証されたものではないからだ。しかしトレード
を仕掛けるとき、自分がリスクを取っていると本当に分かっているだろうか。トレードが何の保証もない可能性に賭けているものであると、本当に受け止めているだろうか。そして可能性の結果を十分に受け入れているだろうか。
答えは明らかに「ノー」だ。大半のトレーダーは、成功者のようなリスクの考え方(リスクテイカーになる意味)をまったく分かっていない。最高のトレーダーはリスクを取るだけではない。リスクを許容する方法を習得しているのだ。トレードを仕掛けたからリスクテイカーになったという前提と、各トレードに内在するリスクをはっきりと許容する考え方には、心理的に大きなギャップがある。リスクを十分に許容して初めて、その成果が自分の運用成績に大きく表れるのだ。
最上級者は何のためらいも葛藤もなくトレードを仕掛ける。そしてトレードが機能しなくても、同じくらい何のためらいも葛藤もなく、容易にその事実を認める。たとえ含み損で手仕舞っても、不愉快な感情は微塵も見せない。つまりトレードに内在するリスクで、自分の規律、集中力、自信を失うことはないのである。裏を返せば、不愉快な気持ち(特に恐怖心)でトレードしているのであれば、トレードに内在するリスクを受け入れる方法を学んでいないことになる。これは大きな問題だ。なぜならリスクが許容できない度合いとリスクを避けようとする度合いは比例するからだ。そして避け難いものを避けようとする試みは、トレード成功させる能力に壊滅的な打撃をもたらすのだ。
どんなに努力しても、リスクを本当に甘受できるようになるのは難しい。特に何かを賭けているトレーダーにとっては非常に受け入れ難い。死ぬことや講演会への出演以外に、一般的に最も恐ろしいものを考えてほしい。損失と間違いは、両方ともそのリストの上位に位置するはずだ。したがって、間違いとそのうえに被った損を認めるのには、かなりの苦痛を感じる。たしかに避けたくなる。しかしトレーダーであるかぎり、これら二つの可能性には常に直面しているのだ。
すると、こう考える人もいるかもしれない。「激しい苦痛があるという事実は分かるが、何かを間違えたり失ったりしたくないのは当然だ。だからこそ、それを避けるためにできるかぎりのことをするのが適切ではないのか?」。そのとおりだ。しかし実はこの考え方によって、トレードを簡単にするように見えて、さらに難しくしてしまう行動を取る可能性が高いのだ。
トレードには「常に不透明な将来に直面しているなかで、どのように自己規律、集中力、自信を維持するか」という根本的な逆説が存在する。まさにそのことを達成するには、トレーダー的「思考」法を習得しなければならない。そのトレーダー的思考法のカギとなるのが、リスクを完璧に許容できるように自分の売買行動を再定義する方法の習得である。つまり、リスクを許容する方法の習得は売買技術の習得なのだ。これは習得可能な最も重要な技術だ。しかしその能力開発に注目し、時間を費やしてその習得に努力するトレーダーは滅多にいない。
リスク許容の技術を習得すれば、マーケットが発する情報に苦痛を感じることはない。マーケットが発する情報に精神的苦痛を受ける可能性がないならば、避ける必要がない。そしてマーケットが伝えている情報は何かしらの可能性に過ぎなくなる。いわゆる客観的観点である。この観点では、この先どうなるか分からないからといって、その不安感から偏見や屈折した解釈をすることはない。 このようなミスの経験がないだろうか。マーケットが実際にシグナルを出すかなり前にフライングしてトレードしてしまった。マーケットが実際にシグナルを出したかなり後で出遅れてトレードしてしまった。損切りの決心がつかず、結果としてより損が大きくなってしまった。あまりにも早計に勝ちトレードを手仕舞ってしまった。逆に勝ちトレードだったのに利益をすべて吐き出してしまった。さらにそのトレードを負けにしてしまった。建玉位置に逆指値が移動したために退場したものの、そのとたんにマーケットが自分の思惑の方向に反転した。これらは、トレーダーが何度も何度も繰り返す多くのミスのほんの一例でしかない。
しかし、これらはマーケットが生んだミスではない。こうしたミスはマーケットのせいではないのだ。マーケットは中立だ。マーケットは動き、情報を発している。値動きと情報は各個人に何かをする機会を提供する。しかしそれがすべてだ! マーケットにはこの情報を理解・解釈する各個人の方法を阻害したり、彼らが下した決断や行動を支配したりする力などない。ちなみに、ここで言及したミスとは「誤ったトレードの姿勢と解釈」と私が呼んでいるものの結果にほかならない。そして誤った姿勢は、信頼や自信ではなく、恐怖を助長してしまう。
私には一貫した勝利者とその他大勢との差が、「最高のトレーダーは恐れない」という点以外にあるとは思えない。事実、彼らは恐れない。自分の観点から、マーケットが可能性を伝えているという予測に基づいてトレードの建玉と仕切りを実行するために、かなり高度で柔軟な心理を持った姿勢を確立しているからだ。そして同時に、無謀なトレードを防ぐ姿勢を確立している。一方で、その他の人たちは多かれ少なかれ恐怖心を抱いている。あるいは怖いもの知らずから無謀になり、結局はそこから、さらなる恐怖をもたらすような経験のタネをまく可能性がある。
目の前からまさにお金が蒸発したかのような気持ちになる、犯しがちなミスのうちの九五%は、間違い、損失、機会喪失、利食い失敗に対する自分の姿勢から生じる。これらを私は、トレードの四大恐怖と呼んでいる。
そこでこう考える人がいるかもしれない。「よく分からない。トレーダーは常にマーケットに健全な恐れを持つべきではないだろうか?」。繰り返す。これは完全に論理的かつ合理的な考え方である。が、ことトレードでは、自分の恐れていたまさにそのことが実際に起きてしまった場合、恐怖心は自分にとって不利に作用する。また間違いを恐れていたら、その恐怖心はマーケット情報の解釈に悪影響をもたらす。そしてその場合、何かしらのミスを犯してしまう原因となるのだ。
恐れていると、ほかの可能性を思いつかなくなる。たとえ努めて理解しようとしても、ほかの可能性を解釈し、適切な対処ができなくなる。なぜなら恐怖で固まってしまうからである。身体的には金縛りや逃げ出す原因となる。そして精神的には恐怖の対象へ目が行き、視野が狭くなってしまう。つまり、ほかの可能性についての思考や、マーケットから提供されるほかの材料を遮断してしまう。恐怖心が消え失せるか、あるいはその出来事が終わるまで、マーケットについて学んだ論理的なことのすべてを考えたくなくなる。そして後の祭りとなってこう考えるのである。「自分はそれを知っていた。しかし、なぜそのときそう考えなかったのだろう?」、あるいは「なぜ自分はそのときに行動できなかったのだろう?」と。
これらの問題の根源が自分自身の不適当な姿勢であると解釈するのは非常に難しい。恐怖心が油断ならないのはそこだ。トレードに不利な影響をもたらす思考パターンの多くは、日常生活で見たり考えたりするために養われた自然な対応なのだ。こうした思考パターンがあまりにも深く根づいているため、トレードを困難にさせる根源が自分の内部にある精神状態から生じているとは、まずたいていの人には分からないのである。実際のところ、彼らが外部(マーケット)に問題の根源を探すのはごく自然に思える。なぜならマーケットが苦痛、苛立ち、不満をもたらしているように感じるからだ。
これらは明らかに抽象的で、そしてたしかに大半のトレーダーは気にしそうにもない概念だ。しかし信念、姿勢、解釈それぞれの理解は、テニスのサーブの仕方を学んだり、ゴルフクラブの振り方を学んだりするのと同じぐらい、トレードの根本なのである。つまり一貫した成果を残したければ、マーケット情報を自分がどう解釈するか、その理解とコントロールが重要となるのだ。
またその他にも、今述べた内容と同じくらい重要なトレードの真実がある。それは一回の勝ちトレードをつかむために、自分自身やマーケットについて何も知る必要がないということだ。ちょうどテニスラケットやゴルフクラブの適当な振り方を知らなくても、四六時中振っていれば良いショットが打てるのと同じだ。私が初めてゴルフをしたとき、特別な技術を何も学んでいなくても、ゲーム中、何回か良いショットを打った。しかし私のスコアは一八ホールで一二〇を超えていたのである。すなわち、私の全体的なスコアを改善するには、明らかに技術を習得する必要があったのだ。
もちろん、同じことがトレードにも当てはまる。総じて成功するには技術が必要だ。しかしどのような技術かが問題である。これは効果的に売買法を学ぶなかで最も難しい面の一つだ。いかにマーケット情報の解釈に自分の信念や姿勢が影響をもたらしているか認識していなければ、あたかもマーケット動向が一貫した収益を阻んでいるように見えるだろう。そのため損失を避ける最善の方法をマーケット分析だと思い込んでしまい、一貫した収益はよりマーケットについて学ぶことから生まれると考えてしまうのである。
この論理は完璧で理解しやすく思えるが、ほとんどすべてのトレーダーがある段階で陥るワナである。マーケットは、あまりにも多くの(そしてときには混乱するぐらいの)考え方を提供しているにすぎない。そして市場の動きを遮るものはない。いつでもどのようにでもなる。実際のところ、トレードしたい人はいつでもマーケットに参加できる。したがってどのトレーダーも何かを引き起こす当事者となる可能性があるのだ。
これはつまり市場動向についてどれだけ学ぼうと、どれだけ聡明な分析者になろうとも、すべてを予想する方法はけっして習得できないことを意味している。トレードに負けて、損をする可能性は常にあるのだ。したがって、もし負けて損をするのを恐れていたら、こうした恐怖心によるマイナスの影響を解消し、客観性と躊躇なき行動力を習得するのは無理である。すなわち、一貫した不透明性に立ち向かう自信がなくなるのだ。結果の不確実さは、トレードの冷たく厳しい現実である。この結果の不確実性を完全に受け入れる技量を習得しないかぎり、苦痛と認識したどのような可能性も、意識的・無意識的に避けようとするだろう。その揚げ句、何度も自らが犯したミスに見舞われ、高い代償を払う結果となるだろう。
ただし、売買機会を明確にし、それを発見するマーケット分析や売買手法がいらないと、私は言っているわけではない。たしかに必要だ。しかしマーケット分析は一貫した結果を残すカギとはならない。また自信の欠如、自己規律の欠如、不適当な視点で実行したトレードの問題を解決するものではない。
より多くの優れた分析が一貫した収益を生み出すという前提で行動すると、できるかぎり多くのマーケット材料を集め、自分の売買ツールの兵器庫に突っ込もうとしてしまうだろう。しかしそこから何が起こるか。マーケットに何度も繰り返し裏切られ、失望するのがオチだ。なぜなら、自分が見つけられなかったものや、十分に考慮していなかったものが常にあるからだ。そしてマーケットを信じられなくなるだろう。しかし現実には、自分を信用できなくなるのだ。
自信と恐怖は正反対の精神状態だが、両方とも信念と姿勢から生まれる。自分がリスクと考えている以上の損が容易に出やすい環境で成功するには、自分自身を完全に信用する必要がある。しかしその信頼感の確立には、一貫して成功するトレーダーの「自然とは逆の思考法」を身に着けなければならない。マーケット動向の分析法を習得したからといって、適切なトレードができるわけではないのだ。
つまりは二つの選択肢がある。一つは、できるかぎり多くのマーケット材料を研究してリスクを排除しようとするやり方だ。私はこれを分析のブラックホールと呼んでいる。なぜならそれは究極の不快感の入り口だからだ。もう一つは、自分が本当にリスクを受け入れたと言える方法で売買活動を再評価するやり方だ。そうすればもはや恐れるものはない。
本当にリスクを受け入れたという精神状態を確立すれば、苦痛を感じながらマーケット情報を定義・解釈する可能性はない。苦痛を感じながらマーケット情報を定義・解釈する可能性がなくなれば、自己正当化、躊躇、早まった行動、「マーケットが儲けさせてくれるだろう」とか、「マーケットが自分に損切りをする力がないのを助けてくれるだろう」といった希望的観測が排除できる。
理屈、自己正当化、躊躇、希望的観測、早まった行動から犯したミスに影響されやすいかぎり、自分で自分を信頼できなくなるだろう。客観的になれず、自分の行動を常に信頼できないのであれば、一貫した成績を残すのはほとんど不可能である。一見単純そうに見える試みに失敗したときほど、自分の行為のなかで最も腹が立つことはないだろう。皮肉にも、おそらく初心者のときに感じたようにトレードが簡単で単純なものとなるには、適当な姿勢で「トレーダー的心構え」を習得し、不透明なものに直面しても常に自信を維持できなくてはならないのだ。
その解決法は何か。まずトレードに適した姿勢と信念を習得する必要がある。そうすれば微塵の恐怖もなくトレードできる。しかし同時に、無謀になるのを防ぐため、枠組みを維持する。それこそがまさに本書の意義である。
本書を読み進むときに、留意してもらいたいことがある。自分の理想像は、自分で成長させなければならない自分の将来像である。成長とは鍛錬、習得、新しい自己表現の方法の確立を意味する。たとえ自分がすでに成功しているトレーダーで、さらなる成功のために本書を読んでいるとしても同じだ。本書で新しく学んだ自己表現方法の多くは、現在自分が抱いているトレードの本質についての思想や信念と、まったく相いれないかもしれない。あるいはすでにこうした信念の幾つかに気がついているかもしれないし、そうではないかもしれない。いずれにせよ、トレードの本質について現在自分が真実だと思っているものが、たとえ苛立ちや不満足な結果であるにせよ、それが自分の現状を形成しているのだと論じていくつもりだ。
このように、論点が内面的になるのは当然である。本書ではこうした論点をできるだけ効率的に解説したいと思う。そしてぜひ、ほかの可能性の存在を前向きに受け止めてほしい。今まで気がつかなかったかもしれない、あるいは十分に考えたことがなかったかもしれない可能性だ。そうすれば間違いなく習熟過程はより早くより楽になるはずだ。
続きを読む
◎「日経マネー」2009年10月号(日経BP社)太田忠様の「転機の1冊」として掲載されました。
◎FXデイトレーダーZEROのデイトレブログ
様に本書をお薦めいただきました。( 2009.08.26 )◎MayuhimeのFX検証記録 様に本書をお薦めいただきました。( 2009.08.18 )
◎『プロ相場師の思考術』(高田智也著、PHP研究所)の中でお薦めいただきました。
◎「日経ヴェリタス」2008年10月6日付 62面の「インデックス運用に勝つ 秋の夜長にお薦め投資本」に本書が「投資の心得を身につける5冊」として掲載されました。
◎『億万長者トレーダーが薦める名作・傑作!投資本30』(扶桑社刊)の中で、本書が推薦されました。