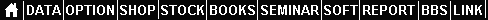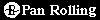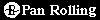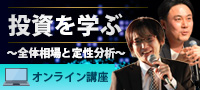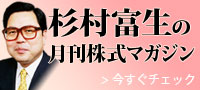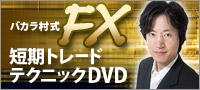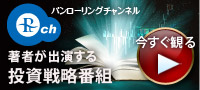|
ETFブログ −世界鏡−
|
ETF投資家は有効な逆張り指標? 04月26日
少し前になりますが、米国のTrimTabs Investment Researchという会社が「Using Equity ETF Flows as a Contrary Leading Indicator」というレポートを出していました。日本語にすれば「株式ETFへの資金流出入を逆張り指標に使う」でしょうか。
レポートによると、2000年1月から現時点までの一ヶ月間の株式ETFへの資金流入量とその一ヶ月後のS&P500のリターンの関係を分析すると逆相関がみられ、回帰モデルの回帰係数は統計的に有意となるそうです。計測期間を二ヵ月、三ヵ月と広げても同様に結果がみられます。一方でショート型株式ETFを対象に分析を行ったところ、今度は正の相関がみられたようです。
(とは言え、回帰モデルの決定係数は0.28程度であり、観測データ数が増えれば回帰係数が統計的有意になりやすいということもありますので、分析に使った回帰モデルが事象をよく捉えていると言えるかどうかは慎重にみた方が良さそうですが。)
そこで株式ETFへの資金流入が過去平均を上回れば株式をショートし、下回れば株式をロングする投資戦略を構築してバックテストをしてみたところ、平均値の計算期間の設定によってパフォーマンスに違いはあるものの、どの設定を採用してもS&P500のリターンを上回るパフォーマンスを記録したようです。例えば平均値を44日間で計算したモデルでは約10年間でS&P500指数を270%近く上回るリターンになったと報告されています。
ちなみにETF資金流入量とS&P500指数のリターンの逆相関の原因として二つ挙げられています。一つはETFの投資家がいわゆる洗練されていない個人投資家だからというもので、もう一つはヘッジファンドが市場流動性が枯渇を懸念したときにETFを利用するからだそうです。
個人投資家の投資選択肢拡大に貢献するはずのETFがうまく活用されていないとしたら何とも切ない話ですが、日本市場でも同様の現象がみられるのか分析してみる価値はありそうです。
コメント投稿
効率的に研究開発投資を行う企業は配当額の増加が鈍い? 04月20日
前回は企業の配当成長率と外部株主との関係を分析した論文の内容を紹介しましたが、今回も企業配当に着目した研究を採り上げたいと思います(と言いますか、自分の研究の参考にしたのでついでに採り上げてみました)。論文は証券アナリストジャーナル2009年8月号「企業の特殊性資産と配当政策の粘着性」で、前回のコラムの最後に付記したものです。
論文の内容は、特殊性資産と配当政策の関係を分析しフリーキャッシュフロー仮説を批判を展開したものです。特殊性資産とは経営者の能力や従業員の技術や知識などの人的資産に基づいて蓄積された無形資産のことです。特殊性資産を効率的に用いている企業では利益を配当として支払うよりも社内に再投資した方が結果的に企業価値の向上に資するため、株主も一定額以上の配当支払いを要求することはなく、よって企業のキャッシュの蓄積に対する配当の感応度が低下すると当論文は主張します。そして特殊性資産が効率的に利益を生んでいるかの指標として経営開発効率という指標を導入し、研究開発効率が高いとキャッシュの蓄積と配当成長率の関係性が薄れることを実証しています。
私も当論文を参考に同じような手法でデータを収集し分析をしてみました。確かに同様の結果が得られましたが、もう少し詳しく分析してみたところ研究開発効率がとても低い企業でもキャッシュの蓄積と配当成長率の感応度が薄いことが分かりました。そこで業種ごとに当該値の平均を算出してみました。以下は研究効率の高い業種と低い業種のトップ5をそれぞれ取り出したものです。
【研究開発効率の高い業種】
1.海運業
2.電気・ガス業
3.陸運業
4.鉄鋼
5.不動産業
【研究開発効率の低い業種】
1.医薬品
2.ゴム製品
3.精密機器
4.化学
5.輸送用機器
この結果をみてみると、研究開発効率の高い業種はそもそも研究開発費が少なそうな業種ばかりです。一方、研究開発効率の低い業種は研究開発に多額の資金を投入している企業が多そうです。配当成長率をみてみると研究開発効率の上位5業種の平均値と下位5業種の平均値はほぼ同じです。こうした結果からすると、もしかしたら経営開発効率という指標の算出方法にさらなる工夫が必要なのかもしれません。
配当に注目して業種別ETF等を選ぶ際の参考指標に研究開発高率が使えればと思ったのですが、なかなかどうして一筋縄ではいかないもののようです。
コメント投稿
外国人投資家と配当 04月15日
大学院の先輩にあたる方の配当に関する博士論文を読みました。論文は従来のフリーキャッシュフロー仮説により展開されてきた「配当を増やせば企業価値が高まる」という関係を幾つかの視点から批判的に検証したものです。
論文のある章では、企業を純粋な投資対象として認識する外部株主の割合が高いと利益と配当総額の連動性が弱まるという点が実証されています。外部株主は優れた経営者に会社経営を任せることで企業価値が高まり株価が上昇することによって便益を得ることが出来るため、投資リスクに対する見返りとして一定の配当を受け取ることが出来ればそれ以上は経営に介入することはないというのです。そのことが利益と配当額の連動性に現れるそうです。
この外部株主の代替変数として外国人株主が用いられています。外国人株主が多ければ増配要求が高まり、企業の利益増に合わせて配当額も増加するものだと私は先入観を持っていましたが、どうもそうではないようです。こうした思い込みは一部のアクティビスト投資家により植え付けられたものなんでしょうか。外国人株主が多ければ配当額が急増するはずだと期待して投資をすると期待外れに終わるかもしれません。
ただ論文の主旨からは外れますが、全体のサンプルと外国人株主の多い企業のサンプルの調査期間中の利益成長率の平均値を比較してみると、全体サンプルではマイナスとなっていましたが外国人株主が多い企業のサンプルではプラスとなっていました。さすがに外国人株主は成長期待が高い企業をしっかり選んでいるようです。この点では外国人株主の多さを投資対象選びのひとつの視点に加えることもあながち間違いとは言えなそうです。
ともあれ、思い込みを見直すきっかけを与えてくれる、ためになる論文でした。博士論文は大学の図書館に行かないと読めませんが、論文の一部は証券アナリストジャーナル2009年8月号「企業の特殊性資産と配当政策の粘着性」に掲載されています。
コメント投稿
米国経済のリバランシング 04月07日
今週号の「The Economist」のスペシャルレポートはアメリカ経済の回復とリバランシングについてでした。このところ楽観的な見方が増えつつある米国経済の回復を促している原動力が何かや、リセッション前の米国の借金依存体質がどのように変わっていくと期待されるかを滔々と説明しています。
レポートの気になった箇所を一部抜き出してまとめると、米景気が回復していると言っても住宅投資や信用供与の状況がリセッション前の水準まで戻ることはないとみられます。個人消費の急増を支えた住宅価格の上昇や金融機関のルーズな貸出態度は期待できず消費の拡大が見込みがたい状況で米経済を引っ張っていくとみられるのは輸出です。特に高品質の製品やサービスの輸出です。輸出先としては新興国の重要性が一段と高まっており、1990年には全体に占める新興国向け輸出の割合が30%程度だったものが2007年には50%以上を占めるまでに拡大しています。輸出の拡大により経常赤字が縮小することも米国の借金依存を和らげる要素とみられます。
投資する際に気を付けたいのは、米国企業の中で輸出を行っている企業の割合は4%程度、製造業だけでみても15%程度にとどまるという点です。取引先企業等への波及効果もあるでしょうが、輸出拡大が米国経済全体を押し上げるのかと言われると心許ない数値です。
米国経済の回復にかけて米国に投資する場合はうまく輸出関連企業をピックアップする必要がありそうです。そしてこれまで以上に新興国の経済状況にも目を配っていく必要があります。もちろんEconomist誌の指摘が正しいかどうか自分なりに確認することがまず先ですが。
コメント投稿
↑ページのトップへ
|
|
|
|