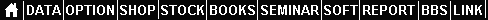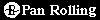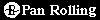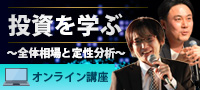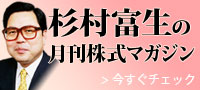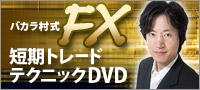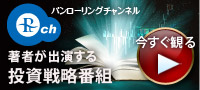|
「生涯現役のトレード日記」
|
短期筋買い⇔長期筋売り:持続的な上昇は期待薄 09月30日
昨日の米国株式相場は続伸した(DJIA +110.94 @18,39.24, NASDAQ +12.84 @5,318.55)。ドル円為替レートは101円台半ばの円安方向へ動いた。本日の日本株全般は反発した。東証1部では、上昇銘柄数が1,370に対して、下落銘柄数は521となった。騰落レシオは121.77%となった。東証1部の売買代金は1兆8789億円と、また2兆円の大台を割り込んだ。薄商いでの反発は裏付けが乏しい。
TOPIX +12 @1,343
日経平均 +228円 @16,694円
TOPIXも日経平均も反発した。予想外にOPECが減産合意(28日、加盟14カ国の原油生産量を日量3250万~3300万バレルに制限する)に至り、9月28日の米原油先物相場が急伸した。OPECが減産するのは金融危機後の2008年以来、約8年ぶり。28日のニューヨーク原油先物市場ではWTI期近11月物が前日比5.3%高の1バレル47.05ドルで終えた。また、円安・ドル高傾向も支援材料となり、資源関連株や輸出関連株など幅広く買われた。原油価格上昇は長い目でみれば日本経済には逆風だが、今日のところは買い材料となった。
http://chartpark.com/wti.html
しかし、取引の主体はあくまで短期筋であり、腰の据わった長期資金は入っていない。売買代金ランキングの1位は、日経平均株価の2倍の値動きをする「NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(日経レバ)」であり、値動きの大きさに着目する短期筋が好むETFだ。対照的に、対外及び対内証券売買契約などの状況を見ると、海外投資家は9月18日~24日に日本株を2117億円売り越しており、売却超は3週連続である。
https://www.mof.go.jp/international_policy/reference/itn_transactions_in_securities/week.pdf
短期筋主導で株式相場は上げたが、長期投資の海外投資家は売り続けているという構図では持続的な上昇は期待しづらい。
33業種中28業種が上げた。上昇率トップ5は、鉱業(1位)、鉄鋼(2位)、石油・石炭(3位)、非鉄・金属(4位)、証券(5位)となった。
コメント投稿
官製相場の限界 09月28日
昨日の米国株式相場は反発した(DJIA +133.47 @18,288.30, NASDAQ +48.22 @5,305.71)。ドル円為替レートは100円台半ばの円高方向へ動き、これを嫌気して本日の日本株全般は下げた。東証1部では、上昇銘柄数が556に対して、下落銘柄数は1,223となった。騰落レシオは114.60%。東証1部の売買代金は1兆8211億円。
TOPIX -18 @1,331
日経平均 -219円 @16,465円
TOPIXも日経平均も反落した。日経平均は9月末配当の権利落ち分(114円)を差し引くと、実質的に105円下げたことになる。日銀が新たな金融政策の枠組みを発表する前日の20日終値(16,492円)を下回った。株式市場と債券市場の両方をコントロールしようとする日銀の政策効果は、わずか4営業日で終わったことになる。
日銀は長期金利をゼロ%程度に誘導するという金融政策を打ち出した。しかし、債券市場で長期金利の指標となる新発10年物国債利回りはおよそ1カ月ぶりの低水準に下落し、銀行の利ざや縮小の懸念が再燃した。また、米司法省との間で巨額の和解金支払い交渉が難航していると伝わったドイツ銀行に続き、コメルツ銀行も9000人の人員削減と配当停止を検討していると伝わった。欧州発の金融システム不安が拡大する兆候を示している。その結果、保険業と銀行業が大きく売られた。日銀が長期金利をコントロールするのは現実的には難しく、株式市場に加えて長期金利まで制御しようとする官製相場の限界と言える。
33業種中、水産・農林、ゴム製品、食料品を除く30業種が下げた。下落率トップ5は、証券(1位)、保険(2位)、銀行(3位)、その他金融(4位)、海運(5位)となった。
コメント投稿
反発を強く示唆している 09月27日
昨日の米国株式相場は大幅下落した(DJIA -166.62 @18,094.83, NASDAQ -48.26 @5,257.49)。ドル円為替レートは100円台後半の円安方向へ動いた。本日の日本株全般は反発した。東証1部では、上昇銘柄数が1,557に対して、下落銘柄数は315となった。騰落レシオは123.06%。東証1部の売買代金は2兆2946億円。
TOPIX +13 @1,349
日経平均 +139円 @16,684円
朝方はドイツ銀行の公的支援を巡る海外株安が嫌気されて大きく下放れて始まり、日経平均は朝方に250円強下げ、その後上昇に転じる荒っぽい値動きとなった。前日のドイツ銀行株急落と、日本時間午前10時から始まった米大統領選の第1回テレビ討論会という海外要因が値動きを荒くした。日経平均は安く始まったが切り返して、前日の陰線の実体部分奥深くに切り込む「切り込み線」となった。TOPIXは前日の陰線を本日の陽線が包む「包み線」となった。いずれも反発を強く示唆している。
9月27日は9月期末を控え配当狙いの買いが入る最終日だった。テレビ討論会を無難に通過したとの見方から配当取りを意識した買いが入るようになった。
33業種中証券と銀行を除く31業種が上げた。上昇率トップ5は、鉱業(1位)、非鉄金属(2位)、石油・石炭(3位)、水産・農林(4位)、電気・水道(5位)となった。
コメント投稿
日米の金融政策会合が終わり材料不足の中・・・ 09月26日
先週金曜日の米国株式相場は下げた(DJIA -131.01 @18,261.45, NASDAQ -33.78 @5,305.75)。ドル円為替レートは100円台後半の推移。本日の日本株全般は続落した。東証1部では、上昇銘柄数が527に対して、下落銘柄数は1,326となった。騰落レシオは117.37%。東証1部の売買代金は1兆6944億円と薄商いだった。
TOPIX -14 @1,336
日経平均 -209円 @16,545円
米国株式相場や原油先物相場が下落し、幅広い銘柄に売りが出て、TOPIXも日経平均も続落した。円相場が1ドル=100円台後半の円高方向に動いたのも重荷となり、主力の輸出関連株は軒並み安となった。市場が最大の関心を寄せていた日銀とFRBの金融政策会合が終わり、新たな材料に乏しい。次の大きな関心事は11月の米大統領選と円高リスクだ。9月末は企業の中間決算を控え、輸出企業のドル売り・円買いが出やすいので、今週は輸出企業など実需の円買いが増加する。
本日後場には日銀の黒田東彦総裁が講演で、今後の追加緩和について「マイナス金利の深掘りと長期金利操作目標の引き下げが中心手段になる」と述べた。このため、金利低下懸念から銀行株への売り圧力が強まり、相場全体の地合いを一段と冷やした。さらに、ドイツ銀行株の安値更新が世界中の銀行株の重しとなっている。米司法省から巨額の和解金を求められているドイツ銀行を巡り、メルケル独首相が公的支援に否定的だと伝わった。9月26日の欧州市場でドイツ銀株は1999年のユーロ発足以来の最安値を更新した。世界的に銀行株への売りが波及することは必至だろう。
医薬品と繊維製品を除き、33業種中31業種が下げた。下落率トップ5は、保険(1位)、鉱業(2位)、空運(3位)、海運(4位)、銀行(5位)となった。
コメント投稿
FRB高官のメッセージに振り回されている 09月13日
昨日の米国株式相場は大きく反発した(DJIA +239.62 @18,325.07, NASDAQ +85.98 @5,211.89)。ドル円為替レートは101円台後半の円高方向へ動いた。本日の日本株全般は高安まちまちとなった。東証1部では、上昇銘柄数が940に対して、下落銘柄数は862となった。 騰落レシオは102.06%となった。東証1部の売買代金は1兆6666億円と薄商いだった。
TOPIX ±0 @1,323
日経平均 +56円 @16,729円
米国株は大幅反発したが、TOPIXはほぼ変わらず、日経平均は小幅反発であった。昨日、10日&25日移動平均線を割り込み、時の利は売りとなった。しかし、6月24日を起点とする上昇トレンドラインはまだ崩れていない。
昨日の米国株の反発は、利上げに消極的な「ハト派」で知られるブレイナードFRB理事が9月12日の講演で「防衛的な利上げを迫られる状況にない」と述べたことが背景にある。これによりFRBの早期利上げ観測が後退している。早期利上げが遠のいたので、9月13日の東京市場で円相場は一時、1ドル=101円台半ばまで上昇した。ただ、利上げの時期が延びれば、為替の円高・ドル安につながり、日本の輸出関連株には逆風となり、日本株の上値も重くなる可能性がある。
最近はFRBから発せられるメッセージに市場は振り回されている。9月9日には景気重視の「ハト派」であるはずのボストン連銀のローゼングレン総裁が講演で早期利上げに賛同する発言をして米市場が大荒れになった。しかし、今度は9月12日に同じく「ハト派」のブレイナードFRB理事が慎重意見を述べて、市場は胸をなでおろして落ち着いた。だが、9月20~21日のFOMCまで、FRBはブラックアウト期間に入るため、FOMC開始日の7日前の米東部時間夜12時以降、FOMC参加者は金融政策などの考えを公言できなくなる。その分だけ株価材料は少なくなる。
33業種中17業種が上げた。上昇率トップ5は、医薬品(1位)、ゴム製品(2位)、食料品(3位)、精密機器(4位)、石油・石炭(5位)となった。
コメント投稿
世界的な金融緩和の持続性に対する疑念が・・・ 09月12日
先週金曜日の米国株式相場は大幅下落した(DJIA -394.46 @18,085.45, NASDAQ -133.58 @5,125.91)。ドル円為替レートは102円台半ばでの推移。本日の日本株全般は大きく下げた。東証1部では、上昇銘柄数は282に対して、下落銘柄数は1,599となった。騰落レシオは105.72%。東証1部の売買代金は1兆7913億円。
TOPIX -21 @1,323
日経平均 -293円 @16,673円
欧米で金融政策が徐々に引き締め方向に向かうとの見方が強まり、米ダウ平均が400ドル近い大幅安となったのを嫌気して、TOPIXも日経平均も前場寄り付きから大きく下げた。欧州ではECB理事会が9月8日、量的金融緩和の延長を見送り、米国では金融緩和に積極的と言われるボストン連銀のローゼングレン総裁が「利上げが遅れれば、資産価格などが急落しかねない」などと発言したため、「利上げに積極的」との受け止め方が広がった。これにより米利上げ観測が高まり、世界的な金融緩和の持続性に対する疑念が強まり、株売りへとつながった。欧米が金融緩和から引き締め方向へ、日本が金融緩和を続けるとすれば、為替は円安方向へ動きやすい。これは日本株にはプラスに働く。他方、世界的な緩和マネーの縮小が日本株に与えるマイナスの影響もある。今日のところは後者の悪影響の方が勝った。
33業種すべてが下げた。しかし、意外な粘り腰を見せたのが保険株、下落率が一番低かった。下落率トップ5は、鉱業(1位)、鉄鋼(2位)、その他金融(3位)、非鉄金属(4位)、海運(5位)となった。
コメント投稿
やはり日経平均17,000円の壁は分厚い 09月09日
昨日の米国株式相場は下げた(DJIA -46.23 @18,479.91, NASDAQ -24.44 @5,259.48)。ドル円為替レートは102円台前半の円安方向へ動いた。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証1部では、上昇銘柄数が739に対して、下落銘柄数は1,082となった。騰落レシオは109.09%。東証1部の売買代金は2兆1662億円。
TOPIX -2 @1,344
日経平均 +7円 @16,966円
TOPIXは小安く、日経平均は小高く引けたが、材料難で動けなかったと言った方が適切だろう。円安進行を受けて買い優勢で始まったものの、1万7000円台を維持したのは一瞬だった。パラパラと出る利益確定売りに押され、下げに転じた。明確な材料が無い中、このところ日々の値動きも小さく1万7000円の成層圏のような壁を振り切れない。やはり17,000円の壁は分厚い。東証1部の売買代金は概算で2兆1662億円と、SQ算出日の割に薄商いだった。9月20~21日にかけて予定される日銀の金融政策決定会合とFOMCを控え、相場はまだまだ膠着状態が続きそうだ。
東京証券取引所が9月8日発表した8月29日~9月2日の投資部門別株式売買動向によれば、海外投資家は2週ぶりに売り越した。この週の日経平均は564円(3.5%)上昇していたにもかかわらず、順張りが中心とされる海外勢は売っていた。外国人投資家の年初からの累計売越額も5兆円を超える。この週は個人投資家も3週ぶりに売り越した。日経平均が心理的節目の1万7000円に近づき利益確定売りを出したと思われる。
http://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/investor-type/nlsgeu000001x0f7-att/stock_val_1_160805.pdf
33業種中20業種が上げた。上昇率トップ5は、海運(1位)、鉱業(2位)、空運(3位)、証券(4位)、非鉄金属(5位)となった。この9月2日以来原油価格が反発基調なので、鉱業が上げている。
http://chartpark.com/wti.html
また、バルチック海運指数は2月中旬に底打ちし、最近は年初来高値を更新しているので、海運株が買われている。
https://www.bloomberg.co.jp/quote/BDIY:IND
コメント投稿
材料難で小動き 09月08日
昨日の米国株式相場は高安まちまちだった(DJIA -11.98 @18,526.14, NASDAQ +8.02 @5,283.93)。ドル円為替レートは101円台半ばの推移。本日の日本株全般は高安まちまちだった。東証1部では、上昇銘柄数が860に対して、下落銘柄数が923となった。騰落レシオは112.87%。東証1部の売買代金は2兆1925億円。
TOPIX -4 @1,346
日経平均 -54円 @16,959円
TOPIXも日経平均も小幅安となった。米国株も円相場も小動きで材料難から方向感を欠いた展開だった。上から順番にそれぞれ上向きの10日、25日、60日の移動平均線の上に株価はあり、株価サイクルは③(着実な上昇)となっている。日銀の中曽宏副総裁が都内で講演し、「マイナス金利の深掘りはできないという考えはない」などと述べたため、一時は銀行株を中心に売られた。しかし、従来の日銀の立場と変更はないとの見方からその後は買いが入った。
33業種中21業種が下げた。下落率トップ5は、保険(1位)、鉄鋼(2位)、サービス(3位)、電気・ガス(4位)、水産・農林(5位)となった。
コメント投稿
急な円高進行でも楽観的な株式市場 09月07日
昨日の米国株は上昇した(DJIA +46.16 @18,538.12, NASDAQ +26.01 @5,275.91)。ドル円為替レートは101円台半ばの円高方向へ振れた。本日の日本株全般は上昇する銘柄の方が多かったが株価指数や下げた。東証1部では、上昇銘柄数が1,054に対して、下落銘柄数は746となった。騰落レシオは105.60%。東証1部の売買代金は2兆1267億円。
TOPIX -3 @1,350
日経平均 -70 @17,012円
急に円高が進み、これを嫌気してTOPIXも日経平均も下げた。米サプライマネジメント協会(ISM)が9月6日に発表した8月の非製造業景況感指数が6年半ぶりの低水準に落ち込んだことで、FRBの早期利上げ観測が再び後退した。その結果、日米金利差の縮小を見込んで円買い・ドル売りが優勢となった。トヨタやパナソニックなど主力株に売られる、一方、これまで売り込まれていた内需関連株や小型株が買い戻され相場を下支えした。
円相場が101円台まで急進した割には株価の下げ幅は小さいと言える。米経済の安定成長や世界的な低金利といったマクロ環境に加えて、日銀のETF買いという需給要因が下値を支えると期待されているからだ。株価指数オプション市場の動向から判断しても、投資家は比較的先行きに楽観的である。10月物の日経平均オプションは権利行使価格1万6000円台のプットより1万7500円や1万8000円のコールの建玉が膨らんでおり、この点からも株価は下がるよりも上がると見る向きが多いと言える。
http://svc.qri.jp/jpx/nkopm/
33業種中19業種が下げた。下落率トップ5は、保険(1位)、銀行(2位)、パルプ・紙(3位)、海運(4位)、証券(5位)となった。
コメント投稿
節目を回復した割に売買代金が非常に少なく薄商い 09月05日
先週金曜日の米国株式相場は上昇した(DJIA +72.66 @18,491.69, NASDAQ +22.69 @5,249.90)。ドル円為替レートは前場の104円台から、後場には103円台前半の円高方向へ動いた。本日の日本株全般は上昇数銘柄が多かった。東証1部では、上昇銘柄数が1,098に対して、下落銘柄数は702となった。騰落レシオは90.84%となった。東証1部の売買代金は1兆7400億円と、2兆円を大幅に割り込んだ。
TOPIX +3 @1,344
日経平均 +112円 @17,038円
TOPIXも日経平均も上昇した。米労働省が8月2日発表した8月の雇用統計で雇用者数の伸びは市場予想を下回ったが(非農業部門の雇用者数は前月から15万1000人増)、年内の米追加利上げを意識した円売り・ドル買いが優勢となった。円相場は一時、1ドル=104円台に下落した。これを好感して、日経平均は約3カ月ぶりに1万7000円台を回復した。投資家心理の改善で商社などの景気敏感株に買いが入った。8月から続く景気敏感株の買い戻しは銀行株や自動車株が先行していたが、本日、一段と上昇したのは海運株や鉱業株だった。
日経平均が17,000円という節目を回復した割に、売買代金が非常に少なく薄商いである。外国人の参加が少ないことと、日銀の金融政策決定会合と総括的検証という目先の最大のイベントが残っているためだ。市場は金融政策の限界を強く懸念している。日銀が動けば材料出尽くし、動かなければもう打つ手がない、とどちらにせよ悪く解釈されかねない。円安基調も一時的かもしれない。これまで積み上がっていた円買い持ち高の解消が雇用統計の発表という節目をきっかけに一気に進んだだけという指摘もあるからだ。
しかし、大きく崩れることもなさそうである、9月以降、日銀のETF買いが加速すると予測されるからだ。8月は4回しか買い出動しなかったので、年間6兆円購入するためには、ここから買いペースを上げる必要があるからだ。しかし、問題がある。ETF買いにより日銀による実質的な株式保有割合が高まっていることだ。その結果、市場に出回る浮動株が減っている。GPIFと合わせた「公的マネー」は、東証1部上場企業の4社に1社の実質的な筆頭株主となっている。日銀のETF買いという官製相場の色合いが濃くなるほど、市場参加者が減少して薄商いとなり、長期的な副作用が強まる。株式の流通量が減れば、わずかな売り買いで値が飛んでしまうので、フェアバリューへの回帰を前提に利益を狙うヘッジファンドにとっては、運用リスクが高まり、結局、日本株を敬遠することにつながる。その結果が薄商いである。
33業種中25業種が上げた。上昇率トップ5は、海運(1位)、電気・ガス(2位)、鉱業(3位)、卸売り(4位)、石油・石炭(5位)となった。
コメント投稿
株価サイクル②(着実な上昇を試す)の局面だが注意点もあり 09月01日
昨日の米国株式相場は続落した(DJIA -53.42 @18,400.88, NASDA -9.77 @5,213.22)。ドル円為替レートは103円台前半の円安方向で推移した。本日の日本株全般は上昇した。東証1部では、上昇銘柄数が1,182に対して、下落銘柄数は656となった。騰落レシオは89.78%。東証1部の売買代金は1兆9541億円へ減少し、再び2兆円の大台を割り込んだ。
TOPIX +8 @1,337
日経平均 +39円 @16,927円
米国株は続落したが、円相場が103円台前半の円安基調が続き、輸出関連株を中心に買いが優勢となった。TOPIXも日経平均も小幅続伸した。ただ、9月2日発表の8月の米雇用統計を見極めたいとの雰囲気が次第に強まり、後場は相場の膠着感が強まった。8月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI)が前月から改善し、中国の景気減速への懸念が和らいだのも日本株には追い風となった。
日経平均のチャートを見ると、10日及び25日移動平均線は収斂して徐々に上向きになってきており、まだやや下向きの60日移動平均線の遥か上にある。株価サイクル②(着実な上昇を試す)の局面である。ただし、250日移動平均線が下向きなので戻り売りが出やすい。高値づかみをしないよう気をつけたい。
しかし、心理的な節目の1万7000円を目前に利益を確定する売りも少なからず出たはずだ。前日の米国株や原油相場の下落も日本株には下押し圧力となった。トヨタや富士重の自動車株や三菱UFJや三井住友FGのメガバンク株に上げが目立ったが、他方、原油安で国際石開帝石や石油資源といった石油関連株に売りが膨らんだ。日経平均の3月の月中平均値は1万6900円程度で本日9月1日の終値とほぼ同水準だ。利益確定売りが出やすい水準として意識されやすい。今年4月以降、日経平均がこの水準を超えたのはわずか12営業日だけだった。
本日は金融、精密などの景気敏感株に資金流入が続いた。上昇率は業種別日経平均・製造業が1.8%、銀行は1.6%、自動車も1.1%と、いずれも日経平均の0.2%を大きく上回る。景気敏感株への資金流入が起こっているが、単に今まで売られすぎていた反動だけではないようだ。好調な米景気を反映して米国が次の利上げをすれば、日米の金利差が広がり円安・株高につながるとの見方から、ベンチマークに負けないためには景気敏感株を買わざるを得ないと市場は意識し始めている。
日経平均が17,000円の壁を打ち破り、さらに4月25日の戻り高値@17,613円を振り切って上げるには、売買シェア6~7割を占める外国人投資家の買いが必要だ。しかし、少しだけ古いが統計データを見ると気になる。対外及び対内証券売買契約などの状況(週間・指定報告機関ベース)によると、8月21~27日に海外投資家は日本株を68億円売り越したのだ。売り越しは2週連続。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-08-31/OCSSZU6SETC401
===============================================================================
~08/27/16 ~08/20/16 ~08/13/16 ~08/06/16 ~07/30/16
===============================================================================
-----------------------(単位:億円)---------------------
<対外証券投資>
合計(ネット) 4,072 4,355 13,538 10,494 4,053
公社債等(ネット) 1,057 4,330 12,976 9,121 3,124
買い 71,197 66,547 63,455 69,784 71,279
売り 70,140 62,217 50,479 60,662 68,155
株式(ネット) 3,335 1,427 1,414 2,437 729
買い 9,099 7,639 8,179 9,033 9,975
売り 5,763 6,212 6,765 6,596 9,245
小計(ネット) 4,393 5,757 14,391 11,559 3,853
短期証券(ネット) -320 -1,402 -852 -1,065 199
買い 2,098 2,572 2,598 2,344 4,966
売り 2,419 3,974 3,450 3,409 4,767
<対内証券投資>
合計(ネット) 524 9,290 -11,662 -6,137 21,186
公社債等(ネット) 2,687 2,919 4,748 -2,663 10,912
買い 9,350 17,229 14,904 22,565 23,990
売り 6,663 14,310 10,156 25,228 13,078
株式(ネット) -68 -2,293 945 -4,928 -955
買い 75,400 80,350 72,447 99,111 101,024
売り 75,468 82,643 71,502 104,039 101,979
小計(ネット) 2,620 626 5,693 -7,591 9,956
短期証券(ネット) -2,095 8,665 -17,355 1,454 11,229
買い 41,089 39,833 45,432 33,443 32,432
売り 43,185 31,168 62,786 31,989 21,203
米雇用非農業部門の就業者増加数が20万人を超えれば、相場は9月の米利上げを本格的に織り込むことになるだろう。
33業種中25業種が上昇した。上昇率トップ5は、その他製品(1位)、銀行(2位)、水産・農林(3位)、医薬品(4位)、その他金融業(5位)となった。
コメント投稿
↑ページのトップへ
|
|