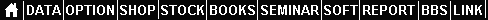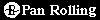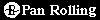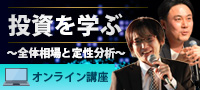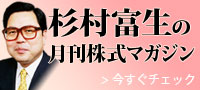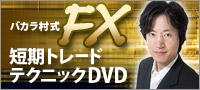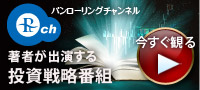|
「生涯現役のトレード日記」
|
「並び赤」となり、下方向には行きたくないとう「意思」 07月30日
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA -49.41 @40,539.93, NASDAQ +12.32 @17,370.20, S&P500 +4.44 @5,463.54)。ドル円為替レートは154円台後半の前日比円安水準での動きだった。東証プライムでは、上昇銘柄数が445に対して、下落銘柄数は1,163となった。騰落レシオは98.41%。東証プライムの売買代金は4兆1668億円。
TOPIX -5 @2,754
日経平均 +57円 @38,526円
米国では、31日に米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を控えており、方向感が乏しい動きだった。今回のFOMCでは、政策金利が据え置かれるとの見通しが主流だが、発表後のFOMC声明とパウエル議長の記者会見をマーケットは注目している。
本日の東京市場では、米国株式市場でダウ工業株30種平均が下げたことを嫌気して、朝方は売りが優勢となり、日経平均は一時400円近く下げた。また、31日の金融政策決定会合で日銀が利上げを見送るとの観測が有力となり、長期金利(新発10年債利回り)が低下した(0.995%へ)。利上げを警戒して売られていた不動産株の一角が買い戻され、肩透かしとなりそうな銀行株は売られて下げた。
日経平均の日足チャートを見ると、安く寄り付いてから切り返して陽線で引けた。昨日とほぼ同じ形のローソク足であり、2日をまとめて見ると「並び赤」となり、下方向には行きたくないという相場の「意思」を暗示しているようだ。
33業種中22業種が下げた。下落率トップ5は、鉱業(1位)、銀行(2位)、パルプ・紙(3位)、繊維製品(4位)、金属製品(5位)となった。
コメント投稿
米利下げ期待が一段と高まり株価は大幅反発 07月29日
先週金曜日の米国株式相場は大幅反発した(DJIA +654.27 @40,589.34, NASDAQ +176.16 @17,357.88, S&P500 +59.88 @5,459.10)。ドル円為替レートは153円台前半の先週末比円高水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄の方が圧倒的に多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,571に対して、下落銘柄数は僅か63だった。騰落レシオは105.39%。東証プライムの売買代金は3兆9681億円。
TOPIX +60 @2,760
日経平均 +801円 @38,469円
米国では、6月の個人消費支出(PCE)価格指数が前年比+2.5%(<5月分前年比+2.6%)と伸びが鈍化し、前月比でが+0.1%となり予想と一致した。米連邦準備制度理事会(FRB)による9月の利下げ期待が一段と高まり、主要3株価指数は揃って上昇した。
本日の東京市場では、日経平均が前日までに8日続落して約3,600円も急落していたこともあり、先週末の米国株の大幅反発の流れを受けて、先物主導で自律反発狙いの買いが優勢となった。日経平均の上げ幅は一時1,000円を超える場面があった。東証プライムの95%の銘柄が上昇してほぼ「全面高」となった。日銀の利上げが時間の問題となっているので、金利上昇で恩恵を受ける保険株が大きく上げた。銀行株も利上げの恩恵を受けるが、今日のところは保険株ほど上げなかった。
日経平均の日足チャートを見ると、先週金曜日時点でRSI(14日ベース)が24.3%(<下げ過ぎの目途である25%)、25日移動平均線乖離率がマイナス6.0%(<下げ過ぎの目途であるマイナス5.0%)と短期的な下方オーバーシュートとなっていた。そこへ米国株の大幅反発が加わり、日経平均も今日は大幅反発となった。これは単なる思惑ではなく、タイミングは正確にはまだ分からないが米国の利下げがかなり近いと言う確かな裏付けがある反発だった。ここからは、米国景気失速と米利下げのどちらが速いかという問題である。利下げのタイミングが遅すぎると、バブル崩壊後の日本経済のようにダメージが予想外に長引く。他方、日銀は日本経済を「金利がある世界」へ戻すべく、利上げのタイミングを測っているため、金利は徐々に上方向へ動くことになる。7月30~31日の金融政策決定会合と米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果を日米の投資家は固唾を飲んで待っている。
33業種中すべての業種が上げる全面高だった。上昇率トップ5は、保険(1位)、化学(2位)、非鉄金属(3位)、不動産(4位)、証券(5位)となった。
コメント投稿
リスクオフ相場は継続しているが落下速度は急減速 07月27日
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA +81.20 @39,935.07, NASDAQ -160.69 @17,181.73, S&P500 -27.91 @5,399.22)。ドル円為替レートは153円台後半の前日比円安水準での動きだった。本日の日本株全般は高安まちまちとなった。東証プライムでは、上昇銘柄数が705に対して、下落銘柄数は871となった。騰落レシオは96.50%。東証プライムの売買代金は4兆4350億円。
TOPIX -10 @2,700
日経平均 -202円 @37,667円
米国では、4~6月期GDP速報値が市場予想以上に強い結果(年率+2.8%>予想+2.1%)となった。これを追い風に景気循環株への資金ローテーションが続き、前日には500ドル強下げていたダウ工業株30種平均は一時584ドル高となったが、その後上げ幅を縮小させて81ドル高で終えた。ただ、7月26日に6月の米個人消費支出(PCE)物価指数発表を控えていたため、慎重だった。足元ではリスクオフがまだ支配的であり、米国債が買われて、米10年債利回りは前日の4.286%から4.244%へ低下した。前日に大幅安となったテスラは上げたが、イーロン・マスク氏の共和党支持は非常に不思議である。テスラ車の購入者の多くは民主党支持者だからである。さらに、トランプ前大統領が返り咲いたら、バイデン政権が現在実施いているEV補助金を打ち切ると明言しているからなおさらである。バイデン政権が化石燃料からの脱却を後押することによりテスラの売上を伸ばすことに貢献して来た。それなのに今、イーロン・マスク氏は気候変動の事実に懐疑的なトランプ支持に回った。地球環境に対する意識の高い米国の消費者はテスラ離れをする可能性が高い。
本日の日本株全般は下げる銘柄の方が多く、日経平均は8日続落した。8日続落は2021年9月27日から10月6日までの8日続落以来、2年9カ月ぶりの珍しいことである。昨日までの急落で自律反発狙いの買いが入り、一時は上昇に転じたが、再び売り圧力が高まり押し戻された。今週末の金融政策決定会合で日銀が利上げを決定するのではないかと警戒した外国人投資家(売買シェアの6~7割を占める)が日本株売りを主導していると推測できる。
シティグループ証券がまとめた過去20年ほどの東証TOPIXの12カ月先予想ROEとPBRの月末値をプロットするとROEが8%を超えるとPBRが上昇し始めることが確認できる(これは他社・研究者のデータでも同様で10年ほど前から度々新聞記事にもなっている)。ただ、PBR=1.5倍が天井となりそれ以上がらない。それは日本企業のROEが9~10%くらいに留まっているからである。理論株価評価モデルの一つである「残余利益モデル」から導き出したPBR決定式(優利加塾の勉強会では毎回取り上げて解説している)で計算してもそれくらいの数値になる。PBR=1.5倍以上に上昇するためには日本企業全体のROEを10%を遥かに超えるまで高めることが鍵となる。
日経平均の日足チャートを見ると、8日続落とはなったが、予想通り落下速度は急減速した。必ず早晩下げ止まり、反発を試しに行く。
33業種中23業種が下げた。下落率トップ5は、輸送用機器(1位)、保険(2位)、電気・ガス(3位)、空運(4位)、サービス(5位)となった。
コメント投稿
「三重苦」により日本株は記録的な下落! 07月26日
昨日の米国株式相場は大幅続落した(DJIA -504.22 @39,853.87, NASDAQ -654.94 @17,342.41, S&P500 -128.61 @5,427.13)。ドル円為替レートは152円台後半の前日比円高水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が277に対して、下落銘柄数は1,326となった。騰落レシオは96.85%。東証プライムの売買代金は5兆1999億円。
TOPIX -83 @2,710
日経平均 -1,285円 @37,870円
米国では、決算結果に失望されたテスラが12.34%安まで、アルファベットが5.04%安まで売り込まれたことで、ハイテク株全体に売りが波及して株価は大幅下落した。テスラは4~6月期決算においてEPS(一株利益)が0.52ドル(<市場予想=0.61ドル)と市場の期待を裏切り、各国で値引き販売を実施したため平均単価が下がり、将来の成長分野であるロボタクシー(自動運転タクシー)の発表を2カ月延期した。これが今回の世界的な急速な株安の引き金となった。24日に発表された米製造業購買担当者景気指数(PMI)は好不況の分水嶺である50を割り込んだ。主要3株価指数は揃って2日大幅続落した。明らかに上げ過ぎた反動が起こっている。アルファベットは7月23日の時点で年初来30%(>S&P500=+16%)も上昇していた。足元では株価が上げ過ぎた反動で急落しているが、遅くとも9月には利下げが始まるはずである。そこからまた駆け上がると見る。ニューヨーク連銀総裁のビル・ダドリー氏は「9月の会合まで利下げを待つのは景気後退のリスクを不必要に増やす」との見解を述べた。
本日の東京市場では、ほぼ全面安となり、日経平均は7日大幅続落(-3.28%、-1,285円34銭)した。米国株、特にハイテク株の大幅安と急速な円高・ドル安が進行したことが重なり、さらに海外投機筋の先物売りも加わった。米国による半導体の対中輸出規制が強化されて半導体関連銘柄の悪材料となっていたが、そこへハイテク株安と急速な円高も加わり「三重苦」となり、日本株を大きく叩き込んだ。日経平均は38,000円台に押し戻され、4月26日以来の水準へ下げた。下げ幅、下げ率ともに記録的な急落だった。7日続落(2021年9月27日~10月6日の8日続落)、下落幅(英国のEU離脱の是非を問う国民投票で離脱派が勝利した2016年6月24日の下げ幅=1,286円)、下落率(2021年6月21日の3.29%)。
来週開催される金融政策決定会合において日銀が利上げを決めそうであるという観測が有力になり、円相場は急速に円高・ドル安になった。日本株はこのまま下落して下落トレンドが明確になるだろうか?おそらくならない。商品投資顧問(CTA)などの短期プレーヤーは売っているが、中期運用のグローバル・マクロ系をはじめとする長期プレーヤーは日本株を買い続けている。世界最大の資産運用会社である米ブラックロックは今週発表したばかりのアウトルックで、今後1年で日本株のオーバーウェイトは最も確信度が高い見通しの一つであるとまで明言している。下げ止まるとすぐに買いが戻ると見る。
日経平均の日足チャートを見ると、巨大なギャップダウンの後さらに下げて長大陰線となった。昨年10月31日を起点とする上昇トレンドラインを明確に下抜けた。7月17日を起点とする7月11日までの上昇を約半分の時間で完全に帳消しにした。ここまで大幅且つ急激に下げると、ここからは下げるにしてもスピードがかなり落ち、下げ止まるや否や自律反発狙いの買いが大きく入り、比較的短期間で少なくとも3分の1戻しくらいはあると見るが、どう動くか?
33業種中、空運、陸運、水産農林を除く30業種が下げた。下落率トップ5は、電気機器(1位)、証券(2位)、保険(3位)、機械(4位)、銀行(5位)となった。
コメント投稿
10月31日を起点として描いてきた上昇トレンドラインの下限に達した 07月25日
昨日の米国株式相場は小幅安となった(DJIA -57.35 @40,358.09, NASDAQ -10.22 @17,997.35, S&P500 -8.67 @5,555.74)。ドル円為替レートは154円台後半の前日比円高水準での動きだった。本日の東京市場では、上昇銘柄数が122に対して、下落銘柄数は1,499となった。騰落レシオは104.45%。東証プライムの売買代金は3兆8657億円。
TOPIX -40 @2,793
日経平均 -440円 @39,155円
米国では、テスラとアルファベットの決算を取引時間終了後に控える中、前日にハイテク株を中心に上げた反動もあり、上値が重い動きだった。取引時間が終わってから発表されたテスラの決算内容が市場予想を下回ったため、時間外取引で7%安となった。
本日の東京市場では、外為市場で円相場が急伸して1ドル=154円台前半まで円高・ドル安になったため、輸出関連銘柄が売られただけでなく、リスク回避目的に海外短期筋が先物を売り先物主導で下げた。日経平均の下げ幅は一時500円を超えた。日経平均は前日まで5日続落して1,600円ほど下げたため、押し目買い狙いの買いも入ったが、悪い材料には勝てずさらに下げた。海外売上比率が高いホンダやコマツが売り込まれた。
日米金利差を背景に、円キャリートレードが活発化して円相場は1月の1ドル=140円台から上昇して来て、7月上旬には一時161円90銭まで下落していた。足元では日米金融政策が転換しそうな局面になっており、日米金利差が縮小しそうである。7月30~31日に日本では日銀の金融政策決定会合が、米国では米連邦準備制度理事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOMC)を開催する。FRBは9月には利下げを開始するとの見方が現在の主流の見方となっている。日銀が今回の金融政策決定会合で国債買い入れの減額と利上げを同時に決定することはないだろうというのが現在の大方の観測であるが、少なくとも国債買い入れの減額は決定すると予想されている。河野デジタル大臣、岸田首相、茂木自民党幹事長など政府要人が日銀に利上げを迫る発言や政府・日銀による突然の市場介入も意識されており、円キャリートレードの巻き戻しがさらに進むと予想される。
日経平均の日足チャートを見ると、昨日の「毛抜き底」も突き破り続落して、やや上向きの60日移動平均線に接するまで下げて来た。10月31日を起点として描いてきた上昇トレンドラインの下限に達したため、この数日間は正念場である。
33業種中全業種が下げた。下落率トップ5は、海運(1位)、電気・ガス(2位)、証券(3位)、空運(4位)、不動産(5位)となった。
コメント投稿
日経平均「毛抜き底」なら明日以降は反発すると見るが・・・ 07月24日
昨日の米国株式相場は反発した(DJIA +127.91 @40,415.44, NASDAQ +280.63 @18,007.53, S&P500 59.41 @5,564.41)。ドル円為替レートは156円台前半の前日比円高水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄の方が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,127に対して、下落銘柄数は472となった。騰落レシオは116.32%。東証プライムの売買代金は3兆4885億円。
TOPIX +6 @2,833
日経平均 -5円 @39,594円
米国では、半導体関連銘柄を中心に自律反発狙いの買いが優勢となった。バイデン大統領が11月の大統領選挙から撤退してカマラ副大統領を後任として指名したことから、ほぼ確実視されていたトランプ前大統領の返り咲きが不透明となった。そのため、トランプ前大統領の再選を見越した「トランプ・トレード」が巻き戻され、化石燃料業界に対する支援期待が後退してエネルギー株が下落した。他方、エヌビディアなど半導体関連銘柄は買い戻された。世界的な大規模障害の原因となったクラウドストライクは13%超下落し、2日続落した。
本日の東京市場では、米国株の反発を受けて、日経平均は朝方は300円を超える場面があったが、その後は利益確定売りが優勢となり押し戻された。来週7月30~31日に開催される金融政策決定会合で日銀が追加利上げに踏み切るのではないかという思惑もあり、株式相場の頭を抑えた。来週は米連邦公開市場委員会(FOMC)も開催されるので取引に慎重になっている。
日本郵船が2025年3月期決算予想を修正し、連結純利益は前期比71%増の3,900億円へ上方修正した。市場予想(3,227億円)を大幅に上回る内容だったため株価は8%上昇した。海運大手3社が出資するコンテナ船会社「オーシャン・ネットワーク・エクスプレス(ONE)」の業績上振れによるものである。そのため、他の海運大手株も大きく連れ高した。中東情勢の緊迫化と需要増加によりコンテナ船運賃が高騰していることに加え、円安・ドル高が続いていることが背景にある。6月の日銀短観によれば、2024年度の想定為替レートは全規模・全産業で1ドル=144円77銭だった。円高誘導のための為替介入が入った後でも足元の実勢レートは156円台なので、まだ12円ほど円安・ドル高水準で動いているため、業績上方修正の余地がある。
米連邦準備理事会(FRB)が早晩利下げに動く一方、日銀は利上げに動くのは時間の問題となっている中、米長期金利が低下したため、日米金利が縮小したことで円ショートの手仕舞いが始まり、円相場はドル安・円高方向へ動いた。
日経平均の日足チャートを見ると、反発して始まったが売り戻されて陰線が2日並んだ。それでも安値を比べて見るとほぼ同じとなっており「毛抜き底」と見ることもできる。毛抜き底なら明日以降には反発する可能性が高い。さて、どう動くか?
33業種中22業種が上げた。上昇率トップ5は、海運(1位)、銀行(2位)、ゴム製品(3位)、ガラス・土石(4位)、その他金融(5位)となった。
コメント投稿
バイデン大統領の撤退により不確実性が高まったため・・・ 07月22日
先週末の米国株式相場は続落した(DJIA -377.49 @40,287.53, NASDAQ -144.28 @17,726.94, S&P500-39.59 @5,505.00)。ドル円為替レートは149円台157円台前半での動きだった。本日の日本株全般は下げた。東証プライムでは、上昇銘柄数が236に対して、下落銘柄数は1,375となった。騰落レシオは107.40%。東証プライムの売買代金は3兆3112億円。
TOPIX -33 @2,828
日経平均 -465円 @39,599円
米国では、クラウドストライクのセキュリティソフトの更新が世界的な大規模システム障害を引き起こし、ハイテク株を中心に売りが優勢となり主要3株価指数は続落した。
本日の東京市場では、米国株安の流れを受けて、東京エレクトロンやアドバンテスト、ディスコ、レーザーテクなど半導体関連株が軒並み安となった。日経平均は4日続落して4万円の大台を割り込んだ。米国大統領選挙を巡る不透明感(バイデン大統領が11月の大統領選から撤退しカマラ・ハリス副大統領を後任に指名)に中国の景気不安(中央銀行が政策金利を引き下げ)も加わった。もし、トランプ前大統領が返り咲くと、米中対立がさらに激化し、自国優先政策をとるはずであり、その場合、現在の円安・ドル高を反転させよう、つまり円高・ドル安の方向へ動かそうとするだろう。中国人民銀行(中央銀行)が実質的な政策金利で優良企業向け貸出金利の指標である「最優遇貸出金利(ローンプライムレート、LPR)を引き下げた。住宅ローンの目安となるLPRも引き下げた。景気回復に繋がるとういう期待よりも、それほど中国景気は低迷しているのかとの不安が今日は勝った。そのため中国市場に対する依存が大きいオムロンや安川電機が下げた。
今まで『トリプル・レッド』(大統領選挙、上院議員選挙、下院議員選挙のすべてで共和党が勝利する)が予想されてきたが、バイデン大統領が選挙戦から撤退してハリス副大統領を後任に指名したことでその可能性が低くなった。しかし、その分だけ不確実性が高まったため、株式相場は下げた。トランプ前大統領はバイデン大統領の「老い」を攻撃してきたが、今度は自分が「老い」を材料に攻撃される立場となった。
トランプ前大統領が当選したら、関税を引き上げ、財政拡張政策を実施すると公言している。これはどちらも物価を押し上げてインフレを促進することになり、インフレが再燃すれば金利は必然的に上昇する。その結果、ドル高・円安の力として働く。1980年代前半のレーガン大統領の時と同じである。それにもかかわらず「私は低金利が好きだ」と無邪気なことを公言している。また、ドルが不当に高いとして不満で、米国の製造業が輸出しやすいようにドル安・元高、ドル安・円高の方向へ外為相場を動かそうとしている。また、半導体分野では台湾が米国からすべてを奪ったと敵意をあらわにしている。中国との対立はより鮮明となり、中国自体の景気減速もあり(高度経済成長は完全に終焉した)、政治的・経済的な理由により投資マネーは中国市場から日本市場へ移動することが想像できる。
日経平均の日足チャートを見ると、4日続落て上向きの25日移動平均線を明確に割り込んだ。これから戻る局面では2点天井やダブルトップを警戒する必要性が高くなった。
33業種中29業種が下げた。下落率トップ5は、精密機器(1位)、海運(2位)、電気機器(3位)、機械(4位)、鉱業(5位)となった。
コメント投稿
上げ過ぎた反動が起こっている 07月20日
昨日の米国株式相場は下落した(DJIA ‐533.06 @40,665.02, NASDAQ -125.70 @17,871.22, S&P500 -43.68 @5,544.59)。ドル円為替レートは157円台後半の前日比円安水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が494に対して、下落銘柄数は1,113となった。騰落レシオは120.89%。東証プライムの売買代金は3兆8167億円。
TOPIX -8 @2,861
日経平均 -62円 @40,064円
米国では、利益確定売りが優勢となり主要3株価指数は揃って下落した。ダウ工業株30種平均は7営業日ぶりに反落した。本日の東京市場では、米国株安の流れを受けて、幅広い銘柄が売られたが、米国市場でエヌビディアが反発したことを好感して、東京エレクトロンやアドバンテストが買われたので日経平均の下げ幅を縮小した。台湾積滞電路製造(TSMC)の2024年4~6月期決算及び7~9月期売上高見通しが市場予想を上回ったことが背景にある。日経平均の下げ幅は一時300円を超えたが、前の2営業日で1,100円ほど急落していたので今日は自律反発狙いの買いも入った。
日経平均の日足チャートを見ると、小幅続落して上向きの25日移動平均線に接するところで踏み止まった。ここで踏み止まれるか、さらに続落するかは米国株が下げ止まるかどうか次第だろう。米国株は連日で史上最高値を更新し続けていたので、今その反動が起こっている。
33業種中27業種が下げた。下落率トップ5は、鉱業(1位)、電気・ガス(2位)、空運(3位)、石油・石炭(4位)、海運(5位)となった。
コメント投稿
株価サイクル③(着実な上昇局面)が一旦終了 07月18日
昨日の米国株式相場は続伸した(DJIA +742.76 @40,954.48, NASADQ +36.77 @18,509.34, S&P500 +35.98 @5,667.20)。ドル円為替レートは157円台後半での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄の方が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,142に対して、下落銘柄数は453となった。騰落レシオは120.21%。東証プライムの売買代金は4兆4302億円。
TOPIX +11 @2,915
日経平均 -177円 @41,098円
米国では、米小売り売り下高が予想以上に強い結果となり、米国経済のソフトランディング期待が高まった。先行して大きく上げていたハイテク株は利益確定売りに抑えられたが、景気敏感株は大きく上昇した。米10年債利回りは前日の4.229%から4.160%へ低下した。ダウ工業株30種平均は5日連騰して史上最高値を更新した。ハイテク株が多いナスダックも3日続伸した。
本日の東京市場では、米経済のソフトランディング期待の高まりを背景とした米国株高の流れを受けて、日経平均は続伸して始まった。しかし、上値では利益確定売りが多く、買い一巡後は下げに転じた。値がさハイテク株の半導体関連銘柄が大きく売り込まれたが、理由があった。バイデン政権が、東京レクトロンやオランダの半導体製造装置大手のASMLホールディングなどの企業が先端半導体技術へアクセスを中国に提供し続けるなら、最も厳しい貿易制限措置を適用すると同盟国に伝えたことが背景にある。そのため、東京エレクトロンは一時8%を超す急落となり、アドバンテスト、スクリン、レーザーテクなどの値がさ半導体株も軒並み安となった。東京エレクトロンの一銘柄だけで日経平均を263円押し下げた。他方、トランプ前大統領が返り咲くと建設需要が高まるのと見立てから「トランプ・トレード」銘柄としてコマツ、日立建機、住友重機など建設機械関連銘柄が上昇した。
外為市場では、さらなる円買い・ドル売り介入を警戒している。変動相場制を採用する国では、介入は「半年で3回」、「1回の介入は3営業日以内」という介入ルールをかつて国際通貨基金(IMF)が示したが、今年の日本の為替介入(4月29日、5月1日、7月11~12日)はこのルールに沿っている。ということは10月下旬までにもう1回、3営業日連続の介入がありうる。7月17日の外為市場では一時、1ドル=156円台前半まで円高・ドル安に振れた。これは12日の介入時に付けた157円30銭台を上回る円高・ドル安水準であった。さらに、トランプ前大統領は米ブルームバーグ・ビジネスウィークのインタビューにおいて、円安と人民元安を容認せず、ドル高を是正する意向を示した。これで円売り・ドル買いがやり難くくなった。
日経平均の日足チャートを見ると、朝高後は下げて陰線で終えた。これで4日連続陰線となり、上げようとしても売りに押し返される日が続いており、基調は弱いと判断される。今日は上向きの10日移動平均線を僅かだか割り込んだので、が6月25日から始まった株価サイクル③(=着実な上昇局面)が一旦終了した。
33業種中27業種が上げた。上昇率トップ5は、繊維製品(1位)、不動産(2位)、建設(3位)、精密機器(4位)、パルプ・紙(5位)となった。
コメント投稿
「もしトラ」実現の可能性が高まったので・・・ 07月17日
昨日の米国株式相場は続伸した(DJIA +210.82 @40,211.72, NASDAQ +74.12 @18,472.57, S&P500 +15.87 @5,631.22)。ドル円為替レートは158円台後半の先週末比円高水準での動きだった。本日の日本株全般は高安まちまちとなった。東証プライムでは、上昇銘柄数が819に対して、下落銘柄数は783となった。騰落レシオは113.42%。東証プライムの売買代金は3兆9010億円。
TOPIX +10 @2,905
日経平均 +84円 @41,275円
米国では、最近相次いで発表された各種経済統計がインフレが落ち着いてきていることを示しており、9月にも米連邦準備制度理事会(FRB)は利下げを決断するとの観測が主流となっている。また、暗殺されかけたトランプ前大統領が九死に一生を得る幸運に恵まれて健在ぶりをアピールしており、大統領に返り咲く可能性が高まっている。恒久減税と石油・石炭など化石燃料に対する規制緩和で企業寄りの政策を公約しており、株価を押し上げる力として働いている。他方、関税を引き上げて国内産業を保護し(輸入物価が上がる)、移民の流入を抑える「不法移民強制送還」(労働力不足から賃金が上昇する)政策も実施すると表明しているため、ともに物価を押し上げる力となる。さらに、恒久減税は関税引き上げだけでは賄い切れず、財源として国債増発を意味しており、長期金利の上昇圧力となる。その結果、金利のイールドカーブ(利回り曲線)は満期が長くなるほど急傾斜(スティープ)化する。ダウ工業株30種平均もS&P500も史上最高値を更新した。
本日の東京市場では、米国株の続伸を受けて半導体関連株や電子部品株を中心に上げたが、先週末に下げ過ぎた反動で自律反発した面もある。「もしトラ」が実現する可能性が高まっており、「トランプ・トレード」として金融・機械・防衛・インフラ関連銘柄にも買いが入り、日経平均は一時300円超上げる場面があった。特に、トランプ氏はかねてより同盟国に対して軍事費の負担増を求めているため、防衛産業銘柄に買いが目立った。三菱重工、川崎重工、IHIが買われるのは自然な流れとなった。また、トランプ氏の恒久減税政策は長期金利を上昇させるため、その恩恵を受ける三菱UFJなどのメガバンク株が上昇した。
ただ、買いが一巡すると上値では利益確定売りが優勢となり押し戻された。また、政府・日銀は7月11日と12日の2日連続で外為市場に市場介入して円買い・ドル売り介入を実施したと推測され、円高・ドル安方向へ大きく振れたため、日本株全般には重しとなった。
日経平均の日足チャートを見ると、反発はしたが小幅反発であり、しかも、短陰線で終えた。今日のところは決して強い反発ではない。割高感がまだ解消していないため、上値では売り圧力の方が勝っている。
33業種中12業種が上げた。上昇率トップ5は、証券(1位)、石油・石炭(2位)、銀行(3位)、保険(4位)、機械(5位)となった。
コメント投稿
円買い市場介入、アイランド・リバーサルの示現・・・ 07月13日
昨日の米国株はナスダックが大幅反落した(DJIA +32.39 @39,753.75, NASDAQ -364.04 @18,283.41, S&P500 -49.37 @5,584.54)。ドル円為替レートは158円後半から159円台前半の前日比円高水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄の方が多かったのだが、株価指数は大幅反落した。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,020に対して、下落銘柄数は573となった。騰落レシオは119.32%。東証プライムの売買代金は5兆2369億円。
TOPIX -35 @2,895
日経平均 -1,033円 @41,191円
米国では、米6月消費者物価指数(CPI)が予想以上に伸びが鈍化した。前月比-0.1%(<予想+0.1%)、前年同期比+3.0(<前年+3.3%、予想+3.1%)。これにより利下げ期待が高まり、もはや「予想」からほぼ「確信」に変わったと言える。米10年債利回りは前日の4.280%から4.212%へ低下した。金利低下の恩恵を受ける銘柄(不動産、住宅関連企業など)が上げたが、年初から大きく上昇し続けて来たハイテク株が利益確定売りに押されて大きく反落した。フィラデルフィア半導体株指数(SOX)は3%強の下げとなった。
本日の東京市場では、米国でのハイテク株の大幅安を受けて、東京エレクトロンやアドバンテストなど半導体関連株を中心に利益確定売りが優勢となった。連日で史上最高値を更新し、高値警戒感が高まっていたところへ米国でのハイテク株安が起り、さらに急激な円高・円安方向への揺り戻し(7月16日の当座勘定残高の見通しからニューヨーク連銀が日銀の委託により3~4兆円規模の委託介入したと推察)も重なり、日経平均は急落した。1日の下げ幅は今年4月19日の1,011円を超えて1,033円安となり、今年最大の下げ幅となった。ただ、全面安とは程遠く、約6割の銘柄(主に内需株)は上昇したことに留意する必要がある。金利上昇期待で上げていた保険株や銀行株は売られた。米利下げ観測が高まってきたので、日銀は円安防止を意識して利上げを急ぐ必要性が低下したとの見立てからである。
久しぶりに政府・日銀が外為市場で市場介入したと推察される。「財政等要因」による減少額が介入がないと仮定した場合に比べて口座残高の減少予定額が3~4兆円多いことから介入に使った資金量がほぼ分かる。EU(欧州連合)の場合、為替の市場介入をする場合、その判断も実施も欧州中央銀行(ECB)が行うが、日本の場合、市場介入の判断は政府・財務省(より具体的には財務官)に権限と責任があり、実務は日銀が代行して行う。実務を代行する日銀が市場から円買い・ドル売り介入を実施すると、市中銀行の日銀勘定からその分だけ資金が引き落とされ、政府の日銀勘定(国庫)へ移し替わるため、民間金融機関の残高は減少する。但し、外為市場での直物売買の決済は2営業日後なので、実際にお金が動くのは、7月11日に介入したとすれば連休明けの16日に残高の変化があるはず。
市場介入のタイミングは絶妙だった。米CPIが発表されたがその内容は利下げを正当化するような物価上昇の鈍化を示すものだったため、米長期金利は低下し、何もしなくても円高・ドル安の方へ動いたはずだが、そのタイミングを見計らって市場介入して円買い・ドル売りを加速したと見られる。但し、実際に米国の立会時間中に介入したのは日銀の委託を受けたニューヨーク連銀だったはず。また、日銀が民間金融機関に対して円とユーロを交換する際の取引条件についての照会、つまり、ユーロの「レート・チェック」が行われた。「レート・チェック」は市場介入する前の準備とされ、対ドルだけでなく、対ユーロでも市場介入する姿勢が示された。1991年以降で円買い介入をした通貨はドルのみであり、もし、ユーロでも円買い介入をすれば史上初となる。ただ、円買い・外貨売りの市場介入は外貨準備残高以内(全部使い切るのはありえない)という誰の目にも明らかな物理的制約があり、短期的な効果しか期待できないということは「外国為替」を履修したなら大学生でも分かる。当然、財務省のエリート官僚も十分理解しているが、何もしないことのリスクを考慮しての行動だろう。
日経平均の日足チャートを見ると、大きくギャップアップして始まり、さらに下げて大陰線で終えた。これで昨日の短陰線は空中に浮いた「島」のようになり、天井を打ったことを暗示する「アイランド・リバーサル」が示現した。ただ、単純平均株価と言う計算上、日経平均に与える影響が大きいハイテク値嵩株が下げたのであって、東証プライムの全銘柄の内、1,020銘柄は上昇したのに対して、ハイテク値嵩株中心とした573銘柄が下落したに過ぎない。つまり、日本株の全面安ではない。来週は本日の急落の反動で反発するのではないだろうか。
33業種中24業種が下げた。下落率トップ5は、保険(1位)、電気機器(2位)、海運(3位)、非鉄金属(4位)、銀行(5位)となった。
コメント投稿
大きくギャップアップして上方新値13本目 07月12日
昨日の米国株式相場は大幅上昇した(DJIA +429.39 @39,721.36, NASDAQ +218.16 @18,647.45, S&P500 +56.93 @5,633.91)。ドル円為替レートは161円台後半の前日比円安水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,251に対して、下落銘柄数は356となった。騰落レシオは118.57%。東証プライムの売買代金は4兆7090億円。
TOPIX +20 @2,929
日経平均 +392円 @42,224円
米国では、パルエルFRB議長が前日の米上院に続き、米下院金融サービス委員会で議会証言を行い、高金利背策が長引いた場合の景気や雇用に対するリスクを述べた。これにより、9月には利下げに転じるとの観測が強まり、米10年債利回りは前日の4.300%から4.284%へ低下した。これらのことを背景に米国株式相場は大きく上昇した。10日に台湾のTSMC(台湾積滞電路製造)が6月の売上高は前年同期比32.9%増加したと発表した。人口知能(AI)がけん引する半導体需要の強さを改めて印象付けた。ナスダックは7日続伸して最高値を更新し続けている。
本日の東京市場では、米国でのハイテク株を中心とした上昇の流れを受けて、値がさ半導体関連株をはじめとする主力株が続伸して、日経平均は3日連続で史上最高値を更新した。日経平均の上げ幅は一時600円に迫ったが、買いが一巡すると上値が重くなった。短期的な過熱感が濃くなってきたからだ。足元の株高の背景には、(1)地政学リスクと景気減速を嫌い中国株から日本株への乗り換え、(2)上場企業が株主還元のために自社株買いを積極的に行っている、(3)従来は逆張り思考が強かった個人投資家がそうではなくなってきた、(4)欧州のパッシブ型運用の機関投資家がリバランスのために日本株を買っている、などが指摘されている。
日経平均の日足チャートを見ると、大きくギャップアップして始まったが、寄り付き後は売りに押されて短陰線で終えた。これで6月17日を起点とすると上方新値13本目となった。経験則では、通常の波ならもうそろそろ一旦は調整が入ってもおかしくないくらい一気に上げて来た。さて、明日はもう一上げするか、一旦は調整するか?
33業種中29業種が上げた。上昇率トップ5は、鉱業(1位)、パルプ・紙(2位)、金属製品(3位)、医薬品(4位)、建設(5位)となった。
コメント投稿
株価サイクル③で順調に上昇中ではあるが・・・ 07月11日
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA -52.82 @39,291.97, NASDAQ +25.55 @18,429.29, S&P500 +4.13 @5,576.98)。ドル円為替レートは161円台半ばの前日比円安水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄の方がやや多かったが、株価指数は続伸した。東証プライムでは、上昇銘柄数が638に対して、下落銘柄数は931となった。騰落レシオは111.14%。東証プライムの売買代金は4兆7650億円。
TOPIX +14 @2,909
日経平均 +252円 @41,832円
米国では、パウエルFRB議長が米上院で議会証言を行い、引き締め政策の長期化が経済活動や雇用に悪影響を与える可能性について認識を示した。つまり、FRBは「インフレ抑制」だけでなく、「雇用維持」も気にし始めたといことだ。通貨の価値を維持することが主な責務の日銀と違い、米連邦準備制度理事会(FRB)は法律上(1)通貨価値の維持と(2)雇用の維持の2つの責務を負っているから、ある意味で当然である。これにより近い将来の利下げが示唆されたと解釈され、株価の支援材料となった一方、株価は高値警戒感から利益確定売りも出て、高安まちまちとなった。FRBの利下げの可能性を巡り、今週木曜日発表の6月米消費者物価指数(CPI)と金曜日発表の6月米生産者物価指数(PPI)に注目が集まっている。
本日の東京市場では、先物主導で株価は上昇して日経平均の上げ幅は一時300円を超え、TOPIXと日経平均が同時に史上最高値を更新した。いわゆる「ダブル最高値更新」である。上場投資信託(ETF)の分配金捻出のため1兆数千億円規模の売りが出るため株価は下がるとの読みから先物でショートしていた投機筋が、予想に反して急上昇してきた相場に踏み上げられて大急ぎで買い戻している姿が目に浮かぶ。国内長期金利の上昇を背景に、東京海上など保険株が上げた。明日以降は銀行株に波及するか。自社株買いを材料としてリクルート・ホールディングス(PBR=7倍、ROE=19%の超優等生企業)が連騰としており、上場来高値を更新した。
信用評価損率(買い方のみ)が高値警戒レベルまで低下してきた。7月5日現在でマイナス4.63%まで縮小して来た。経験則では、信用評価損率が5%未満になってくると相場が天井を打つことが多い。
もう一つの仮需である裁定取引はどうなっているか。相場が力強く上昇する局面ではまず先に先物が買われて現物よりも早く上げることが多いため、先物価格は割高となり現物は割安となる。そこで割高な先物を売り、割安な現物を買う裁定取引が行わる。値幅は小さいものの、SQでは必ず先物価格=現物価格となるため、裁定取引を行った瞬間に利益が確定する。この残高が裁定買い残となるが、この残高が或る程度積みあがってくると自重で崩れるように、裁定解消売りが起り始めて相場が天井を打つため、信用評価損率とともに監視する必要がある。裁定買い残は3週連続で続伸しており、7月5日時点で2兆5129億円となった。これは5月31日の2兆5850億円以来の高水準である。
日経平均の日足チャートを見ると、6月25日に株価サイクル③(着実な上昇局面)(「生涯現役の株式トレード技術 海図編」210ページ)に入ってから上昇に弾みが付いている。6月17日を起点に上方新値12本目となったので、後数本以内の上方新値で一旦は止まるのが通常のパターンである。信用評価損率もマイナス5%を切って来たので調整相場の気配を感じたら一旦は利食い売りをして利益確保しておきたい。
33業種中26業種が上げた。上昇率トップ5は、保険(1位)、サービス(2位)、精密機器(3位)、証券(4位)、食品(5位)となった。
コメント投稿
オイルマネー流入観測、大陽線で上げた 07月09日
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA -31.08 @39,344.79, NASDAQ +50.98 @18,403.74, S&P500 +5.66 @5,572.85)。ドル円為替レートは160円台後半での前日比円安水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,098に対して、下落銘柄数は472となった。騰落レシオは107.88%。東証プライムの売買代金は4兆4725億円。
TOPIX +28 @2,896
日経平均 +799円 @41,580円
米国では、先週末に発表された6月雇用統計が弱い内容だったため米連邦準備制度理事会(FRB)が利下げをしやすい環境になったとの観測でS&P500とナスダックが共に史上最高値を更新した。しかし、7月9~10日にはパウエルFRB議長が上下院で議会証言を行い、11日には6月の消費者物価指数(CPI)の発表を控えているため、多くの投資家は慎重だった。
本日の東京市場では、米連邦準備制度理事会(FRB)が利下げをしそうだという相場観測とS&P500とナスダックが史上最高値を更新したことを背景に日経平均は上昇して、上げ幅は一時900円を超えた。本日の特徴は時価総額が大きい大型株銘柄が集中的に買われたことだ。東証株価指数コア30は1.48%高となった。上場投資信託(ETF)の分配金を捻出するために売りが多く出て下げるとの見立てに基づき、株価指数先物を使いショートで仕掛けていた投機筋は、逆に反発したため慌てて買い戻したようである。これが上昇に弾みを付けた。また、多くの大型株を押し上げるほどの大きな金額の買いが日本株市場に入っており、オイルマネーが流入し始めたと推察できる。
信用買い残が2週連続で減少しており、信用買い残(7月5日時点)は5週間ぶりの低水準となった。株価が上昇する過程で信用買い残が減少・信用売り残が増加すると株価は軽くなるのでさらに上昇しやすくなる。
日経平均の日足チャートを見ると、3月22日の高値@41,087円を大陽線で上抜けした。これで上方向への弾みが付いた。
33業種中24業種が上げた。上昇率トップ5は、電気(1位)、非鉄金属(2位)、精密機器(3位)、上昇・通信(4位)、化学(5位)となった。
コメント投稿
上場投資信託(ETF)による分配金捻出のための売りを警戒して・・・ 07月08日
先週金曜日の米国株式相場は上昇した(DJIA +67.87 @39,375.87, NASDAQ +164.46 @18,352.76, S&P500 +30.17 @5,567.19)。ドル円為替レートは160円台後半での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が493に対して、下落銘柄数は1,098となった。騰落レシオは104.51%。東証プライムの売買代金は3兆9025億円。
TOPIX -17 @2,868
日経平均 -132円 @40,781円
米国では、米6月雇用統計が弱かったため、米連邦準備制度理事会(FRB)による利下げ期待が高まり(9月にも実施か)、米10年債利回りが低下した。その結果、株式相場は上げた。非農業部門雇用者数(NFP)は予想以上だった(20.6万人>予想20.0万人)が、前月分は大幅下方修正された。失業率は横ばい予想だったが悪化し(4.1%>予想4.0%)、平均賃金率も前月分から伸びが鈍って予想と一致した(前月比+0.3%、前年同月比3.9%)。つまり、労働市場の需給の引き締まりが緩和してきてコスト・プッシュ・インフレが収まってきている兆候である。
本日の東京市場では、短期的な過熱感(日経平均は2週間ほどで2,000円強上げていた)ため、利食い売り優勢となり日経平均は下げた。ザラバでは40,112円と取引時間中の最高値を更新する場面もあった。ただ、今週は上場投資信託(ETF)の運用会社が分配金捻出のため、8日と10日で合計1兆円数千億円の売りを出すと推定されているので、買いが引っ込んだと思われる。5月の勤労統計調査で高い賃金率が確認されたので日銀は追加利上げを含む金融政策の正常化をしやすくなったとの観測が強まり、株式相場の重しになった。
投資信託を経由した日本人の家計が円安・ドル高を進める力になっている。2024年1~6月の海外株式・ファンドの買い越し額は6.1兆円となった。同じ期間の日本の貿易赤字額(2011年の福島の原発事故から始まった)は約4兆円だったから、それを上回る円安・ドル高の力となった。今年1月から始まった新NISAを活用した積立投資が海外資産に向っている。これは短期投機筋とは違い、長期投資なので何年も反対売買は起こらないため、為替相場の方向を大きく左右する。足元の日本の物価上昇率は2%程度だが、大きなリスクを取らない限りそれを上回る運用商品が日本にはほとんどないため、より高いリターンを求めて投資資金は海外へ向かう。それが円安・ドル高を進行させる力となる。
日経平均の日足チャートを見ると、ザラバでは史上最高値を更新したものの、その後は売りに押されて上ひげを引いた短陰線で終えた。上値では利食い売りや戻り売り圧力が強いことを示した。
33業種中27業種が下げた。下落率トップ5は、海運(1位)、電気・ガス(2位)、鉄鋼(3位)、保険(4位)、銀行(5位)となった。
コメント投稿
日経平均、ザラバでは史上最高値@41,087円を更新したが・・・ 07月06日
昨日の米国株式相場は独立記念日の祝日のため休場だった。ドル円為替レートは160円台後半の前日比円高水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数は303に対して、下落銘柄数は1,314となった。騰落レシオは110.26%。東証プライムの売買代金は4兆288億円。
TOPIX -14 @2,884
日経平均 -1円 @40,912円
昨日の米国株式相場は祝日のため休場だった。ドイツDAXやフランスCAC40など欧州株式相場の上昇の流れを受けて、日経平均も上昇して始まり、東京エクトロンはスクリンなど半導体関連銘柄の一角が買われて取引時間中の最高値を更新したが、その後売り圧力が高まり陰線で終えた。足元で目立って上げて来た保険株が利益確定売りが優勢となり下げた。外為市場では、円相場が円高・ドル安方向に振れた。円高・ドル安を背景にインバウンド需要が高水準で推移しており、高級ブランドをはじめとして高額商品が売れている。6月の速報では既存店売上高は前年同期比2割ほど増加しており、三越伊勢丹は24.2%も売り上げ増となった。その結果、百貨店株は明確な中期上昇トレンドを描き続けている。
日経平均は史上最高値を更新する目前まで上昇して来たが、不安材料がないわけではない。それは日本株売買シェアの6~7割を占める外国人投資家の動向である。7月4日に公表された投資家別売買動向によれば、6月第4週(24~28日)に外国人は先物で4,746億円買い越した。しかし、外国人投資家は先物で4月から6月第3週まで1兆円以上売り越していたため、その一部を買い戻したに過ぎないと言える。先物を売買するのは主に短期売買目的であり、中長期のポジションを取る目的ではない。そのため、先物買いが増えたからと言ってもそのロングポジションの大半は比較的早く反対売買して売り戻される。では、現物はどうか。現物売買では外国人投資家は6月第4週には買い越したものの、その金額は僅か1,239億円であり、先物買いの4分の1の小ささだった。結論。外国人投資家はまだ本腰を入れて長期保有を目的に日本株を買っているわけではないようだ。
日経平均の日足チャートを見ると、4日続伸で始まり、ザラバでは一時、今年3月22日に付けた史上最高値@41,087円を更新して41,100円まで上げた。これで当面の目標達成である。来週の月曜日以降、さらに続伸して上放れるか、或いは、利食い売りが優勢となって調整するか?日経平均も株価サイクル③であり、個別銘柄も株価サイクル③のものは上振れしやすい。
33業種中27業種が下げた。下落率トップ5は、海運(1位)、輸送用機器(2位)、電気・ガス(3位)、非鉄金属(4位)、鉄鋼(5位)となった。
コメント投稿
3月22日の史上最高値(@41,087円)更新は目前! 07月05日
昨日の米国株式相場は半日の短縮取引だったが、続伸した(DJIA -23.85 @39,308, NASDAQ +159.54 @18,188.35, S&P500 + 28.01 @5,537.02)。ドル円為替レートは161円台前半の前日比円高水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,645に対して、下落銘柄数は586となった。騰落レシオは124.52%。東証プライムの売買代金は4兆1303億円。
TOPIX +26 @2,898
日経平均 +333円 @40,914円
米国では、経済指標が総じて弱い結果となり、FRBが9月には利下げに動くとの期待ややが高まり、米10年債利回りが前日の4.436%から4.354%へ低下した。6月ADP民間部門雇用者数が15.0万件(<予想16.0万件)、6月ISM非製造業総合指数(PMI)は48.8(<好不況の分水嶺50.0)、新規失業保険申請件数は23.8万件(<予想23.5万件)となった。長期金利の低下を背景に、大幅高となったテスラが先導してナスダックは連日で史上最高値を更新した。
本日の東京市場では、米国でハイテク株が上昇した流れを受けて、アドバンテストやソフトバンクグループが買われ、トヨタやホンダなど自動車株、三菱UFJなどの銀行株も買われた。時価総額が大きいバリュー株が買われたことで、TOPIXの上昇に弾みが付き、TOPIXは1989年12月18日に付けた史上最高値@2,884.80を34年7カ月ぶりに更新した。株価指数先物の売り方やコール・オプションの売り方の買戻しに追い込まれ、日経平均の上げ幅は一時400円を超えた。
トランプ氏が米大統領に返り咲くシナリオが有力となるに連れて、もしそれが実現したら何が起こるかを想像しておこう。まず、人気取りのために減税をする、同時に財政出動を拡大する、その資金源は国債の増発になるので長期金利に上昇圧力がかかるが、他方でトランプ氏は米連邦準備制度理事会(FRB)に圧力をかけて、利下げを強要する。ただ、FRBが直接コントロールできるのは政策金利であるFF金利のみである。それでも、米景気にはプラスの力が働くので米株価は上昇する。当然、その恩恵は日本経済と日本株にも及ぶはずである。さらに、別ルートの日本株押し上げ効果も想像できる。トランプ氏は対中国貿易政策で共和党政権以上に強硬姿勢を打ち出すはずだから、中国株に振り向けられている資金が日本株に移るため日本株の上昇要因になる。
日経平均の日足チャートを見ると、3日続伸して今年3月22日に付けた市場最高値@41,087円目前まで上昇して来た。このまま一気に上抜ければさらに上昇に弾みが付くが、目標達成感が支配的となれば利食い売りが優勢となり、暫くは調整相場となる。株価サイクル③になってまだ日柄が浅いので上昇エネルギーが十分残っているため上抜けするか。
33業種中28業種が上げた。上昇率トップ5は、非鉄金属(1位)、輸送用機器(2位)、銀行(3位)、卸売り(4位)、機械(5位)となった。
コメント投稿
株価サイクル③の真骨頂をまたもや発揮 07月04日
昨日の米国株式相場は続伸した(DJIA +162.33 @39,331.85, NASDAQ +149.46 @18,028.876, S&P500 +33.92@5,509.01)。ドル円為替レートは161円台後半での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が980に対して、下落銘柄数は616となった。騰落レシオは124.29%。東証プライムの売買代金は4兆3443億円。
TOPIX +16 @2,872
日経平均 +506円 @40,581円
米国では、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長がインフレ抑制のため、2%のターゲットに向って進展があったとECBフォーラムで述べた。しかし、利下げについてはインフレが持続的に2%に向って低下しているさらなる確証が必要であるとして、早期の利下げには慎重な姿勢を示した。5月JOLTS求人件数が814万件(>市場予想791万件)と強い結果となった。米長期金利(=10年債利回り)は前日の4.479%から一時4.465%まで上昇する場面があったものの、4.437%で引けた。テスラが10.1%と大幅上昇したことでアマゾンやアップルなど他のハイテク株も連れ高となった。S&P500とナスダックは史上最高値を更新した。7月4日は独立記念日のため休場となるが、その前日の3日は半日の短縮取引となる。
本日の東京市場では、米国市場でのハイテク株の上昇を受けて、東京エレクトロンやアドバンテストなどの半導体関連銘柄や村田製作所やTDKなどの電子部品銘柄が上昇して日経平均を押し上げた。前日まで上昇基調が強かった保険株や銀行株は上昇が一服した。日経平均の上げ幅は一時600円を超えた。
日経平均の日足チャートを見ると、力強く続伸して株価サイクル③の真骨頂をまたもや発揮した。今年1月9日以降の動きと比較してみると今のところ似ている。
33業種中21業種が上げた。上昇率トップ5は、機械(1位)、海運(2位)、その他金融(3位)、化学(4位)、電気機器(5位)となった。
コメント投稿
株価サイクル③(着実な上昇局面)入り 07月03日
昨日の米国株式相場は小幅高となった(DJIA +50.66 @39,169.52, NASDAQ +146.70 @17879.30, S&P500 +14.61 @5,475.09)。ドル円為替レートは161円台後半の前日比円安水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄の方がやや多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が864に対して、下落銘柄数は720となった。騰落レシオは115.28%。東証プライムの売買代金は4兆5345億円。
TOPIX +32 @2,857
日経平均 +444円 @40,075円
米国市場では、アップル、マイクロソフト、テスラなどのハイテク株が主導して株式相場を押し上げた。ナスダックは約半月ぶりに史上最高値を更新した。6月ISM製造業PMIは48.5(<前月48.7、市場予想49.1)と予想よりも弱い結果となり、米10年債利回りは低下する場面があった。しかし、仏国債が売られて仏長期金利が上昇すると、米10年債利回りも連れ高となり4.49%まで上昇した。
本日の東京市場では、保険や銀行などを中心としたバリュー株が引き続き上昇し、円安・ドル高が進行して株式相場全体を押し上げた。米国市場ではトランプ氏が大統領に返り咲く可能性が高まったとして財政赤字がさらに悪化することを想定し、米長期金利が4.49%まで上昇した。これに呼応して国内長期金利も上昇し、それが上昇していた保険株と銀行株をさらに押し上げた。三菱UFJは7営業日で17%上昇して一時、2006年以来の約18年ぶりに最高値を更新した。メガバンクは金利が高い米国を中心として海外でも大規模に展開しており、且つ、連結決算では円安・ドル高が収益をさらに増大させる。銀行をはじめとする時価総額が大きい銘柄が上げて来たことでTOPIXは連日で年初来高値を更新しており、1990年1月以来約34年ぶりの高値を付けた。外為市場では、1ドル=161円台後半の円安(1986年12月以来37年半ぶり)になっているため、輸出関連銘柄の一角が買われた。
金利が上昇中であるにもかかわらず、銀行株や保険株以外も買われている。本来は金利が上昇すると株価を押し下げるのが原理原則である。ではなぜ今株価が上昇しているのだろうか。それは名目金利から期待インフレ率を引いた実質金利は依然としてマイナスであるからである。
7月上旬、特に8日と10日には要注意である。多くの上場投資信託(ETF)が分配金の支払基準日(=決算)を迎えるためである。分配金捻出のための売りは最大で1兆2600億円と試算されている。この下げを見越して例年7月上旬には先物や値嵩株を空売りを仕掛ける動きがあるため、数日間から1週間程度は下げるシナリオも想定しておきたい。
日経平均の日足チャートを見ると、安く始まったが切り返して陽線で終えた。3つの移動平均線(10日、25日、60日)のすべてが上向きに転じ、且つ、株価はその上に位置している。株価サイクル③(着実な上昇局面)である。
33業種中31業種が上げた。上昇率トップ5は、海運(1位)、鉱業(2位)、保険(3位)、精密機器(4位)、証券(5位)となった。
コメント投稿
「フレンチ・ショック」はまだだが・・・ 07月02日
先週金曜日の米国株式相場は小幅反落した(DJIA -45.20 @39,118.86, NASDAQ -126.08 @17,732.60, S&P500 -22.39 @5,460.48)。ドル円為替レートは161円台前半の前日比円安水準での動きだった。本日の日本株全般は高安まちまちとなった。東証プライムでは、上昇銘柄数は796に対して、下落銘柄数は790となった。騰落レシオは112.60%。東証プライムの売買代金は3兆8632億円。
TOPIX +15 @2,824
日経平均 +48円 @39,631円
米国では、5月個人消費支出(PCE)価格指数の伸びが鈍化した。コア指数は前月比+0.1%、前年比+2.6%となり、事前の市場予想と一致した。また、6月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値は68.2%
(>予想65.8%)は予想よりもやや強かったが、1年先期待インフレ率確報値は前月分の3.3%から3.0%へ低下し、5年先期待インフレ率確報値も3.1%から3.0%へ低下した。その結果、米10年債利回りは前日の4.288%から一時4.261%まで低下する場面があったが、終値では4.396%となった。利下げ期待が高まり、S&P500とナスダックはザラバで史上最高値を更新したが、期末特有のリバランス(持ち高調整)目的の売りが多く出て、主要3株価指数は揃って小幅反落した。
本日の東京市場では、ドル高・円安基調を背景に輸出企業の収益改善期待が日本株全体を下支えした。日経平均は一時300円超上げて、心理的節目(=上値抵抗線)となる4万円に近づくと売りに押し返された。他方、日銀の追加利上げ観測が高まり(7~10月?)、長期金利が上昇していることでその恩恵を受ける第一生命やMS&ADなどの保険株や銀行株が引き続き上げた。しかし、買いが一巡すると伸び悩んだ。4万円の心理的な上値抵抗線と上場投資信託(ETF)が分配金捻出のためにポートフォリオの一部を換金するために売ってくる(7月8日、10日の2日間で1兆2000億円くらいの売り需要がある)ことを警戒した。中東情勢の緊迫化によりスエズ運河の通航を避け、喜望峰周りで積み荷を運ぶ海運会社が増えており、その分だけ運送日数が増加して、運賃が上昇している。コンテナ運賃も上昇した。その結果、海運大手3社の収益が改善すると見られ、本日は海運3社の株価は上げた。
発表された6月の日銀短観では、大企業製造業の業況判断指数(DI)が3月調査から改善した(プラス13>前回11)。事業計画の前提となる2024年度の想定為替レートは輸出企業で1ドル=142.68銭(>前回調査1ドル=140円40銭)なので、足元の160円近辺とは大きなプラス乖離がある。因みにトヨタ自動車の2025年度の想定為替レートは1ドル=145円であり、トヨタは1円・円安になる毎に収益が500億円増加する為替感応度を持つ企業である。ただ、大企業非製造業の数値を見ると業績判断DIはプラス33(<3月調査、プラス34)へ低下し、さらに、小売業に注目するとプラス19(<前回調査、31)から12ポイントも落ち込んだ。物価高で売り上げが大きく落ちている現実を反映しているだろう。
フランスでは6月30日に国民議会(下院)選挙の初回投票が実施され、ルペン氏率いる極右政党である国民連合(RN)が投票率首位となったが単独では過半数を取れなかった。右派が議席を伸ばすことは事前に予想されていたたため、株式相場には既にある程度織り込まれていたため、本日のところはこれと言った悪材料とは見做されなかった。しかし、左派も台頭し、その結果、与党が勢力を大きく落とした。このまま行けばフランスの政権分断は深刻化する。その先にあるのはフランス国債の急落とそのショック(フレンチ・ショック)が、たとえ一時的にせよEU及び世界の金融・外為市場を揺さぶりかねない。7月7日の2回目の投票(決選投票)まで確定はしないが、与党の中道連合は解散前の250議席から60~90議席まで減ると予想されている。極右政党と左派政党は政策が違うが、折り合える共通項が一つだけある。それは「人気取り」のために財政政策により政府の支出を増加するということである。欧州連合(EU)は、参加条件として債務残高を国内総生産(GDP)比で60%以下、財政赤字は同3%以内に抑えるという財政ルールを順守するように加盟国に求めている。しかし、1999年にユーロが誕生して以来、フランスはこの2つの基準を満たしたことがほとんどない。2024年予想は財政収支は4.8%の赤字で、債務残高は111%である。それでも共通通貨ユーロがあるため資金繰りに困ることはなかった。通常の国なら長期金利が上昇するとその国の通貨は高くなるのだが、フランス国債が売られてフランスの長期金利が上昇すると、おそらくユーロは下がるだろう。すると、ドル円では有効だったキャリートレードが対ユーロでは難しくなることを暗示し、為替レートの変動が金利差から政治・経済の安定と言う側面に焦点が移ることになる。
日経平均の日足チャートを見ると、高く寄り付いたがその後は売りに押されて陰線で終えた。チャートは上方向に行きたがっているように見えるが、その方向への動きはそれを逆行させるような大きな材料が今後飛び出して来なければという条件付きであることを常に肝に銘じておかなければならない。チャートは役に立つが割と頻繁に期待外れの動きをする。予想だけに頼っていては市場平均並みのリターンしか得られない。だから、もしそうなっても困らないようにするには何をどのような原理に基づいてどう考えてどう行動するのかを事前に決めておくのだ。そして、その体系が「売買ルール」である。当然、その売買ルールの有効性と限界はバックテストして十分理解しておかなければならない。
33業種中23業種が上げた。上昇率トップ5は、海運(1位)、保険(2位)、石油・石炭(3位)、鉄鋼(4位)、鉱業(5位)となった。
コメント投稿
↑ページのトップへ
|
|