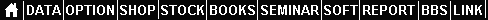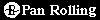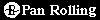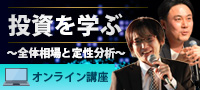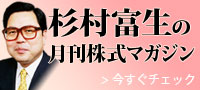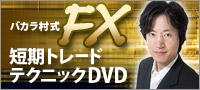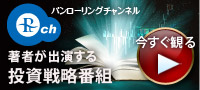|
「生涯現役のトレード日記」
|
石破政権の経済政策を警戒して「倍返し」の急落! 09月30日
先週金曜日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA +137.89 @42.313.00, NASDAQ -70.70 @18,119.59, S&P500 -7.20 @5,738.17)。ドル円為替レートは 141円台後半の先週末比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は大幅下落となった。東証プライムでは、上昇銘柄数が130に対して、下落銘柄数は1,505となった。騰落レシオは105.44%。東証プライムの売買代金は6兆1216億円。
TOPIX -95 @2,646
日経平均 -1,910円 @37,920円
米国では、8月個人消費支出(PCE)価格指数が予想を下回る伸び(+2.2<予想+2.3%、7月+2.5%)となり、インフレ鈍化傾向を示した。米連邦準備理事会(FRB)による追加利下げと米経済のソフトランディング期待が株式相場を下支えした。米10年債利回りは前日の3.789%から3.756%へ低下した。ミシガン大学が発表した9月米消費者態度指数(確報値)は70.1となり、速報値(69.0)から上方修正され、且つ、市場予想(69.3)も上回り、消費を巡る懸念が和らいだ。ダウ工業株30種平均は一時450ドルほど上げる場面があった。
本日9月30日の東京市場では、27日の自民党総裁選で石破茂氏(企業に対して法人税を引き上げ、投資家に対しては金融所得課税強化を唱え、日銀の独立性を尊重・重視していることから日銀の利上げを支持)が決選投票で高市早苗氏(アベノミクスの継承、つまり、円安・株高・金利低下、金融緩和と積極財政政策を唱える)を逆転して勝利したことで、高市早苗氏の勝利を見込んで前日に大幅上昇していた分を「倍返し」で吐き出した。外為市場では、1ドル=141円台の円高ドル安となったため、輸出関連銘柄を中心に幅広い銘柄が売られ、日経平均の下げ幅は一時2000円を超えた。
10月1日に臨時国会が召集され新内閣が発足し、4日には所信表明演説、その後、衆議院は解散され、衆議院議員選挙は10月15日告示、27日投票と決まった。過去を見る限り、選挙期間中は株は下がらない、つまり、「選挙は買い」である。1993年以降、10回あった総選挙前後の日経平均は、解散当日から投票日まで10回とも日経平均は上昇した。今回はどうなるか?
石破氏は週末のテレビ番組で「金融緩和を継続する」と発言し、円高進行への市場の不安を払しょくしようとした。しかし、本日の株式相場を見る限り、マーケットは日銀の利上げを織り込み始めたと見る。その根拠は、メガバンク株が軒並み逆行高で寄り付き、33業種中唯一逆行高となったことである。
米中ともに景気重視に舵を切り、金融緩和を開始したため、世界経済を下支えると期待されるが、経験則では10月は相場が荒れやすい。要注意である。
日経平均の日足チャートを見ると、直前の大陽線2日分を完全に打ち消して反落した。前日の陽線の始値辺りから始まり、長大陰線で反落する「振り分け線」となった。振り分け線はそれまでの株価の動きを止めるサインとされる。25日移動平均線はまだ上向きであり、株価もその上で推移しているので、もし明日続落するとしても、下げ幅は今日よりもずっと小さくなると見ているが、さて、どう動くか。
33業種中、銀行を除く32業種が下げた。下落率トップ5は、輸送用機器(1位)、不動産(2位)、証券(3位)、電気・ガス(4位)、電気機器(5位)となった。
コメント投稿
9月2日の戻り高値@39,080円を上抜けしたが、来週月曜日は・・・ 09月27日
昨日の米国株式相場は上昇した(DJIA +260.36 @42,175.11, NASDAQ +108.09 @18,190.29, S&P500 +23.11 @5,745.37)。ドル円為替レートは146円前半の前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は高安まちまちとなった。東証プライムでは、上昇銘柄数が642に対して、下落銘柄数は928となり、下落銘柄数の方が多かったが、株価指数は大きく上昇した。騰落レシオは115.78%。東証プライムの売買代金は5兆6354億円。
TOPIX +20 @2,741
日経平均 +904円 @39,830円
米国では、新規失業保険申請件数が21.8万件(>予想22.5万件)と予想を下回り、労働市場が堅調なことを示した。8月耐久財受注は前月比変わらず(>予想はマイナス2.6%)、4-6月期GDP確報値は改定値の+3.0%と変らずとなった。米経済はソフトランディングしつつあるとの期待がますます高まった。米長期金利(10年債利回り)は前日の3.78%から3.80%へ上昇した。中国当局は24日に既に預金準備率を引き下げて景気刺激策を打ち出していたが、26日には追加で不動産市場の安定化を図る支援策も打ち出した。中国経済の恩恵を受けやすいキャタピラーやスリーエムなど資源・産業資材関連銘柄が上げた。また、好決算を発表したマイクロンテクノロジーが約15%上昇し、他の半導体関連銘柄も上げた。景気後退しない中での利下げは株高となり易いという経験則がある。FOMO(=Fear of Missing Out: 今行動しないと自分だけ取り残される恐怖)で多くの投資家が株を買うように突き動かされている。
本日9月27日の東京市場では、自民党総裁選挙で高市早苗経済安全保障大臣が得票数トップとなった。彼女はアベノミクスの継承を掲げる政策を公約しているため、日銀の利上げに反対しており、金利低下・円安の「高市トレード」が活発になったことで、日経平均は大幅高となった。外為市場では、1ドル=146円台まで円安ドル高が進んだため、トヨタ自動車など輸出関連銘柄が目立って上げた。配当権利落ち分が約261円あったが、それを完全に撥ね退けて上昇した。
しかし、自民党総裁選挙は大引け後の決選投票で、日銀の独立性を尊重し、金融所得課税強化を訴えている石破茂元幹事長が勝利した。これを受けて、外為市場では146円台から一挙に142円台の円高ドル安となった。日経平均先物は時間外で急落しており、午後9時40分現在、38,000円割れ目前となっている。大阪取引所の夜間取引では、取引開始直後に売りが殺到して前日比2,000円以上安となったため、誤発注などを防止する目的で一時的に強制的に売買停止をする「ダイナミック・サーキット・ブレーカー」が発動された。これは上下に8%動いた場合の通常の「サーキット・ブレーカー」とは別の強制一時売買停止措置である。石破氏の自民党総裁選での勝利を受けて、日銀は利上げがしやすくなり、140円台の円高ドル安は射程圏内に入り、新発10年債利回りは0.805%から一時0.855%へ急上昇した。
日経平均の日足チャートを見ると、目先の目標だった9月2日の戻り高値@39,080円を長大陽線で軽く上抜けした。チャートだけ見るとさらに上に行きそうな勢いだが、株価を動かす原因はチャートそのものでなく、チャートは結果に過ぎない。株価を動かす真因は業績見通し(=予想EPS)と期待(予想PER)の変化であり、数週間以内の超短期では期待の変化が株価を動かし、その結果としてチャートが描かれる。本日の自民党総裁選で石破氏が勝利したことで、株式相場にとっては悪材料となり、既に日経平均先物は急落して動いている。ほぼ確実に来週月曜日は大きく下げて始まりそうである。
33業種中17業種が上げた。上昇率トップ5は、精密機器(1位)、機械(2位)、不動産(3位)、化学(4位)、電気機器(5位)となった。
コメント投稿
1兆2000億円の「配当再投資」による買い需要を先回り買い!? 09月27日
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA -293.47 @41,914.75, NASDAQ +7.67 @18,082.20, S&P500 -10.67 @5,722.26)。ドル円為替レートは144円台後半の前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は上昇した。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,580に対して、下落銘柄数は56となった。騰落レシオは113.76%。東証プライムの売買代金は5兆2377億円。
TOPIX +71 @2,721
日経平均 +1,055 @38,926円
米国では、主要3株価指数が相次いで最高値更新を続けているため高値警戒感が漂う中、週内に新規失業保険申請件数、8月個人消費支出(PCE)価格指数の発表を控えていることで、様子見ムードが支配的となり、利益確定売りが優勢となってきた。
中国当局による景気刺激策が強気材料として注目を集めている。米国の利下げが中国の景気刺激策を決断させた背景にある。人民元安を心配せずに利下げ出来るからである。日本以外の多くのにも当てはまる。
本日9月26日の東京市場では、円相場が1ドル=145円台まで円安ドル高方向に振れたため、自動車をはじめとする輸出関連銘柄が買われたが、米国での半導体関連銘柄が上げたことを受けて、東京エレクトロンやアドバンテストなど半導体関連銘柄も上げた。また、今日は3月期決算企業の中間配当の権利付き最終売買日だったため、配当の権利取りを狙う個人投資家の買いがたくさん入ったと見られる。さらに、機関投資家は中間配当を受け取るまでの期間、株価指数と実際の運用成績とのズレ(トラッキング・エラー)を最小限に抑えるため受け取り配当金分を先物で買っておく操作をする。そのため株価は上げ易くなる。この「配当再投資」の額は1兆2000億円を超えると見積もられており、その買いを見越して海外投資家が先回りして大量に買ったと見られる。
米FRBが利下げを開始したのに円安ドル高方向に動くことが多いが、それは足元の利下げが「予防的利下げ」であるからだ。経験則では、予防的利下げは金利低下につながりにくい。過去数十年で米FRBが予防的利下げに踏み切ったのは1995年、1998年、2019年の3回あったが、いずれも米長期金利は利下げ後でもほとんど下がらず、寧ろ上がる時すらあった。今回も今のところその前例通りの動きをしているため、日米金利差が縮小せず、円安ドル高方向に基調として動いていない。これは日本株にとっては円高ドル安という逆風がほとんど吹かないということである。
日経平均の日足チャートを見ると、当面の目標である9月2日の戻り高値@39,080円に迫るところまで上昇して来た。ただ、明日は配当権利落ちがあるので300円弱は悪材料がなくても下げるはずだ。
33業種中すべての業種が上げた。上昇率トップ5は、その他製品(1位)、金属製品(2位)、電気機器(3位)、機械(4位)、ガラス・土石(5位)となった。
コメント投稿
利益確定売りが多くなり小幅安となった 09月26日
昨日の米国株式相場は続伸した(DJIA +83.57 @42,208.22, NASDAQ +100.25 @18,074.52, S&P500 +14.36 @5,732.93)。ドル円為替レートは144円台前半の前日比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は高安まちまちとなった。東証プライムでは、上昇銘柄数が805に対して、下落銘柄数は772となった。東証プライムの売買代金は3兆8404億円。
TOIPIX -6 @2,651
日経平均 -70円 @37,870円
米国では、9月消費者信頼感指数が前月分改定値の105.6から98.7へ大きく悪化したことで再び景気後退懸念が強まった。しかし、既に0.50%の政策金利の引き下げが行われているだけでなく、今後、FRBは速いピッチで追加利下げを実施する(11月のFOMCでさらに0.50%利下げする)はずなので米国経済はソフトランディングするとの期待が根強い。米長期金利が下げ、特に政策金利の影響を受けやすい2年債利回りは下げた。その結果、ダウ工業株30種平均は4日連続で史上最高値を更新した。また、中国当局も24日に追加金融緩和策と株式・不動産市場支援策を発表したことも米国株式相場を下支えした。ただ、S&P500も連日の最高値更新により米国株式相場は高値警戒感が強まっているのでちょとした悪材料がきっかけで急落することもあるので要注意だろう。
本日9月25日の東京市場では、日経平均は直前4日で約1,700円上げていたこともあり、利益確定売りが多くなり5営業振りに反落した。米長期金利の低下を反映して円相場は円高ドル安方向へ動いた。しかし、自社株買いを発表したトヨタ自動車株は円高を撥ね退けて上げた。米長期金利の低下を嫌気して保険と銀行が目立って下げた。
東証が25日に発表した9月20日申し込み時点の信用買い残高は3兆9831億円と、前週末から1,027億円減少した。信用買い残の減少は株式相場の重しが減ることを意味し、上げ易くなる。反対に信用買い残が増加すると、潜在的な売り需要が増加するため閾値を超えてくると相場全体の上昇を抑える方向に働く。さらに、株価が下げる過程で信用買い残が増加し続けると下げ相場が長引く。
日経平均の日足チャートを見ると、上ひげを引いた短陰線で小幅安となった。10日移動平均線も25日移動平均線も上向きであり、株価もその上にあるので上に動きやすいが、日々の日足ベースの値動きはその時々の株価材料に反応する。
33業種中16業種が下げた。下落率トップ5は、保険(1位)、銀行(2位)、水産・農林(3位)、精密機器(4位)、情報通信(5位)となった。
コメント投稿
植田和男日銀総裁の発言で円安ドル高へ大きく振れた 09月25日
昨日の米国株式相場は小幅続伸した(DJIA +61.29 @42,124.69, NASDAQ +25.95 @17,974.27, S&P500 +16.02 @5,718.57)。ドル円為替レートは144円台前半の先週末比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は高安まちまちとなった。東証プライムでは、上昇銘柄数が877に対して、下落銘柄数は713となった。騰落レシオは106.47%。東証プライムの売買代金は4兆3014億円。
TOPIX +14 @2,657
日経平均 +217円 @37,941円
米国では、9月の米購買担当者景気指数PMI速報値が予想以上に悪化した(前月47.9から47.0へ)ため、景気後退懸念が再び持ち上がった。しかし、先週、米連邦公開市場委員会(FOMC)で先手を打って0.50%の大幅利下げを決定していたので、株式相場は狼狽することなく続伸した。7月中旬から始まった狼狽売りの嵐とは大違いである。S&P500 とダウ工業株30種平均はともに連日で史上最高値を更新した。
本日9月24日の東京市場では、米経済がソフトランディングするとの期待から米国株式相場の上昇基調が継続していることを好感して、買い優勢の展開となった。日経平均は一時上げ幅が700円強となった。日銀の植田和男総裁が、政策判断について「時間的な余裕はある」と再び発言したと報道されると、円相場は1ドル=144円台まで円安ドル高となり、株式相場はこれを好感して上げた。中国でも、当局が追加金融緩和を相次いで発表し、上海総合指数とハンセン指数が急伸したことも日本株の買い安心感につながった。ただ、日経平均は直前の3営業日で1,500円ほど上げていたので、利食い売りに頭を抑えられた。
6月の日銀短観によれば2024年度の企業の想定為替レートは全規模・全産業で1ドル=144円77銭だったため、1ドル=140円台では減益懸念が高まっていたが、その懸念が後退した。3月期決算企業の配当権利付き最終売買日が近づき、上場投信(ETF)やGPIFなどのパッシブ型運用の機関投資は9月末の配当再投資をするのでその買いが期待されている。
日米金利差の縮小はほぼ確実路線だが、足元では円高ドル安方向には動いていない。それはなぜだろうか。一つの理由はドルの実需買いが大きくなっているからである。では、なぜドル買い円売りの実業買い需要が大きいのだろうか。それは日本の貿易収支が大赤字だからである。2024年1~8月の累計では、4兆5000億円もの赤字である。2022年、2023年も巨額の貿易赤字だった。投機目的のドル買い円売りは利益確定のため比較的短期間で反対売買が起るが、実需のドル買い円売りは反対売買が起らないため為替相場の方向性を大きく左右する。さらに、ミセス・ワタナベ(個人のFXトレーダーの総称)も金利差からドル買いを好む。今後の円相場は、金利差縮小によるドル売り円買いの力と実需によるドル買い円売りの力との綱引きとなるので、円高ドル安が着実に進行することはなさそうである。円安ドル高にも関わらず、本日、トヨタ自動車株が上がらなかった背景はここにあるかもしれない。
日経平均の日足チャートを見ると、3日続伸したが下向きの60日移動平均線にちょうど弾き返されるように上ひげを引いた陰線で終えた。9月2日の戻り高値@39,081円が現在の目標であるが、米国株の動き次第だろう。
33業種中25業種が上げた。上昇率トップ5は、海運(1位)、保険(2位)、電気・ガス(3位)、非鉄金属(4位)、精密機器(5位)となった。
コメント投稿
FOMCと金融政策決定会合を通過 09月21日
昨日の米国株式相場は大幅高となった(DJIA +522.09 @42,025.19, NASDAQ +400.68 @18,013.98, S&P500 +95.38 @5,713.64)。ドル円為替レートは142円台前半での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,077に対して、下落銘柄数は504となった。騰落レシオは113.52%。東証プライムの売買代金は5兆9244億円。
TOPIX +25 @2,642
日経平均 +569円 @37,724円
米国では、前日に米連邦公開市場委員会(FOMC)で0.50%の大幅利下げが決定されて株式市場が好感している中、新規失業保険申請件数が予想を下回る強い結果(21.9万件<予想23.0万件)となった。これにより米経済は景気後退ではなくソフトランディングするとの期待が高まっており、ダウ工業株30種平均もS&P500も史上最高値を更新した。エヌビディアやAMDなどの半導体関連銘柄が大きく上げて、フィラデルフィア半導体株指数(SOX)も4.26%高で終えた。
本日9月20日の東京市場では、前日の米国株相場の大幅高の流れを受けて日本株全般は上昇し、日経平均の上げ幅は一時800円を超えた。日銀の金融政策決定会合では現状維持が決定され、追加利上げはない。今後も当面の間、日銀が追加利上げするのは難しそうだ。
日経平均の日足チャートを見ると、上向きの25日移動平均線上抜けした。ただ、長めの上ひげを引いた寄り引き同事線となったので今日のところは売り買いの力が拮抗した。明日以降どのように動くかは米国株の動き方次第だろう。
33業種中29業種が上げた。上昇率トップ5は、石油・石炭(1位)、非鉄金属(2位)、電気機器(3位)、銀行(4位)、鉱業(5位)となった。
コメント投稿
米金利利下げ決定でも「意外」の円安ドル高の理由は・・・ 09月19日
昨日の米国株式相場は小幅下落した(DJIA -103.08 @41,503.10, NASDAQ -54.76 @17,573.30, S&P500 -16.32 @5,618.26)。ドル円為替レートは142円台後半の前日比円安水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,340に対して、下落銘柄数は257となった。騰落レシオは112.77%。東証プライムの売買代金は4兆594億円。
TOPIX +52 @2,617
日経平均 +775円 @37,155円
米国では、米連邦公開市場委員会(FOMC)で0.50%の大幅利下げが決定された。政策金利であるFF金利を従来の5.25~5.50%から4.75~5.00%へ引き下げた。これを受けて、米10年債利回りは前日の3.642%から一時3.634%まで低下した。しかし、バルエルFRB議長が会見で利下げを急がない姿勢(今後の利下げペースは穏やか)を示したことで切り返し、結局3.731%に上昇して終えた。つまり、0.50%という大幅利下げにもかかわらず、米長期金利は逆に上昇した。これにより円安ドル高となった。FOMCメンバーのFF金利見通しは年内にさらに0.50%の追加利下げの可能性を示した。パウエルFRB議長は今回の利下げは「予防的な措置」であり、米経済は良い状態であるという楽観的な認識を示した。
本日9月19日の東京市場では、FOMCを通過し、円相場が円安・ドル高となったことをきっかけとして輸出関連銘柄を中心に買われた。マーケットの期待通り、米利下げが始まったことで米経済は景気後退に陥ることなく、ソフトランディングするとの期待が高まり、日経平均の上げ幅は一時1,000円を超えた。足元では円高ドル安基調を主な理由として売り込まれてきた三越伊勢丹や高島屋など百貨店株が買い戻された。ただ、この先も中期的に日米金利差縮小がほぼ確実な状況では、一時的に円安方向に振れても基調は円高方向に動くのが道理である。本日は意外高となった主な原動力は、米金利利下げによる円高ドル安と日本株安を見越して大きく売り長ポジションへ傾斜していた短期筋が買い戻したことである。米景気が後退しないなら、米利下げ局面の第一段階の利下げは日本株の大底になり易い(1995年、1998年、1999年)という経験則が意識された。
日銀は19~20日に金融政策決定会合を開催している。円相場は7月に付けた1ドル=161円台を起点として考えるとかなり円高方向に動いてきたことを考えると、今回は追加利下げはしないと見ている。しかし、もし追加利上げを実施するなら、ほぼ確実に円高ドル安と株安が同時に進むはずだ。
日経平均の日足チャートを見ると、大きくギャップアップして始まり、さらに上げて陽線で終えた。一時1,000円以上高くなり、上向きの25日移動平均線にもう少しで届きそうになった。9月5日に25日移動平均線を割り込んでからその下で団子状になっていきたが、その団子の上限を上抜けた。明日以降、上向きの25日移動平均線を回復できるかどうかに注目している。
33業種中すべての業種が上げた。上昇率トップ5は、海運(1位)、保険(2位)、輸送用機器(3位)、非鉄金属(4位)、サービス(5位)となった。
コメント投稿
FOMCの結果公表待ち 09月18日
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA -15.90 @41,606.18, NASDAQ +35.93 @17,628.06, S&P500 +1.49 @5,634.58)。ドル円為替レートは141円台半ばの前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,190に対して、下落銘柄数は413となった。騰落レシオは111.48%。東証プライムの売買代金は3兆4707億円。
TOPIX +10 @2,565
日経平均 +177円 @36,380円
米国では、翌日の米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果公表を控えて、高安まちまちとなった。利下げはほぼ確実視されているが、下げ幅が通常の0.25%なのか大幅利下げの0.50%なのかにマーケットの注目が集まっている。もし0.50%なら景気を下支えする効果と企業の資金調達コストの低下をもたらす効果が期待される一方、米景気はそこまで悪いのかという景気後退懸念を高める可能性もある。株価に対する影響はどうだろうか。利下げ幅が0.50%なら円高・ドル安進行を通して日本株売り、0.25%なら日米ともに株は失望売りとなるか。
本日9月18日の東京市場では、米経済指標が市場予想を上回ったことで米景気後退懸念が和らぎ、米長期金利が上昇したことを反映して1ドル=142円台まで円安ドル高方向に動いた。これを好感して昨日売られた自動車株など輸出関連銘柄を中心に買い戻された。日経平均は一時470円高まで上げたが、円相場が1ドル=141円台前半になると日経平均も売りが優勢となり上げ幅を縮小した。日本時間の今夜、午前3時にFOMCの結果が公表される。続いて、9月20日には日銀の金融政策決定会合の結果が公表される。マーケットはこういう大きなイベントの通過を待っている。
日経平均の日足チャートを見ると、今日も陰線で終え、株価は下向きの10日移動平均線の下に沈んだままである。しかし、9月11日から見ると安値は徐々に切り上がっている。さらに、25日移動平均線の傾きが上向きに転じているため下げ渋り感が強い。
33業種中23業種が上げた。上昇率トップ5は、輸送用機器(1位)、石油・石炭(2位)、鉱業(3位)、ゴム製品(4位)、倉庫・運輸(5位)となった。
コメント投稿
米大幅利下げ観測により円高ドル安が進み・・・ 09月17日
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA +228.30 @41,622.08, NASDAQ -91.85 @17,592.13, S&P500 +7.07 @5,633.09)。ドル円為替レートは130円台後半から140円台後半の先週金曜日比円高水準での動きだった。本日の日本株全般は高安まちまちとなった。東証プライムでは、上昇銘柄数が960に対して、下落銘柄数は631となった。騰落レシオは113.06%。東証プライムの売買代金は4兆2028億円。
TOPIX -15 @2,556
日経平均 -379円 @36,203円
米国では、9月18日に連邦公開市場委員会(FOMC)の結果公表を控えているが、2022年3月に始まった利上げ過程で初めて利下げが実施されることが確実視されている。金融株やエネルギー株など幅広い銘柄が買われてダウ工業株30種平均は8月30日以来、半月ぶりにザラバと終値で史上最高値を更新した。他方、ハイテク株が多いナスダックは反落した。WSJ(Wall Street Journal)が先週、今回の利下げ幅は0.50%(通常は0.25%刻み)になるとの観測を示した。会合後のパルエル議長の記者会見も年内の利下げ幅を予測するために注目される。
本日9月17日の東京市場では、日米金利差の縮小を見越して円高ドル安が進み、一時は1ドル=139円台へ突っ込んだ。その結果、トヨタ自動車をはじめとする輸出関連銘柄を中心に売られ、米金利の低下により利ザヤが縮小するとの懸念から銀行と保険も売られた。ナスダックの反落を受けて、東京エレクトロンなど半導体関連銘柄も下げ、日経平均の下げ幅は一時750円を超えた。
日経平均の日足チャートを見ると、陰線で終えて9月4日に10日移動平均線を下抜けて以来本日までその上に再浮上していない。下向きの10日移動平均線の下で株価が推移している限り、上振れよりも下振れし易い。
33業種中18業種が下げた。下落率トップ5は、保険(1位)、銀行(2位)、証券(3位)、電気機(4位)、輸送用機器(5位)となった。
コメント投稿
円高進行と3連休を控えて・・・ 09月14日
昨日の米国株式相場は続伸した(DJIA +235.06 @41,096.77, NASDAQ +174.15 @17,569.68, S&P500 +41.63 @5,595.76)。ドル円為替レートは140円台後半の前日比円高水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が358に対して、下落銘柄数は1,234となった。騰落レシオは115.94%。東証プライムの売買代金は4兆2172億円。
TOPIX -21 @2,571
日経平均 -252円 @36,582円
米国では、米8月生産者物価指数(PPI)がほぼ予想通りとなり、新規失業保険申請件数も予想の範囲内の小幅増加だったことで、9月の米連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ期待がさらに高まると同時に米経済はソフトランディングするとの期待もさらに高まった。その結果、主要3株価指数は揃って続伸した。欧州中央銀行(ECB)は2会合ぶりに利下げを決めた。
本日9月13日の東京市場では、円高ドル安が進み、一時は1ドル=140円60銭台まで円高に振れたため、自動車株をはじめとする輸出関連銘柄が売られた。日経平均の下げ幅は400円近くまで拡大する場面があった。ただ、前日の米国株式市場でハイテク株が上昇したことから、東京市場でも東京レクトロンやアドバンテストなどの値がさ半導体株が買われて日経平均を下支えた。昨日の日経平均が先物主導で1,213円と今年3番目の上げ幅だったことを考えるとある程度の調整は自然であるし、3連休を控えていたことも手じまい売りしたいという気持ちを促した。
来週の米FOMCと日銀の金融政策決定会合という大きなイベントを通り過ぎれば株価は安定するか。ただ、懸念材料がある。米国の特別清算指数(SQ)を算出する第3金曜日を過ぎると、決算発表1カ月前から企業は自社株買いを控えることも一因となり、過去3年では日米ともに9月は月末に向けて株価は大きく下げた。今年はこれに円高ドル安も下げ要因として加わる。日本経済は自動車、電気、機械などの米国を中心とする海外で稼ぐ外需株の比率が他国よりも高い。それに円相場の変動も加わり、日本株は海外景気の変動を他国の株式相場以上により敏感に影響を受ける。
日経平均の日足チャートを見ると、陰線で終えたが、昨日の長大陽線の上半分くらいでの値動きだった。上向きの260日の上に留まっている。
33業種中27業種が下げた。下落率トップ5は、ゴム製品(1位)、輸送用機器(2位)、医薬品(3位)、保険(4位)、電気・ガス(5位)となった。
コメント投稿
円高進行の一服と米ハイテク株の上昇を受けて・・・ 09月12日
昨日の米国株式相場は上昇した(DJIA +124.75 @40,861.71, NASDAQ +369.65 @17,395.73, S&P500 +58.61 @5,554.13)。ドル円為替レートは142円台後半の前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は大きく反発した。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,550に対して、下落銘柄数は77となった。騰落レシオは118.51%。東証プライムの売買代金は4兆2134億円。
TOPIX +62 @2,593
日経平均 +1,214円 @36,833円
米国では、米8月消費者物価指数(CPI)でコアCPIが前月比+0.3%(>予想+0.2%)と予想を上回ったことからFRBによる9月の大幅利下げ(0.50%)が遠のき、一時株価は大きく下げて反応した。ダウ工業株30種平均は743ドル安まで下げた。しかし、売りが一巡すると切り返して前日比反発して終えた。米10年債利回りは前日の3.644%から3.657%に上昇して終えた。フィラデルフィア半導体株指数(SOX)は5%高となり、エヌビディアも急反発して8%高となった。
本日9月12日の東京市場では、米国市場でハイテク株が大きく上昇した流れを受けて、東京エレクトロンやアドバンテストなど半導体関連銘柄が大きく上昇した。米8月CPIの結果を反映してFRBによる9月の大幅利下げは遠のき、0.25%になるだろうとの読みから 円高ドル安進行が一服した。これを好感して自動車株など輸出関連銘柄も買い戻され、日経平均を押し上げた。
11日には日銀の中川順子審議委員が、そして本日12日には田村直樹審議員が利上げに関して前向きなタカ派発言をした。昨日は過剰反応して円高ドル安方向へ振れたが、本日は冷静な反応だった。輸入物価が下げてきているため時間差を伴い早晩、消費者物価指数(CPI)も上昇圧力が弱まり、もしかしたら来春には2%を割り込むかしれない。もしこのシナリオが実現すると、これから1年先でも日銀の利上げ幅は精々0.25%くらいではないだろうか。
米国の債券市場で「短期金利>長期金利」という逆イールドが解消して来た。逆イールドは景気後退の兆候を示す「炭鉱のカナリア」のように受け止められる。政策金利の利下げがほぼ確実な現在、政策金利の影響を受けやすい短期の2年債利回りは急速に下げているのに対して、10年債利回りも下げてはいるがその下げる速度が遅いため、9月6日以降、逆イールドが解消した。政策金利は今後下げていることがほぼ確実なため2年債利回りも同じようなペースで下げて行くはずである。対照的に、10年債利回りは下げるにしてもペースが遅くなりそうである。11月の米大統領選挙戦で共和党のトランプ氏が勝っても、民主党のハリス氏が勝っても、どちらも大規模な財政出動を伴う政策を公約しているからである。ただでさえ、米国は何十年も税収不足で財政赤字を続けているため、当然お金が大幅に足りない。その不足分は大規模な国債発行で賄うしかなく、10年債利回りは相対的に高止まりする。
日経平均の日足チャートを見ると、ギャップアップして始まりさらに上値を追って上がり大陽線で終えた。9月9日以来沈み込んでいた上向きの260日移動平均線の上に再浮上した。ただ、どこまで反発するかは不明であるが、チャートを見る限り、弱ければ半値戻しで25日移動平均線辺り@36,900円が反発の限界となるかもしれない。強くても9月2日高値@39,080円辺りか。
33業種中すべての業種が上げた。上昇率トップ5は、電気機器(1位)、機械(2位)、非鉄金属(3位)、輸送用機器(4位)、海運(5位)となった。
コメント投稿
日銀の追加利上げ・円高を懸念して・・・ 09月11日
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA -92.63 @40,736.96, NASDAQ +141.28 @17,025.88, S&P500 24.47 @5,495.52)。ドル円為替レートは141円台前半の前日比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は下げた。東証プライムでは、上昇銘柄数が105に対して、下落銘柄数は1,523となった。騰落レシオは113.24%。東証プライムの売買代金は4兆1993億円。
TOPIX -46 @2,531
日経平均 -539円 @35,620円
米国では、9月17~18日に開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)では利下げがほぼ確実に決定されるとマーケットは織り込み済みであるが、問題はその利下げ幅(0.25% or 0.50%)である。その利下げ幅の手がかりとなりそうなものが、今週発表される8月消費者物価指数(CPI)と8月卸売物価指数(
PPI)である。現在にマーケットの主流は0.25%の利下げである。
本日9月11日の東京市場では、1ドル=140円台まで円高・ドル安が進行したことを嫌気して輸出関連銘柄を中心に売られた。また、米大統領選挙候補者テレビ討論で、民主党のハリス氏が共和党のトランプ氏(法人税の引き下げを公約している)よりも優勢との見方が広がると、海外投機筋が売りで反応した。日経平均の下げ幅は一時900円を超えた。今日の円高ドル安進行の主な原因の一つは、本日11日に日銀の中川順子審議員が、経済・物価見通しが実現していくようなら金融緩和の度合いを調整して行くことになると述べ、日銀の追加利上げを示唆したものと受け止められたことである。
円高ドル安基調は当分の間は続くだろう。なぜなら米連邦準備制度理事会(FRB)は今月にも利下げを開始し始めるのに対して、日銀はこれから徐々に利上げを実施するため金融政策の周期がほぼ180度ずれているからだ。これから日米金利差は縮小していくのがほぼ確実なので、短期的な綾戻しは何度もあるはずだが、ベクトルの方向としは円高ドル安が進むと見ておく。では株価はどうなるか。内需株は円高ドル安の恩恵を受けるが、反対に外需株には逆風となるため、日経平均で測る日本株全般は向こう半年から1年先くらいまで下に大きく振れ易くなり、それでも安くなると押し目買い入ることにより反発するが、1/3戻しから1/2戻しくらいで反発は止まり、そこからまた下げるというイメージが今現在は描ける。ではそれがいつまで続くか。それは米利下げが完了するか、日銀の利上げが完了するまでだろう。
原油価格の下げが続いている。米原油指標であるWTI先物価格の期近物はは9月10日に一時1バレル=65.27ドルまで下げ、2023年5月以来の安値となった。主な原因は米中での需要の伸びが鈍化している(景気減速懸念と表裏一体)からである。原油安効果もあり、10年物のブレーク・イーブン・インフレ率(BEI=国債と物価連動債の利回り格差)は10日は2.0%に迫った。もう少しで2020年12月以来の1%台となり実質インフレ利が低下しているので、米連邦準備制度理事会(FRB)は利下げをしやすくなった。その結果、米長期金利は2023年6月以来の低い水準となった。これは日銀にはどういう力学が働くだろうか。原油安と円高は日本の輸入インフレを抑える。ということはインフレ抑制という大義名分が薄れてしまい、日銀の利上げを抑制する力となって作用することで日銀が利上げし難くなる。だから何?マーケットが警戒しているほど速くは円高・ドル安は進まない可能性が高い。
日経平均の日足チャートを見ると、昨日に続き下ひげを引いた陰線で大きく下げた。下ひげの安値が9月9日安値@35,247円にほぼ並ぶ35,253円となった。円高ドル安基調は依然として明確且つ理由もあるので、外需銘柄を中心に売られて日経平均の下振れは暫くの間大きくなると見る。東証が11日に発表した6日時点で裁定買い残が前週比減少したことも相場の弱さを裏付けている。株価が力強く上昇する過程では先物が主導して上昇するため、先物は理論値に比べて割高になる。そのため機関投資家は割高な先物を売り、割安な現物を買う裁定取引を行うことで薄利だが、SQまで待つだけでリスクなしで利益を確定することができる。逆に、株価が下げる過程ではこの「買い裁定取引」は起こらない。むしろ逆のことが起こる。割安となった先物を買い戻し現物を売る「裁定解消売り」が出てくるが、こうすることにより限月(先物の期日)のSQまで待たずに裁定取引による利益を確定することができるからである。
33業種中すべての業種が下げた。下落率トップ5は、鉱業(1位:原油安のため)、石油・石炭(2位:原油安のため)、不動産(3位:日銀の利上げ懸念のため)、輸送用機器(4位:円高・ドル安進行のため)、水産・農林(5位)となった。
コメント投稿
今週と来週は重要イベントが目白押しで控えているので・・・ 09月10日
昨日の米国株式相場は大きく反発した(DJIA +484.18 @40,829.59, NASDAQ +193.77 @16,884.60, S&P500 +62.63 @5,471.05)。ドル円為替レートは143円台前半での動きだった。本日の日本株全般は高安まちまちとなった。東証プライムでは、上昇銘柄数が802に対して、下落銘柄数は787となった。騰落レシオは131.25%。東証プライムの売買代金は3兆7829億円。
TOPIX -3 @2,577
日経平均 -57円 @36,159円
米国では、米連邦準備制度理事会(FRB)が利下げすることがほぼ確実な状況の中で前日急落したため割安感が高まり、この日は押し目買いにより株価は大幅反発した。主要3株価指数は揃って大幅反発した。ダウ工業株30種平均は一時650ドル以上上げた。今週水曜日には8月消費者物価指数(CPI)、木曜日には8月生産者物価指数(PPI)が発表されるが、その結果がFRBの利下げ幅を通常の0.25%にするのか大幅利下げの0.50%にするのかの決定に影響を与えるとマーケットは見ている。
本日9月10日の東京市場では、米国株の大幅反発を受けて、日経平均は高く始まったが売りに押されて前日比で反落する場面もあった。下げ幅は一時200円を超えたが、売りが一巡すると上げ幅も一時300円を超え、不安定な値動きだった。円高・ドル安基調の影響もあり、足元では下げる時は米国株以上に急落し、上げる時は米国株ほど上げない下方バイアスがかかった相場となっている。足元の不安定な値動きの背景には株価を大きく動かす重要イベントが目白押しで控えていることがある。今週には米CPIや米PPIなどの重要な経済指標発表を控えているだけでなく、来週には17~18日に米連邦公開市場委員会(FOMC)、19~20日には日銀の金融政策決定会合が待っている。
日経平均の日足チャートを見ると、昨日の陽線の終値に対して、本日の陰線の終値がほぼ出会うような「出会い線」で終えた。下から上に行こうとする勢いを上から下に下げる力が止めた形である。今週と来週は重要イベントが相次ぐので不安定な値動きが続くと見ている。
33業種中15業種が上げた。上昇率トップ5は、水産・農林(1位)、陸運(2位)、倉庫・運輸(3位)、空運(4位)、食料品(5位)となった。
コメント投稿
日経平均は大幅安で始まったが明確な下げ渋りを見せた 09月10日
先週金曜日の米国株式相場は大きく下落した(DJIA -410.34 @40,345.41, NASDAQ -436.83 @16,690.83, S&P500 -94.99 @5,408.42)。ドル円為替レートは142円台後半の前日比円高水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が536に対して、下落銘柄数は1,074となった。騰落レシオは120.86%。東証プライムの売買代金は4兆626億円。
TOPIX -18 @2,580
日経平均 -176円 @36,216円
先週金曜日の米国市場では、注目を集めていた8月米雇用統計で非農業部門雇用者数(NFP)が14.2万人(<予想16.1万人)と予想を下回った。6月分も7月分も下方修正し、雇用拡大が鈍化していると受け止められた。これにより米景気後退懸念が再燃し、株は軒並み売られて主要3株価指数は揃って大きく下落した。他方、失業率は改善した(前月4.3%から4.2%へ低下し、予想と一致)。また、平均賃金率は伸びた(前月比+0.4%>予想+0.3%;前年比+3.8%>予想+3.7%)。つまり、強弱が入混じった結果だった。米10年債利回りは前日の3.733%から3.709%へ下げたため、円高・ドル安が進んだ。米景気後退懸念を反映して、原油相場の国際的指標であるWTI先物は1バレル=67.17ドルまで低下してきた。
本日9月9日の東京市場では、先週金曜日に米国株が大幅下落したことを受けて、ほとんどの銘柄が大きく売られて日経平均の下げ幅は一時1,100円を超え、ザラバでは一時35,000円割れとなった。しかし、円高進行が一服して1ドル=143円台になると先物を中心に買い戻しが入り、下げ幅を縮小させて終えた。国内年金基金などがリバランス目的の買いを入れているとの観測も出た。東京エレクトロンやアドバンテストなど半導体関連銘柄の下げが大きく、東京エレクトロンは年初来安値を更新した。
日経平均の日足チャートを見ると、大きくギャップダウンして始まったが切り返して、長い下ひげを引いた陽線で終えた。明確な下げ渋りを示すローソク足だった。追加の大きな悪材料が出てこない限り、明日は大きく反発すると見る。本日大引け数分前で売り玉は全て成行で手仕舞いしました。
33業種中24業種が下げた。下落率トップ5は、輸送用機器(1位)、保険(2位)、海運(3位)、銀行(4位)、鉱業(5位)となった。
コメント投稿
8月米雇用統計の発表目前だが売り優勢 09月07日
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA -219.22 @40,755.75, NASDAQ +43.37 @17,127.66, S&P500 +16.66 @5,503.41)。ドル円為替レートは142円台後半の前日比円高水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が433に対して、下落銘柄数は1,163となった。騰落レシオは114.51%。東証プライムの売買代金は3兆8553億円。
TOPIX -23 @2,597
日経平均 -266円 @36,391円
米国では、景気後退懸念が再燃しており、翌日金曜日の8月米雇用統計の発表を控えて高安まちまちとなった。朝方発表された8月ADP民間部門雇用者数は弱い結果となった(9.9万人<前月分改定値11.1万人&予想14・55万人)。しかし、新規失業保険申請件数は強い結果となった(22.7万件<予想23.0万件)。10年債利回りは前日の3.768%から3.718%へ下げて引けた。
本日9月6日の東京市場では、8月の米雇用統計の発表を目前に控えて発表後の急激な動きに備えて売り優勢となった。外為市場で円高・ドル安が進み輸出関連銘柄を中心に売られ、日経平均は4日続落した。日経平均の下げ幅は一時400円を超えた。
日経平均の日足チャートを見ると、小高く上げて始まったが、売り優勢となり陰線で引けた。上向きの260日移動平均線で辛うじて留まったが、月曜日は下抜けしそうだ。しかし、8月初旬のようなパニック売りにはならいないとみているが、さてどうなるか。相場には常に「登り坂」、「下り坂」の他に「ま坂」があるので常に「心と建玉の準備」をしておく必要がある。
8月の米雇用統計の結果が予想よりも弱いと、9月のFOMCでは大幅利下げの期待が高まるため円高・ドル安がさらに進行することになり、その影響で日本株は売られてさらに下げると連想できるが、既にこの時間までに8月雇用統計の結果が判明している。
非農業部門の就業者数は前月比14万2千人の増加となったが市場予想(16万人増)を下回った。これは悪い材料。他方、失業率は4.2%と予想通りに低下し、平均時給は前月比0.4%増となり、市場予想(0.3%)を上回った。これは良い材料。好悪両方が入混じった結果だが、米国株式市場では売り優勢となっており、主要3株価指数は揃って下げている。日経平均の時間外取引では、9月7日午前0時15分現在、35,500円前後で推移している。来週月曜日の朝は大幅安で始まりそうだ。
33業種中28業種が下げた。下落率トップ5は、機械(1位)、鉄鋼(2位)、電気機器(3位)、非鉄金属(4位)、証券(5位)となった。
コメント投稿
米労働市場の過熱感は完全に解消したようだが・・・ 09月05日
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA +38.04 @40,974.97, NASDAQ -52.0 @17,084.30, S&P500 -8.86 @5,520.07)。ドル円為替レートは143円台前半の前日比円高水準での動きだった。本日の日本株全般は高安まちまちとなった。東証プライムでは、上昇銘柄数が784に対して、下落銘柄数は803となった。騰落レシオは110.48%。東証プライムの売買代金は4兆2056億円。
TOPIX -13 @2,621
日経平均 -391円 @36,657円
米国では、今週金曜日の8月米雇用統計の発表を控えて、様子見ムードが強まり、小動きとなった。それでも9月4日の「恐怖指数」と言われる株価の変動性指数VIXは節目の20を超えているので不安定である。
7月の米雇用動態調査(JOLTS)では7月JOLTS求人件数が予想を下回り(非農業部門求人件数767.3万件<予想810万件)、インフレが急上昇する前の2021年1月以来の低水準となった。失業者一人当たりの求人件数は1.07件(<1.2件:新型コロナウィルス感染が始まる直前)まで低下した。これにより労働市場の過熱感は新型コロナ禍が始まる前を下回るほどになり、過熱感は完全に解消した。9月の連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ幅が0.25%ではなく0.5%になる可能性が高くなり、先の金利低下を見越して米国債が買われたため、10年債利回りは前日の3.844%から3.757%へ低下した。また、2年債利回りも前日の3.888%から3.760%へ低下して、長短金利の逆転(短期金利>長期金利=景気後退の兆候)が解消した。
ただ、まだ大幅利下げが決定的とは言えない。「サーム・ルール」(直近3カ月の平均失業率が過去1年間の平均失業率を0.5ポイント上回れば景気後退が始まっているという経験則:景気の悪化により失業者が増えることを前提としている)をマーケットは警戒している。7月は0.53ポイントとなりマーケットに動揺が走った。ただし、この経験則の有効性は若干変化している。それは労働市場の変化に原因がある。最近は移民の急増により労働力人口が急拡大していることが主因でテクニカル的に失業率を高めていると推察できるからである。いずれにせよ、8月の雇用統計が残っている。
本日9月5日の東京市場では、米長期金利の低下を反映して円高・ドル安が進み自動車・機械などの輸出関連銘柄を中心に売られた。日経平均の下げ幅は一時700円を超えたが、下値では押し目買いが入って下げ幅を縮小した。7月JOLTSに続き8月米雇用統計の発表を控えて神経質な動きとなった。9月5日に日銀の高田創審議員が賃上げの持続性が確認できれば徐々に利上げするという趣旨の発言をし、株式相場の重しとなった。9月5日、厚生省は7月の毎月勤労統計(速報)を発表した。物価変動の影響を除いた実質賃金の前年同月比伸び率は2カ月連続でプラスとなった。
下値ではGPIFが買っているとマーケットでは噂になっている。GPIFのアセットアロケーションは、国内株(25%)、外国株(25%)、国内債(25%)、外国債(25%)に分散投資されているが、株価の下落などにより国内株の比率が下がるとリバランスのために買い増しをするからだ。8月初旬とは違い、今は追証による投げ売りリスクは小さくなっている。GPIFによる下値での買いと投げ売りリスクの低下の組み合わせは、安値になると投資家の買い安心感を増すのではないだろうか。
日経平均の日足チャートを見ると、続落したが上下に長いひげをひいた短陽線で終えた。25日移動平均線を完全に割り込んでいる。今日の下ひげが上向きの260日移動平均線に接するところまで下げてきている。中期的な視野で見ると、1980年以降の日本株の経験則では260日移動平均線が上向きである限り、ある程度下げるとまた反発しやすいので押し目買いが有効となる。百聞は一見に如かず。興味ある人は自分で確認することを勧めます。
33業種中18業種が下げた。下落率トップ5は、保険(1位)、医薬品(2位)、海運(3位)、輸送用機器(4位)、小売り(5位)となった。
コメント投稿
株価急落で8月初旬のデジャブ―のようだが・・・ 09月04日
昨日の米国株式相場は大幅下落した(DJIA -616.15 @40,936.93, NASDAQ -577.33 @17,136.30, S&P500 -119.47 @5,528.93)。ドル円為替レートは145円台前半の前日比円高水準での動きだった。本日の日本株全般は大きく下げた。東証プライムでは、上昇銘柄数が97に対して、下落銘柄数は1,528となった。騰落レシオは117.83%。東証プライムの売買代金は5兆1062億円。
TOPIX -100 @2,633
日経平均 -1,639円 @37,048億円
米国では、8月ISM製造業購買担当者景況感指数(PMI)(47.2<予想47.9)と8月S&Pグローバル製造業PMI確定値(47.9<7月48.0)が予想を下回った。これにより再び景気後退懸念が強まり、エヌビディアを始めとする半導体関連銘柄が強烈に売り込まれた。8月初旬の暴落の初動を彷彿とさせた。景気後退の懸念を反映して米10年債利回りは先週末の3.911%から3.831%へ低下した。しかし、長期金利低下による株価浮揚効果よりも、景気後退懸念による株価下押し効果の方がはるかに大きかった。主要3株価指数は揃って大きく下げた。フィラデルフィア半導体株指数(SOX)も7.7%安となり、今年最大の下落率となった。もとも利下げを見込んで株価が史上最高値を更新し続けるほどの高値圏に達していたため高値警戒感が強く、少し悪い指標が出るだけで売りがどっと出る。米司法省から反トラスト法違反の疑いで調査を開始されたエヌビディアが9.9%も急落し、たった1日で41兆円(日本の国家予算の4割近く)の時価総額が吹き飛んだ。
本日9月4日の東京市場では、米景気後退懸念によるハイテク株を中心とした米国株の急落と、米長期金利の低下による円高・円安の悪材料を受けて、半導体関連銘柄をはじめとして大きく売り込まれた。日経平均の下げ幅は一時1,800円を超えた。東京エレクトロンとアドバンテストの2銘柄だけで日経平均を345円押し下げた。日経平均の下げ幅は今年3番目に大きく、歴代では5番目の大きさだった。
今年8月初旬の暴落時のデジャブ―のように、再びちょっとした景気指標の悪化がきっかけて株価が急落し始めた。そしてまた6日に「運命の」雇用統計の発表がある。この結果が景気後退を示すようなものならまた大きく売り込まれる可能性が高いが、他方、既に1回経験しているため今回は再びそうなったとしても、もう少し冷静に反応するかもしれない。
ただ、程度はわずかだが景気後退を暗示する経済指標は8月の米ISM製造業購買担当者景況感指数だけでない。一つは原油相場の下落。世界的に経済が不活発になれば原油に対する需要は低下し、価格は下がる。9月4日現在、原油価格の国際指標であるWTIは70ドルを割り込んで来た。もう一つは8月のPMI指数(S&Pグローバルが算出)は米国以外のドイツ、フランス、オランダ、そして日本でも好景気と不景気の分水嶺である50を割り込んでいる。特に中国は4カ月連続で50を下回っている。つまり、このPMI指標で判断する景気悪化懸念は米国だけでなく世界的な現象である。だからこそ、海外需要に大きく依存する日本企業、つまり日本株の下落率が一番大きいと解釈できる。
日経平均の日足チャートを見ると、ほぼ横向きの25日移動平均線を割り込んだ。数日以内にまた浮上できるかどうかに注目している。今週金曜日に8月の米雇用統計が発表されるまで、日本株も不安定な動きを続けると見ている。
33業種中すべての業種が下げた。下落率トップ5は、鉱業(1位)、非鉄金属(2位)、証券(3位)、石油・石炭(4位)、銀行(5位)となった。
コメント投稿
国内長期金利の上昇 ➡ 銀行、保険が上昇 09月03日
昨日の米国株式市場は祝日のため休場だった。ドル円為替レートは146円台後半から147円台前半の前日比円安水準での動きだった。本日の日本株全般は上昇する銘柄の方が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,230に対して、下落銘柄数は364となった。騰落レシオは122.13%。東証プライムの売買代金は3兆3167億円。
TOPIX +17 @2,733
日経平均 -15円 @38,686円
昨日の米国株式市場は祝日のため休場だった。本日の東京市場では、昨日に続きさらに円安・ドル高に振れた円相場を手掛かりに輸出関連銘柄を中心に買われ、日経平均の上げ幅は一時200円を超えた。しかし、結局、東京エレクトロンやアドバンテストなどの値がさ半導体株が売られて株価指数を押し下げた。39,000円前後では戻り売り圧力が強かった。国内長期金利が上昇して来たため、収益拡大が見込まれるメガバンク株や保険株が目立って買われて上昇した。他方、海運大手株は下げが顕著になっているが、チャートを見ると定石通りの下げである(➡優利加塾生は第65期売買ルール構築の講義動画でこの定石を確認してください)。
日本時間の今夜、8月のサプライマネジメント協会(ISM)製造業景況感指数の発表がある。相次ぐ雇用関連の統計発表を前に、その前哨戦とも言える。米連邦準備制度理事会(FRB)は9月には利下げに踏み切るのはほぼ確実だろう。問題はその利下げ幅である。標準で0.25%だが、景気減速懸念が強くなれば0.5%の大幅利下げもありうるとマーケットは期待している。利下げ幅が0.25%なら織り込みのため当面は若干円安・ドル高に振れ、0.5%なら円高・ドル安に振れるのではないかと見ているが、さてどう動くか。
日経平均の日足チャートを見ると、上下にひげを引いた短陰線で終え、値動きは昨日の陰線の上下の範囲内での小動きだった。米国市場が休場だったこともあり材料不足が主な原因と考えられる。
33業種中23業種が上げた。上昇率トップ5は、銀行(1位)、保険(2位)、陸運(3位)、繊維製品(4位)、小売り(5位)となった。
コメント投稿
60日・10日・25日移動平均線の上に株価が浮上 09月03日
先週金曜日の米国株式相場は上げた(DJIA +228.03 @41,563.08, NASDAQ +197.19 @17,713.62, S&P500 +56.44 @5.648.40)。ドル円為替レートは146円台の先週末比円安・ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄の方が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が628に対して、下落銘柄数は967となった。騰落レシオは126.11%。東証プライムの売買代金は3兆3216億円。
TOPIX +3 @2,716
日経平均 +53円 @38,701円
米国では、米連邦準備制度理事会(FRB)が注目する7月個人消費支出(PCE)価格指数が予想通りの伸びだった(前月比+0.2%=前月比横ばい、前年比+2.5=前年比横ばい<予想+2.6%)ことで、9月の利下げ期待がさらに高まった。主要3株価指数は揃って上昇し、ダウ工業株30種平均は4日続伸して史上最高値を更新し続けた。PCE物価指数がほぼ市場想通りとなりサプライズ感が乏しいことから、一部で期待されていたような利下げ幅0.5%という大幅利下げ見通しは後退した。その結果、10年債利回りは3.867%から3.909%へ上げ、円相場は円安・ドル高方向へ動いた。今週末に発表される米8月雇用統計(特に、非農業部門雇用者数、失業率、平均賃金の3つ)へ市場の関心が移った。9月2日はレイバーデイの祝日のため休場となる。
本日9月2日の東京市場では、ダウ工業株30種平均の連日の史上最高値更新と円安・ドル高を追い風に買い優勢で始まった。日経平均の上げ幅は一時400円を超えた。ザラバでは約1カ月ぶりに39,000円台を回復したが、今週末には8月米雇用統計の発表を控えていることと、米国株式市場が3連休を控えていることも重なり、そこからは利益確定売りや戻り待ちの売りに押し戻されて上げ幅を縮小して終えた。今日のところ、米金利上昇は利ザヤ拡大を見越して銀行株を押し上げ、円安・ドル高は自動車株を上げた。
9月4日には7月の米雇用動態調査(JOLTS )、6日には8月ADP全米雇用レポートの発表に続き、6日の8月米雇用統計と、雇用統計関連の経済指標が相次いで発表される。もし、米雇用統計関連の経済指標の結果が予想以上に弱いと、9月の利下げ幅が通常の0.25%ではなく0.5%に拡大するとの期待が強くなるため円高・円安への振れが大きくなる。すると輸出関連銘柄をはじめとして日本株全般は売り優勢となり下げる。通貨オプション市場で「リスク・リバーサル」という指標がある。ドルプットとドルコールのどちらが強いかを示す指標で、3か月物の値はマイナス1.7台である。8月初旬のマイナス3%超よりは小さくなったものの、マーケットは依然として円高リスクに備えていることを示す。まあ、向こう1年先を見ると日米金利差の縮小がほぼ不可避であることを考えれば当たり前ではあるが。
日経平均の日足チャートを見ると、ギャップアップして2日続伸したが寄り付き後は売りに押されて陰線で終えた。しかし、終値ベースで60日、10日、25日の順で各移動平均線すべての上に株価が浮上して来た。各移動平均線の順番が10日>25日>60日の順番になった時(株価サイクル③)が一番株価は安定して上昇しやすいが、今はまだそこまでは達していない。それでも悪くはない。
33業種中19業種が上げた。上昇率トップ5は、非鉄金属(1位)、銀行(2位)、その他金融(3位)、保険(4位)、証券(5位)となった。
コメント投稿
↑ページのトップへ
|
|